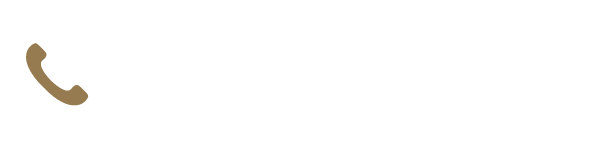ご依頼お待ちしております!!
先妻の子に相続させないことは可能?遺言書でできる対策と知っておくべき知恵を解説

再婚家庭における相続で、特に多く寄せられるご相談の一つが
「先妻の子に相続させないことはできないのか」という切実な悩みです。
「長年連れ添ってきた今の配偶者や子どもに、できるだけ多くの財産を残したい」
「正直、面識もほとんどない先妻の子と相続で関わりたくない」
そう感じることは、決して身勝手なことではありません。
しかし一方で、相続には感情だけでは割り切れない、明確な法律ルールが存在します。
誤った知識や思い込みのまま対策を進めてしまうと、
「遺言書を書いたのにトラブルになった」
「かえって家族が金銭請求を受けてしまった」
といった事態を招くことも少なくありません。
では、先妻の子に相続させないことは本当に可能なのか。
遺言書を作成すれば、すべて解決するのでしょうか。
この記事では、行政書士の視点から、まず押さえておくべき前妻の子の相続権の基本ルールを整理したうえで、遺言書で「できること」と「できないこと」、そして今の家族を守るために知っておくべき現実的な対策と知恵を、具体例を交えながらわかりやすく解説していきます。
「あとで考えよう」では手遅れになるのが相続対策です。
後悔しない選択をするために、まずは正しい知識を身につけていきましょう。
前妻の子の相続権、まず知っておくべき3つの基本原則
具体的な対策を考える前に、まずは法律で定められている相続の基本的なルールを3つの原則に分けて理解しておくことが不可欠です。ここを正確に押さえることが、すべての対策のスタートラインとなります。
原則1:前妻の子は「常に」「後妻の子と平等な」相続人です
最も重要な原則は、前妻との間に生まれた子どもも、法律上の実子である限り「常に」法定相続人になるということです。
「離婚すれば、父親と前妻の子の親子関係は切れるのではないか?」というのは、非常によくある誤解です。しかし、法律上の親子関係は、両親の離婚によって消滅することはありません。たとえ何十年も会っていなくても、音信不通であったとしても、その事実が相続権に影響することはないのです。
さらに、その相続する権利の割合(法定相続分)は、現在の配偶者との間に生まれた子どもと完全に平等です。前妻の子だからといって、相続分が少なくなるということは一切ありません。
原則2:離婚した「前妻」に相続権はありません
一方で、離婚した元配偶者である「前妻」自身には、相続権は一切ありません。相続人となる「配偶者」とは、亡くなった時点で法律上の婚姻関係にある人のみを指すためです。
したがって、遺産の分割について話し合う当事者は、あくまで前妻との間に生まれた「子ども」本人となります。
ただし、注意点が一つあります。もし前妻の子が未成年であった場合、その親権者である前妻が、子どもの法定代理人として遺産分割協議に参加する可能性があります。
原則3:法定相続分の計算方法
では、遺言書がない場合、法律で定められた相続分(法定相続分)は具体的にどのようになるのでしょうか。計算方法はシンプルです。
まず、配偶者は常に相続人となり、その相続分は全体の2分の1です。そして、残りの2分の1を、すべての子ども(後妻の子も前妻の子も含む)の人数で均等に分けます。
例えば、相続人が「後妻」「後妻の子1人」「前妻の子1人」の合計3人だった場合の法定相続分は以下のようになります。
| 相続人 | 法定相続分 | 備考 |
|---|---|---|
| 後妻 | 1/2 | – |
| 後妻の子 | 1/4 | 残りの1/2を子2人で分けるため |
| 前妻の子 | 1/4 | 後妻の子と完全に平等 |
このように、遺言書がなければ、会ったことのない前妻の子にも、法律上は遺産の4分の1を取得する権利が認められているのです。
「今の家族に多く財産を残したい」を叶える最も有効な対策は遺言書
法定相続分のルールをご理解いただいた上で、「やはり、長年連れ添った今の家族に、できるだけ多くの財産を残したい」と考えるのは当然の感情です。その想いを法的に実現するための最も重要かつ効果的な方法が「遺言書」の作成です。
遺言書があれば、法定相続分とは異なる割合で財産を分けることが可能になります。亡くなった方の最終的な意思として、遺言書の内容は法定相続分よりも優先されるのです。
遺言書を作成する最大のメリット:遺産分割協議が不要になる
遺言書を作成する最大のメリットは、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)が不要になる点です。
遺言書がない場合、預金の解約や不動産の名義変更といったすべての相続手続きにおいて、相続人全員の署名と実印での押印、そして印鑑証明書が必要になります。つまり、後妻が前妻の子に連絡を取り、事情を説明し、書類に署名・押印してもらうといった、精神的にも事務的にも負担の大きい手続きを経なければなりません。
しかし、「妻〇〇に不動産を、長男〇〇に預金を相続させる」といった内容の遺言書さえあれば、他の相続人の協力や同意がなくても、指定された人が単独で手続きを進めることができます。これにより、相続手続きは格段にスムーズになり、残された家族の負担を大幅に軽減できるのです。
遺言書を作るなら「公正証書遺言」がおすすめ
遺言書には、自分で手書きする「自筆証書遺言」と、公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書遺言」の2種類が主にあります。
自筆証書遺言は手軽で費用もかかりませんが、日付の記載漏れや押印忘れといった形式的な不備で無効になってしまうリスクや、内容が曖昧で解釈をめぐって争いになる可能性があります。
特に、前妻の子がいるなど、将来的に相続争いが予想されるケースでは、形式不備で無効になるリスクが極めて低く、内容の証明力も非常に高い「公正証書遺言」の作成を強く推奨します。自筆証書遺言については、相続開始後にその作成の真否等を争う裁判が起こされやすく、かえって紛争の火種となる可能性があるためです。法律の専門家である公証人が関与して作成するため、ご自身の意思を最も確実に実現できる方法と言えるでしょう。
遺言執行者を指定して手続きを円滑に
遺言書では、その内容を実現するための責任者である「遺言執行者」を指定することができます。これは非常に便利な制度です。
例えば、後妻を遺言執行者に指定しておけば、遺言書の内容に沿った手続き(預金の解約や不動産の名義変更など)を、他の相続人の同意や実印がなくても、後妻の権限で単独で進めることが可能になります。これにより、相続手続きはさらに迅速かつ円滑に進みます。
遺言書があっても越えられない壁「遺留分」とは?
「なるほど、『妻に全財産を相続させる』という公正証書遺言を作成すれば、もう万全だな」 そうお考えになったかもしれませんが、実はまだ安心はできません。遺言書という強力なツールをもってしても、越えることができない「壁」が存在します。それが「遺留分(いりゅうぶん)」という権利です。
ここで、二つの重要な言葉を明確に区別しておきましょう。 「法定相続分」とは、遺言書がない場合に法律が定める相続割合です。一方で「遺留分」とは、遺言書がある場合でも、特定の相続人に保障される最低限の取り分です。この二つは全く別の制度であり、遺言書はこの「遺留分」の壁を越えることはできません。
遺留分は遺言書でも奪えない最低限の権利
遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に法律で保障された「最低限の遺産の取り分」のことです。これは、残された家族の生活を保障するためのセーフティーネットのような制度であり、被相続人の意思(遺言)よりも優先される非常に強力な権利です。
つまり、たとえ遺言書に「前妻の子には一切相続させない」と書かれていたとしても、前妻の子には、この遺留分を請求する権利が法律上残されているのです。
前妻の子の遺留分はいくら?
では、前妻の子の遺留分は具体的にどれくらいの割合になるのでしょうか。子の遺留分は、法定相続分のさらに半分です。
具体例として、相続人が「後妻」「後妻の子2人」「前妻の子1人」の合計4人、遺産総額が6,000万円だった場合の遺留分を計算してみましょう。この場合、法定相続分は後妻が1/2、子ども3人で残りの1/2を分けるため、子1人あたり1/6となります。
| 相続人 | 法定相続分 | 遺留分 | 遺留分の金額(遺産6,000万円の場合) |
|---|---|---|---|
| 後妻 | 1/2 (3,000万円) | 1/4 | 1,500万円 |
| 後妻の子① | 1/6 (1,000万円) | 1/12 | 500万円 |
| 後妻の子② | 1/6 (1,000万円) | 1/12 | 500万円 |
| 前妻の子 | 1/6 (1,000万円) | 1/12 | 500万円 |
このケースでは、前妻の子一人ひとりに対して、最低でも500万円を受け取る権利が法律で保障されていることになります。
遺留分を無視すると「遺留分侵害額請求」という金銭トラブルに
もし、前妻の子の遺留分を無視して「全財産は後妻とその後妻の子に相続させる」という遺言書に基づき手続きを進めた場合、どうなるのでしょうか。
その場合、前妻の子は、遺産を多く受け取った後妻やその子に対して、「私の遺留分が侵害されたので、その分のお金を支払ってください」と請求することができます。これを「遺留分侵害額請求」と呼びます。
この請求は法律で認められた正当な権利であり、請求された側は原則として、その支払いに応じなければならない義務があります。話し合いがこじれれば、最終的には裁判にまで発展する可能性もあり、これこそが最も避けたい金銭トラブルの典型例です。
トラブルを避けるための遺言書の書き方の工夫
遺留分という強力な権利の存在を踏まえた上で、将来のトラブルを未然に防ぎ、できるだけ円満な相続を実現するためには、遺言書の書き方にいくつかの工夫を凝らすことが重要です。
対策1:遺留分に配慮した内容にする
最も確実で根本的なトラブル回避策は、あらかじめ前妻の子の遺留分に相当する財産を相続させる内容の遺言書を作成しておくことです。
先の例で言えば、遺産の12分の1に相当する預貯金などを前妻の子一人ひとりに相続させる、と明記します。確かに「今の家族にすべてを」という希望は100%は叶いませんが、この方法をとることで、将来、後妻やその子が「遺留分侵害額請求」という金銭トラブルに巻き込まれるリスクそのものを無くすことができます。残される家族の平穏を第一に考えるのであれば、最も賢明な選択と言えるでしょう。
対策2:「付言事項」で想いと理由を伝える
遺言書には、法的な効力を持つ本文とは別に、最後の部分に「付言事項(ふげんじこう)」として、家族へのメッセージを自由に書き残すことができます。これには法的な拘束力はありませんが、相続を円満に進める上で非常に大きな効果を発揮することがあります。
なぜこのような財産の分け方にしたのか、その理由や想いを、ご自身の言葉で正直に綴るのです。
(付言事項の記載例)
- 「長年連れ添い、病気の際には献身的に看護してくれた妻Bの老後の生活が非常に心配なため、自宅不動産と預金の多くを妻に残すことにした。前妻の子であるDには、これまでの養育費とは別に、感謝の気持ちとしてこの遺産を残すので理解してほしい。」
このような理由が丁寧に記されていれば、前妻の子も遺言の内容に感情的に納得しやすくなり、無用な争いを避けられる可能性が高まります。
対策3:「付言事項」で遺留分請求をしないようお願いする
付言事項の中で、上記のような納得できる理由を述べた上で、「どうかこの遺言の内容を尊重し、遺留分侵害額請求はしないでもらえないだろうか」と、丁寧に懇願するメッセージを付け加えることも、トラブル防止に繋がる可能性があります。
ただし、この方法には注意が必要です。遺留分という制度を知らなかった相続人に、かえってその権利の存在を知らせてしまう「両刃の剣」となる可能性も否定できません。これはあくまで心理的な効果を期待するものであり、法的拘束力はないことを十分に理解した上で、戦略的な判断が求められます。
遺言書以外の対策:効果を高める3つの方法
遺言書は相続対策の核となりますが、他の生前対策と組み合わせることで、より効果的に「今の家族に財産を多く残す」という目的を達成することが可能になります。
方法1:生命保険の活用
最も有効な「合わせ技」の一つが、生命保険の活用です。 夫を契約者および被保険者とし、保険金の受取人を後妻やその後妻の子に指定しておきます。こうして支払われる死亡保険金は、法律上、相続財産とはみなされず「受取人固有の財産」として扱われます。
これは、原則として遺産分割協議の対象にならず、前妻の子と分ける必要がない現金を、確実に今の家族の手元に残せることを意味します。例えば、成功事例では、保険金を活用して、後妻が相続税や当面の生活費に充てるための現金を確保しつつ、円満な相続を実現しました。
ただし注意!生命保険金が遺留分の計算対象になる「特段の事情」
原則として遺留分の対象外となる生命保険金ですが、例外が存在します。判例では、保険金の額が遺産総額に対して著しく大きいなど「特段の事情」がある場合、例外的に遺留分の計算基礎に含めるべき、と判断される可能性があります。
実務上、保険金の額が遺産総額の70%~80%を超えるような極端なケースでは、この「特段の事情」に該当するリスクが高まります。例えば、遺産のほとんどが不動産で預貯金がごくわずかな状態で、多額の生命保険を後妻のみが受け取るような設計は、将来のトラブルの火種となりかねません。生命保険は強力なツールですが、万能ではないことを理解し、専門家と相談の上でバランスの取れた設計をすることが重要です。
方法2:生前贈与
夫が元気なうちに、後妻やその子へ財産を少しずつ贈与しておく方法です。これにより、将来の相続発生時に遺産の総額を減らすことができ、結果的に前妻の子が請求できる遺留分の金額を抑える効果が期待できます。
しかし、この方法には専門的な注意点がいくつかあります。
- 相続税の計算対象期間:2024年の税制改正により、亡くなる前7年以内に行われた贈与は相続税の計算対象となります(改正前は3年)。
- 遺留分の計算対象期間:相続人への生前贈与は、相続開始前10年以内に行われたものまで遺留分の計算基礎に加算されます。
- 不動産贈与のコスト:不動産を生前贈与する場合、登録免許税(固定資産税評価額の2%)が相続時(0.4%)の5倍になるほか、不動産取得税も課税されるため、現金での贈与に比べてコストが非常に高くなります。
方法3:死因贈与契約
これは、生前に「私が死んだら、この不動産を妻の〇〇にあげます」という内容の契約を、贈与者(夫)と受贈者(後妻)の間で結んでおく方法です。
遺言が一方的な意思表示であるのに対し、死因贈与は双方の合意に基づく「契約」であるという点が異なります。これも、特定の財産を確実に特定の人に残すための選択肢の一つとなり得ます。
まとめ:円満な相続の鍵は「遺留分への配慮」と「事前の準備」
再婚家庭における相続問題は非常にデリケートですが、正しい知識を持って事前に対策を講じることで、将来のトラブルを回避し、円満な解決を目指すことは十分に可能です。
最後に、この記事の最も重要なポイントをまとめます。
- まず、前妻の子にも後妻の子と完全に平等な相続権と、遺言書でも奪えない「遺留分」があるという法律上の現実を、冷静に受け止めることがすべての第一歩です。
- 感情的な対立や将来の金銭トラブルを避けるための最善の策は、**「前妻の子の遺留分に配慮した内容の公正証書遺言」**を作成することです。
- さらに、生命保険や計画的な生前贈与といった対策を組み合わせることで、よりご自身の希望に沿った形で、今の家族へ多くの財産を承継させることが可能になります。
最も大切なことは、問題を先送りにせず、ご自身が元気で判断能力がしっかりしているうちに、行動を起こすことです。相続は、ご家族の状況によって最適な対策が異なります。ぜひ一度、相続に詳しい専門家に相談し、ご自身の家族にとって最善の道筋を見つけ、安心して未来を迎えるための準備を始めてください。