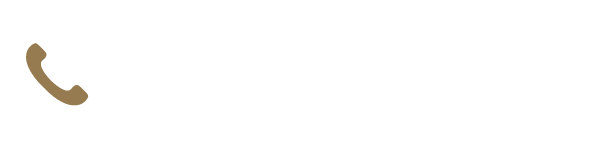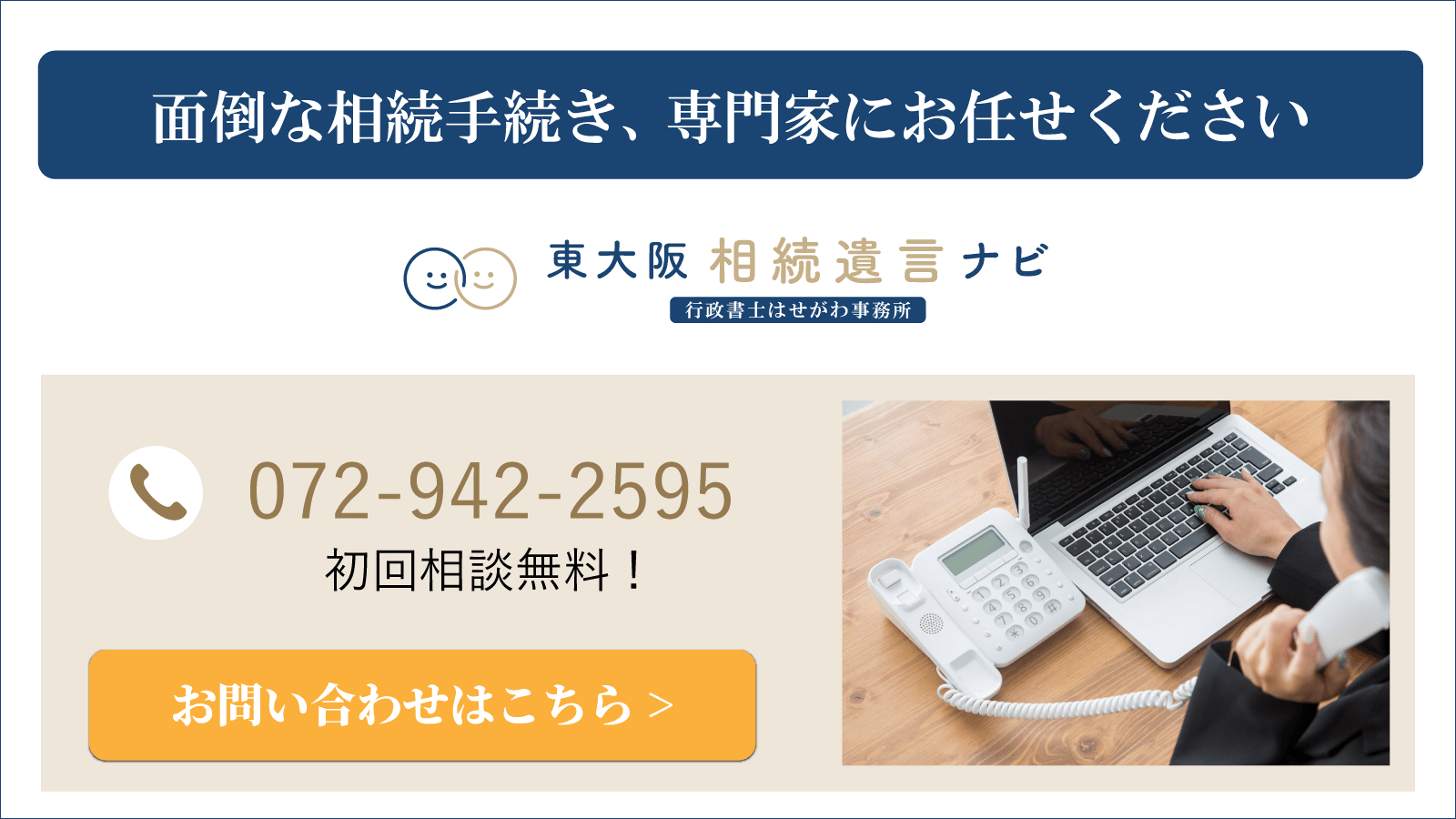初回相談無料!
銀行の相続手続きを自分で行う方法|必要書類から口座凍結の注意点まで徹底解説

ご家族が亡くなった際、ほとんどのケースで必要となるのが銀行口座の相続手続きです。不動産や株式と異なり、預金口座は多くの方が保有しているため、避けては通れない手続きと言えるでしょう。
この記事は、専門家に依頼せずご自身で銀行の相続手続きを進めたいと考えている方のために、手続きの全体像から注意点までを網羅した完全ガイドです。手続きの流れ、最重要ポイントである口座凍結の仕組み、ケース別の必要書類、そして緊急時に役立つ「預金の仮払い制度」まで、分かりやすく徹底解説します。
口座凍結の仕組みと注意点
銀行の相続手続きを進める上で、最初に理解しておくべきなのが「口座凍結」です。これは手続きの起点となると同時に、いくつかの重要な注意点を含んでいます。
口座が凍結されるタイミング
預金口座は、銀行が口座名義人の死亡を知った瞬間に凍結されます。相続人が手続きのために銀行に連絡をした時点で、その事実が伝わり凍結されるのが一般的です。
凍結されるとどうなるか
口座が凍結されると、ATMからの引き出しはもちろん、預け入れ、振込、公共料金やクレジットカードの自動引き落としなど、すべての取引が停止します。故人の預金通帳を確認し、もし継続的な引き落としがある場合は、事前に支払い方法の変更手続きをしておくと安心です。
【要注意】凍結前の安易な預金引き出しのリスク
「凍結される前にキャッシュカードで引き出してしまえば良い」と考えるのは非常に危険です。故人のキャッシュカードを使って預金を引き出す行為は、法律上、すべての遺産(借金などのマイナスの財産も含む)を無条件に相続する『単純承認』をしたとみなされ、原則として相続放棄が認められなくなります。後から多額の借金が発覚しても、相続を拒否できなくなる重大なリスクがあるため、絶対に行わないでください。

預金口座の相続方法は2種類:名義変更と解約払戻し
故人の預金口座を相続する方法には、大きく分けて2つの選択肢があります。
- 名義変更
故人が利用していた口座の支店や口座番号はそのままに、名義人だけを相続人の一人に変更する方法です。この場合、新しい銀行印の登録などの手続きが必要になります。公共料金の引き落としや年金の受け取りなどでその口座を継続して利用したい場合に選択されることがあります。 - 解約払戻し
故人の口座を完全に解約し、残高を利息とともに相続人が指定する口座に振り込んでもらう方法です。特別な理由がない限り、手続きがシンプルで分かりやすいこちらの解約払戻しを選択することをおすすめします。
自分で行う銀行の相続手続き、5つのステップ
銀行の相続手続きは、一般的に以下の流れで進みます。
銀行へ連絡し、死亡の事実を伝える
まず、故人が口座を持っていた銀行の支店窓口や相続専門センターに電話し、口座名義人が亡くなったことを伝えます。その際、『相続手続きに必要な書類の一覧』や銀行所定の『相続届』の郵送を依頼しておくと、その後の手続きがスムーズに進みます。前述の通り、この連絡によって口座が凍結され、正式な相続手続きが開始されます。
必要書類を収集する
次に、手続きに必要な書類を集めます。必要書類は遺言書の有無や各金融機関の方針によって異なります。どのような書類が必要になるか、詳しくは次のセクションで解説します。
銀行所定の相続届を取得・記入する
ほとんどの銀行では、独自の相続手続き専用の用紙(「相続届」など)を用意しています。この書類に、相続人全員の署名と実印での押印が必要となるのが一般的です。用紙は銀行の窓口で受け取るか、郵送で取り寄せます。
書類一式を銀行窓口へ提出する
収集した書類と記入済みの相続届を、銀行の窓口へ提出します。メガバンクなどではどの支店でも受け付けてくれることが多いですが、信用金庫などの場合は口座があった支店での手続きを求められることもあるため、事前に確認しましょう。
手続き完了と払戻し
提出した書類に不備がなければ、銀行側での確認・処理が進められます。手続き完了までには通常2週間〜1ヶ月程度の時間がかかり、その後、指定した相続人の口座へ預金が振り込まれます。
【ケース別】銀行の相続手続き 必要書類チェックリスト
必要となる書類は、故人が遺言書を残していたかどうかで大きく異なります。ここでは代表的な2つのケースに分けて、必要な書類をリストアップします。
遺言書がある場合の必要書類
- 遺言書
- 亡くなった方(被相続人)の戸籍謄本
- 預金を相続する方(または遺言執行者)の印鑑証明書
- 銀行所定の相続届
- 亡くなった方の通帳・キャッシュカード
遺言書がなく、遺産分割協議書で手続きする場合の必要書類
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印の押印があるもの)
- 亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本などすべて)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 銀行所定の相続届
- 亡くなった方の通帳・キャッシュカード
書類に関するよくある質問 (Q&A)
- 通帳やキャッシュカードを紛失してしまいました。手続きはできますか?
-
はい、問題なく手続きできる場合がほとんどです。どこの金融機関に口座があったかさえ分かっていれば、通帳やカードがなくても手続きを進めることは可能です。
- 印鑑証明書や戸籍謄本に有効期限はありますか?
-
多くの銀行では、印鑑証明書は発行後3ヶ月または6ヶ月以内のものを求められます。一方で、戸籍謄本については特に有効期限を定めていないことがほとんどです。
- 提出した戸籍などの原本は返してもらえますか?
-
ほとんどの場合、銀行に『原本還付(げんぽんかんぷ)希望』と伝えれば、コピーを取った後に戸籍謄本などの原本を返却してもらえます。ただし、金融機関によっては返却しない方針のところもあるため、提出時に必ず確認するようにしましょう。
特例:葬儀費用などに使える「預金の仮払い制度」とは?
口座が凍結されても、葬儀費用などの緊急の支払いに対応するため、「預金の仮払い制度」という特例が設けられています。
- 制度の概要
この制度を利用すると、遺産分割協議が完了する前でも、相続人の一人が単独で(他の相続人の同意なく)預金の一部を引き出すことができます。葬儀費用や当面の生活費など、急な出費に充てることが想定されています。 - 引き出せる金額の上限
引き出せる金額の上限は、「150万円」または「口座残高 × 1/3 × その相続人の法定相続分」のいずれか低い方の金額となります。 例えば、口座残高が600万円で、法定相続人が配偶者と子供2人(法定相続分は配偶者1/2、子供各1/4)の場合、子供1人が引き出せる上限額は「600万円 × 1/3 × 1/4 = 50万円」となり、150万円より低いため50万円が上限です。 - 利用する際の注意点
この制度は便利ですが、注意点もあります。まず、手続きには一定の書類が必要で、即日で引き出せるとは限らないため、葬儀費用の支払いに間に合わない可能性があります。また、引き出したお金を葬儀費用や故人の未払金など、緊急性の高い支払い以外に使うと「単純承認」とみなされ、後から相続放棄ができなくなるリスクがあるため、使途には十分注意が必要です。
まとめ
銀行の相続手続きについて、ご自身で行うためのポイントを解説しました。
- 銀行が名義人の死亡を知った瞬間に口座は凍結され、一切の取引が停止する。
- 凍結前に預金を引き出す行為は「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなるリスクがある。
- 手続きは、銀行への連絡、書類収集、相続届の記入・提出、払戻しという流れで進む。
- 必要書類は遺言書の有無で異なり、戸籍謄本や印鑑証明書などが求められる。
- 葬儀費用など緊急の場合は、他の相続人の同意なく一部を引き出せる「仮払い制度」も利用できる。
ご自身で手続きを行えば専門家への依頼費用を節約できますが、戸籍謄本の収集や銀行とのやり取りには、相応の時間と手間がかかることも事実です。もし手続きが複雑で難しいと感じたり、多忙で時間を確保できなかったりする場合には、行政書士などの専門家に相談することも有効な選択肢です。専門家であれば、手間のかかる出生から死亡までの戸籍謄本の収集、遺産分割協議書の作成、そして各金融機関との折衝まで、相続手続きのすべてを正確に代行することが可能です。