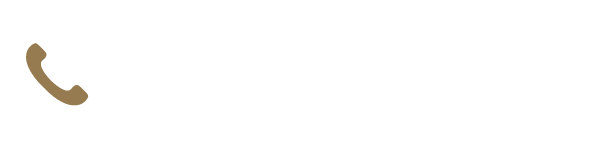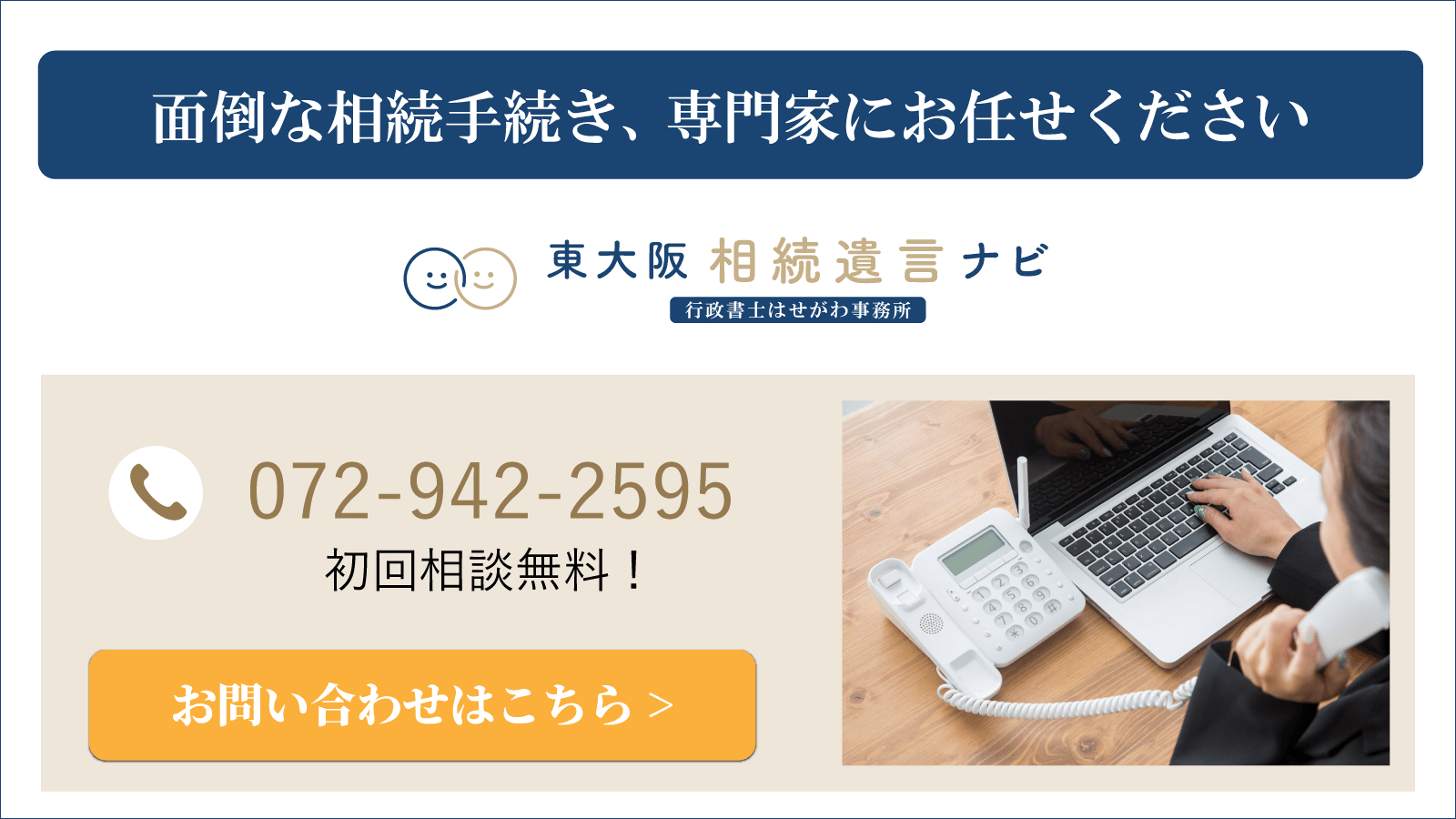初回相談無料!
相続放棄をしても遺族年金はもらえる?借金があっても安心な理由と注意点を解説

「夫に多額の借金があるため相続放棄をしたい。でも、今後の生活のために遺族年金は受け取りたい。相続放棄をすると遺族年金ももらえなくなるのでは?」
このようなご不安を抱えて相談に来られる方は少なくありません。大切な方を亡くされた悲しみの中で、借金の問題と今後の生活費の問題が重なり、大きな心配をされていることと思います。
結論から言うと、相続放棄をしても遺族年金を受け取ることは可能です。
この記事では、なぜ相続放棄をしても遺族年金が受け取れるのか、その法的な理由と、相続放棄に関する基本的な注意点、そして遺族年金の他に受け取れるお金について、相続問題に精通した司法書士がわかりやすく解説します。
なぜ相続放棄をしても遺族年金は受け取れるのか?
相続放棄をしても遺族年金を受け取れる理由は、遺族年金が「相続財産」ではないからです。これには主に2つの法的な根拠があります。
遺族年金は「相続財産」ではない
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産を一切引き継がないための手続きです。ここでいう「財産」には、不動産や預貯金といったプラスの財産だけでなく、借金や保証人の地位といったマイナスの財産もすべて含まれます。
遺族年金は、亡くなった方が遺した財産ではなく、法律の規定に基づいて遺族に直接支払われるものです。そのため、そもそも相続の対象となる「相続財産」には含まれません。
遺族年金は受給者「固有の権利」
遺族年金は、国民年金法や厚生年金保険法といった法律に基づき、残された遺族の生活保障を目的として支給されるものです。これは、受給権者である遺族自身が持つ「固有の権利(年金受給権)」とされています。
つまり、亡くなった方の財産とは切り離された、遺族ご自身の権利として受け取るお金なのです。したがって、亡くなった方の財産をすべて放棄する「相続放棄」をしても、ご自身の固有の権利である遺族年金は問題なく受け取ることができます。
裁判所の判例も認めている
この考え方は裁判所の判例でも確立されており、例えば大阪家庭裁判所の昭和59年4月11日の審判では、遺族年金は相続法とは別個の立場で支給されるものであり、被相続人の遺産とは解されないと判断されています。このように、法的な解釈としても定着しているため、安心して手続きを進めることができます。
そもそも「相続放棄」とは?基本と注意点
相続放棄について正しく理解しておくことも重要です。基本的なポイントを3つ押さえておきましょう。
プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄する手続き
相続放棄をすると、借金や保証人の立場といったマイナスの財産を引き継がなくて済む一方で、不動産や預貯金などのプラスの財産も一切相続できなくなります。「借金だけを放棄して、プラスの財産はもらう」ということはできません。特に注意すべきは、亡くなった方の預金を使って借金を返済したり、形見分け以外の目的で遺品を処分したりすると、相続を承認した(法定単純承認)と見なされ、相続放棄ができなくなる可能性がある点です。判断に迷う場合は、何かに手をつける前に必ず専門家にご相談ください。
家庭裁判所への申立てが必須
相続人同士で「私は相続を放棄します」と話し合ったり、念書を書いたりしただけでは、法的な効力はありません。必ず、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄の申述」という手続きを行う必要があります。
「3ヶ月以内」の期限がある
相続放棄の手続きには期限があります。原則として、**「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」**に家庭裁判所に申し立てる必要があります。この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、これを過ぎてしまうと原則として相続放棄はできなくなるため、注意が必要です。
【要チェック】未支給年金も相続放棄後に受け取れる
遺族年金とよく混同されるものに「未支給年金」があります。これも相続放棄をしても受け取ることが可能ですので、しっかり確認しておきましょう。
未支給年金とは?
未支給年金とは、「亡くなった方が受け取るはずだったが、亡くなったためにまだ支払われていない年金」のことです。
公的年金は、2ヶ月分がまとめて後払いで支給されます(例:2月分と3月分が4月に支給)。そのため、亡くなった月までの年金が、本人が亡くなった後で支払われることになります。この、本人が受け取れなかった分の年金が「未支給年金」です。
例えば、5月に亡くなった場合、本人が生きていれば4月分と5月分の年金が6月に支払われますが、本人は受け取れません。この4月・5月分の年金が未支給年金となります。
未支給年金も相続財産ではない
この未支給年金も、遺族年金と同様に法律(国民年金法第19条など)で受給権者が定められており、特定の遺族が自己の名で請求できる固有の権利とされています。そのため、相続財産には含まれず、相続放棄をしても受け取ることが可能です。
未支給年金を受け取れる人
未支給年金を受け取れるのは、「亡くなった方と生計を同じくしていた」遺族に限られ、以下の優先順位が定められています。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 上記以外の3親等以内の親族(甥、姪、おじ、おばなど)
ここでいう「生計を同じくしていた」とは、同居していた場合に加え、別居していても仕送りをしていた、または健康保険の扶養に入っていたなどの経済的な援助関係があった場合を指します。金銭だけでなく、食料品や衣類などを定期的に送っていた場合も含まれることがあります。
手続きをしないともらえない
非常に重要な点ですが、未支給年金は自動的に支払われるものではなく、請求手続きが必要です。手続きをしないと受け取れません。また、請求できる権利は5年で時効によって消滅してしまうため、忘れずに手続きを行いましょう。
相続放棄をしても受け取れるお金・財産一覧
遺族年金や未支給年金のほかにも、相続放棄をしても受け取れる可能性があるお金や財産があります。これらはいずれも「相続財産」とは見なされないためです。
- 生命保険金
受取人として指定された人の固有の財産とみなされるため。ただし、相続放棄をしても、税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になる場合がある点には注意が必要です。また、受取人が「被相続人(亡くなった方)」に指定されている場合は相続財産となります。 - 死亡退職金
会社の規程などで受取人が遺族と定められている場合、その遺族固有の財産とみなされるため。ただし、生命保険金と同様に、税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になる場合があります。 - 香典
葬儀の主宰者(喪主)への贈与とみなされ、葬儀費用などに充てられるものと考えられるため。 - お墓や仏壇などの祭祀財産
民法上、相続財産とは区別され、祭祀を主宰する人が承継するものと定められているため。 - 葬祭費・埋葬料
国民健康保険や健康保険組合などから、葬儀を行った人に対して支給されるもので、相続財産ではないため。
まとめ
今回は、相続放棄と遺族年金の関係について解説しました。最後に、記事全体の要点を3つのポイントにまとめます。
- 相続放棄をしても遺族年金は受け取れる 遺族年金は、亡くなった方の財産(相続財産)ではなく、法律に基づいて遺族に与えられる「受給者固有の権利」だからです。
- 未支給年金も受け取り可能 亡くなった方が受け取るはずだった未支給年金も、相続財産ではないため受け取れます。ただし、自動的には支払われないため、忘れずに請求手続きを行いましょう。
- 相続放棄は専門家への相談が安心 相続放棄には「3ヶ月以内」の期限があり、一度手続きをすると撤回はできません。特に、知らずに相続財産に手をつけてしまい放棄できなくなる(法定単純承認)といった取り返しのつかない事態を避けるためにも、借金の問題で相続放棄を検討している場合は、早めに弁護士や司法書士へ相談することをおすすめします。