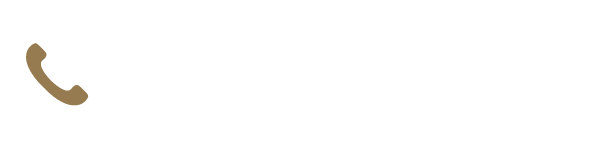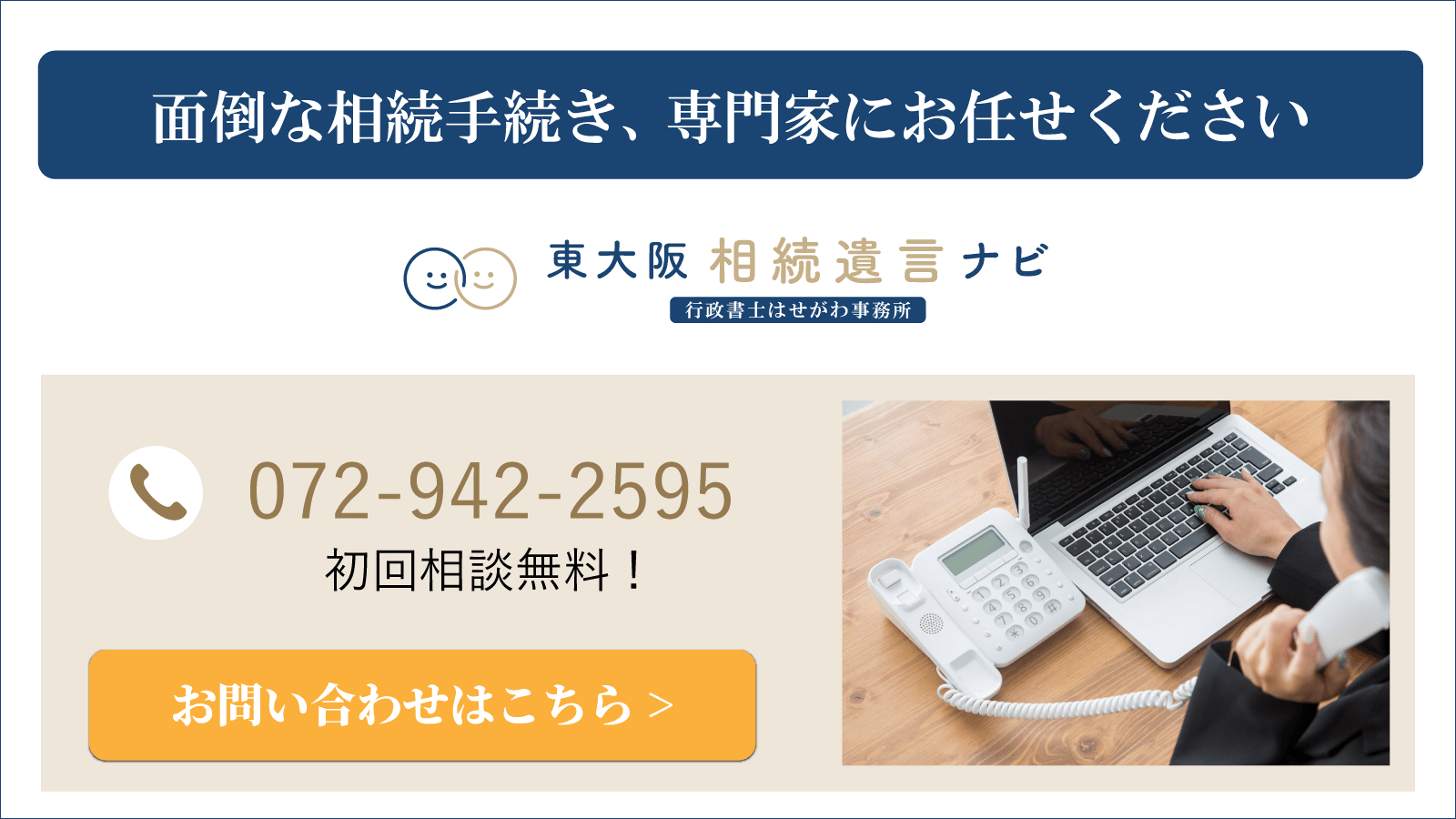初回相談無料!
相続人が一人の場合の手続きを解説!遺産分割協議は不要?注意点も紹介
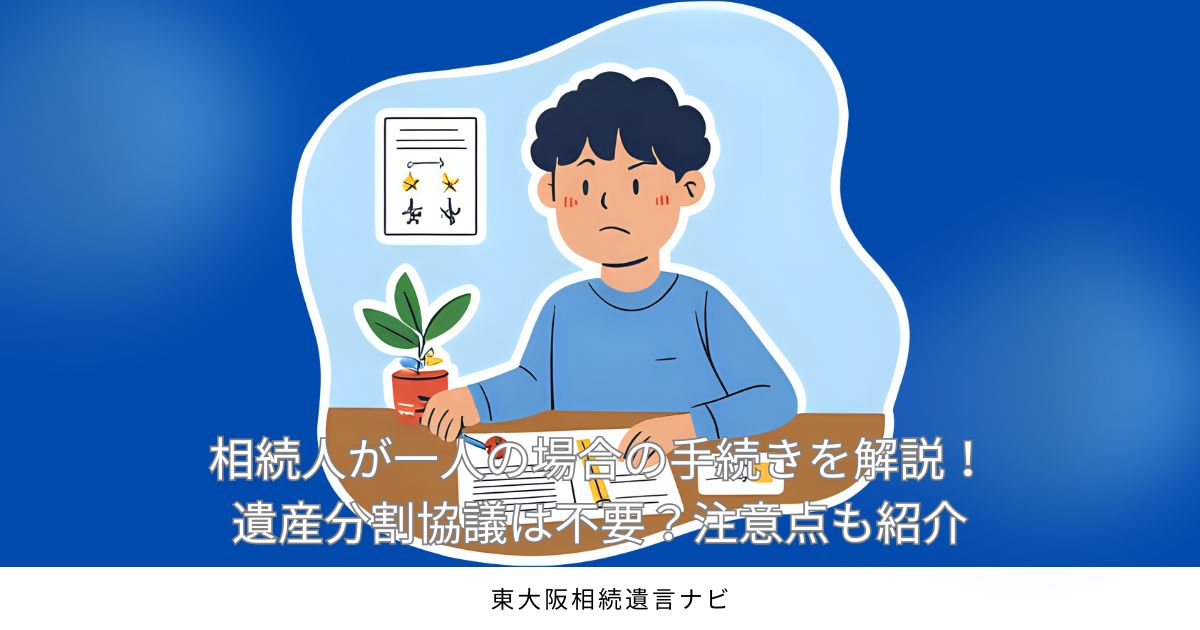
相続人がご自身一人だけの場合、兄弟姉妹など他の相続人との遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」が不要なため、「手続きが簡単そうだ」というイメージをお持ちの方も多いかもしれません。しかし、実際には相続人が一人だからこそ直面する特有の注意点や、たとえ一人であっても必ず踏まなければならない法的な手続きが存在します。
この記事では、相続手続きを専門とする司法書士の視点から、相続人が一人である場合の具体的な手続きの流れ、メリットとデメリット、そして特に知っておくべき重要な注意点を網羅的に解説します。
相続人が一人の場合のメリット・デメリット
相続人が一人の場合に考えられる利点と、注意すべき点を整理します。
メリット
遺産分割協議が不要で、相続トラブルのリスクが少ないこと
相続人が複数いる場合に最も発生しやすいのが、遺産の分け方をめぐる争いです。相続人が一人であれば、誰と財産を分けるか話し合う必要がないため、このような親族間のトラブルを根本的に避けることができます。
手続きに必要な書類が比較的少なく、手続きがスムーズに進むこと
相続手続きでは、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書など、多くの書類が必要になります。相続人が増えるほど、これらの書類を全員から集める手間と時間がかかりますが、一人の場合はご自身の書類を準備するだけで済むため、手続きの負担が軽減されます。
デメリット(注意点)
すべての相続手続きを一人で進めなければならないこと
戸籍の収集から財産調査、金融機関や法務局での名義変更まで、相続手続きは多岐にわたります。これらの煩雑な作業をすべて一人で行うのは、時間的にも精神的にも大きな負担になり得ます。ご自身での対応が難しい場合は、専門家への相談も選択肢となります。
被相続人のプラスの財産もマイナスの財産(借金など)もすべて引き継ぐこと
相続は、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金やローン、誰かの連帯保証人になっている地位といったマイナスの財産もすべて引き継ぐのが原則です。相続人が一人の場合、これらの負債をすべて一人で背負うリスクがあることを忘れてはなりません。
被相続人に配偶者が存命の場合、トラブルになる可能性があること
例えば、父が亡くなり相続人が母と一人っ子であるご自身の場合、法律上の相続人は二人になります。この1対1の状況では、財産の分け方を決める際に意見が対立すると、間を取り持つ兄弟姉妹がいないため、話し合いが膠着してしまうリスクがあります。一人っ子だからこそ、当事者同士で直接向き合う必要があり、関係性によっては大きな精神的負担となる可能性があります。
相続人が一人の場合でも必須!相続手続きの5つのステップ
相続人が一人であっても、以下の基本的な手続きは省略できません。順を追って確実に進めましょう。
ステップ1:相続人の調査・確定
「相続人は自分一人のはずだ」と思っていても、法的な手続きを進める上では、戸籍上で本当に相続人が一人であることを証明する必要があります。そのために、亡くなった方(被相続人)の「出生から死亡まで」の連続した戸籍謄本類をすべて取得します。これにより、ご自身が知らなかった前婚の子や、認知した子(婚外子)、養子などがいないかを確認し、法的な相続人を確定させます。これは、金融機関や法務局といった第三者が、他に相続人がいないことを公的に確認できなければ、故人の大切な財産を安心して引き渡すことができないためです。
ステップ2:遺言書の調査
次に、被相続人が遺言書を残していないかを確認します。遺言書には「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」などの種類があり、故人の自宅の金庫や引き出し、貸金庫などを探します。また、公正証書遺言であれば公証役場のデータベースで、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言であれば法務局で、その有無を調査できます。封印された遺言書を発見した場合は、勝手に開封せず、家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があります。
ステップ3:相続財産の調査
相続する財産を正確に把握するため、プラスの財産とマイナスの財産の両方を調査します。故人宛の郵便物や、信用情報機関への照会などが手がかりになります。
- プラスの財産: 預貯金、不動産、有価証券(株など)、自動車
- マイナスの財産: 借金、ローン、連帯保証人の地位
ステップ4:相続するか「相続放棄」するかを決定
財産調査の結果、明らかにプラスの財産よりも借金などのマイナスの財産が多い場合は、「相続放棄」という選択肢を検討します。相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになり、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継ぐ必要がなくなります。
ステップ5:預貯金や不動産等の名義変更
相続することを決めたら、各財産の名義をご自身のものに変更する手続きを行います。主な手続きは以下の通りです。
- 不動産: 法務局で相続登記(名義変更)を行います。
- 預貯金: 金融機関で口座の解約または名義変更の手続きをします。
- 有価証券: 証券会社で名義変更の手続きをします。
- 自動車: 運輸支局で名義変更の手続きをします。
【重要】遺産分割協議書は本当に不要?ケース別に解説
相続人が一人の場合、手続きの要となる「遺産分割協議書」の扱いはどうなるのでしょうか。原則と例外に分けて解説します。
原則として「遺産分割協議書」は不要
法的に相続人が一人しかいない場合、遺産を「分割」する相手が存在しないため、遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」そのものが発生しません。したがって、その話し合いの結果をまとめた「遺産分割協議書」も作成は不要です。相続人が一人になる具体的なケースには、以下のようなものがあります。
- もともと法定相続人が一人しかいない場合(例:両親が既に亡くなっており、子供が一人っ子)
- 自分以外の相続人全員が家庭裁判所で「相続放棄」をした場合
- 自分以外の相続人全員が「相続欠格」や「相続人廃除」により相続権を失った場合
例外的に「遺産分割協議書」が必要になるケース
一方で、法定相続人が複数いる状況で、話し合いの結果として「特定の相続人一人がすべての遺産を相続する」と決めた場合には、遺産分割協議書の作成が必要です。
例えば、相続人が子供二人で、話し合いの結果「長男がすべての財産を相続する」と合意した場合、その合意内容を証明するために遺産分割協議書を作成します。これは、次男が「すべての遺産を長男に渡すことに同意しました」という意思を公的に示すための重要な書類となり、金融機関や法務局での名義変更手続きに必須となります。
その他、一人っ子の相続で知っておくべき注意点
最後に、これまで解説した内容以外で、一人っ子の相続において特に注意しておきたい点を2つご紹介します。
遺言で全財産が第三者に遺贈されても「遺留分」がある
親が「全財産を長年お世話になった知人に遺贈する」といった内容の遺言書を残していたとしても、子供には法律で最低限保障された遺産の取り分である「遺留分」を請求する権利があります。この権利を行使して、遺産を受け取った相手に対して金銭の支払いを求めることを「遺留分侵害額請求」と呼びます。遺言の内容に納得がいかない場合は、この権利の行使を検討しましょう。
自分に相続人がいない場合のことも考えておく
相続した一人っ子の方が、ご自身に配偶者や子供がおらず、いわゆる「おひとりさま」の場合、将来ご自身が亡くなったときに、その財産を相続する人が誰もいないという状況が起こり得ます。実際、2020年のデータでは50歳時点での未婚割合が男性で約4人に1人、女性で約6人に1人となっており、これは決して他人事ではありません。特別な縁故者がいなければ、最終的に財産は国庫に帰属する(国のものになる)ことになります。親の相続を機に、ご自身の財産の将来について考え、遺言書の作成などを検討するのもよいでしょう。
まとめ
相続人が一人であっても、相続人の確定調査、財産調査、そして不動産や預貯金といった各種財産の名義変更手続きは必ず必要です。遺産分割協議がない分、トラブルは少ない傾向にありますが、手続きのすべてを一人で担う負担や、予期せぬ債務を引き継いでしまうリスクも存在します。
もし手続きの進め方に不安がある場合や、財産の状況が複雑でご自身での対応が難しいと感じた場合は、無理をせず、私たち行政書士を含めた相続の専門家へお気軽にご相談ください。