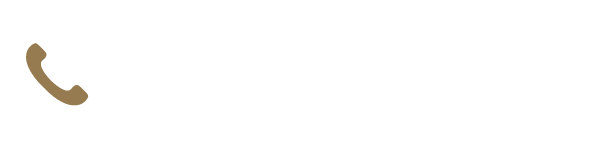ご依頼お待ちしております!!
遺言書があっても遺産分割協議は可能?条件と注意点を解説

「遺言書がある場合、必ずその内容どおりに遺産を分けなければならないのでしょうか?」これは、相続のご相談で非常によくいただく質問です。故人の最終的な意思を尊重するため、遺言書の内容が最優先されるのが法律上の大原則です。しかし、特定の条件下では、相続人全員の合意によって遺言書とは異なる内容で遺産を分ける「遺産分割協議」を行うことが認められています。
本記事では、相続を専門とする弁護士の立場から、遺言書と異なる遺産分割協議が可能になるための条件や、その際に必ず守るべき重要な注意点について、法的な根拠を交えながら分かりやすく解説します。
遺言書が最優先されるのが大原則
相続における最も基本的な原則は、亡くなった方(被相続人)が遺言書で示した最終的な意思を尊重することです。遺産は元々被相続人の財産ですから、その分け方について被相続人自身が残した意思を法律は最優先します。
したがって、法的に有効な遺言書が存在する場合、通常は相続人間での話し合い(遺産分割協議)は不要となり、遺言書に記載された内容に従って遺産が分割されることになります。
遺言書と異なる遺産分割協議が可能な理由
遺言書が最優先であるにもかかわらず、例外的に異なる内容の遺産分割協議が認められるのはなぜでしょうか。これには、法律上の根拠と実務上の必要性の両方があります。
まず、民法第907条1項では、共同相続人は、被相続人が遺言で分割を禁じた場合を除き、いつでも協議によって遺産の分割ができると定められています。この規定が、遺言書があっても遺産分割協議を行うことの法的根拠となります。
そもそも、被相続人が遺言書を作成する主な目的は「相続人間の争いを避けること」にあります。この点について、さいたま地方裁判所の判例(平成14年2月7日判決)でも、相続人全員が円満に合意した内容であれば、それは被相続人の意思に反するものではないと示されています。利害関係者全員が納得しているのであれば、あえて遺言書を強制し、その後に当事者間で財産を再分配させるような非効率な手続きを強いる必要はない、というのが司法の立場です。
さらに、実務上、遺言書の内容とは異なる遺産分割が望ましい具体的なケースも存在します。
- 遺言書に不備や曖昧な点がある場合 ご自身で作成された自筆証書遺言などでは、検認手続きは通過できても、内容が曖昧であったり、不動産や預貯金の名義変更手続きに使うには不備があったりする場合があります。このような場合に、改めて相続人全員で遺産分割協議を行う方が、手続きを円滑に進められます。
- 税制上の特例を活用したい場合 遺言書の内容によっては、「配偶者の税額の軽減」や「小規模宅地等の特例」といった、相続税を大幅に軽減できる特例が使えなくなってしまうことがあります。例えば、全ての財産を子に相続させると遺言した場合、配偶者がこれらの特例を使えません。節税の観点から、相続人全員で合意して、特例が使えるような遺産の分け方に変更することがあります。
遺言書と異なる遺産分割協議を行うための3つの必須条件
遺言書の内容とは異なる遺産分割協議を行うためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。一つでも欠けると、遺言書の内容が優先されます。
1. 相続人および受遺者全員の同意があること
これが最も重要かつ基本的な条件です。法律上の相続権を持つ「法定相続人」全員と、遺言によって財産を受け取ることになっていた「受遺者」全員が、遺言書の内容によらず遺産分割協議を行うことに同意しなければなりません。
たとえ一人でも「遺言書のとおりにすべきだ」と主張する人がいれば、遺産分割協議は成立せず、遺言書どおりに手続きを進めることになります。ここでいう「受遺者」には、相続人ではない友人や知人、お世話になった施設や慈善団体なども含まれます。これらの受遺者がいる場合は、その方が遺贈を放棄するか、遺産分割協議の内容に同意することが不可欠です。
2. 遺言書で遺産分割が禁止されていないこと
被相続人は、遺言によって遺産の分割を一定期間禁止する権利を持っています。民法第908条では、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができると規定されています。
もし遺言書にこのような分割禁止の条項がある場合、その期間中はたとえ全員が同意したとしても、遺産分割協議を行うことはできません。
3. 遺言執行者がいる場合は、その同意があること
遺言執行者とは、遺言の内容を確実に実現するために、遺言書で指定された人のことです。遺言執行者は、相続財産の管理やその他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利と義務を負っています(民法第1012条1項)。そのため、相続人は遺言執行者の職務を妨害する行為をすることはできません(民法第1013条)。
したがって、遺言執行者が指定されている場合には、その執行者の同意なくして遺言書と異なる内容の遺産分割協議を行うことはできません。もし同意なく進めた場合、その遺産分割は無効と判断される可能性があります。
では、相続人全員が合意しているのに、遺言執行者が反対することはあるのでしょうか。これは十分にあり得ます。遺言執行者の責務は、あくまで故人の意思を実現することです。もし遺言書が、専門家を交えて相続税対策や残された配偶者の生活設計などを熟慮して作成されたものであった場合、相続人たちの合意がその計画を根本から覆すものであれば、執行者は故人の意思を尊重し、同意を拒否することが正当な職務執行となるのです。
遺産分割協議を行う際の重要な注意点
全員の合意が得られ、遺言書と異なる遺産分割を行う場合でも、守らなければならない重要な注意点があります。これらを怠ると、罰則を受けたり、相続権を失ったりする可能性があります。
全員に遺言書の内容を正直に伝える
一部の相続人に遺言書の存在や内容を隠して遺産分割協議を進めることは絶対にあってはなりません。もし遺言書の存在を知らないまま不利な内容の分割協議に同意してしまった相続人がいれば、後から「錯誤」を理由に遺産分割協議の無効を主張される可能性があります。
さらに、意図的に遺言書を隠す行為(隠匿)は、相続人の資格を失う「相続欠格事由」に該当し、発覚した場合はすべての相続権を失うという厳しい結果につながります。
遺言書を破棄・偽造してはならない
遺言書の内容に従わないと決めた場合でも、その遺言書そのものを破棄したり、隠したり、改ざんしたりすることは決して許されません。これらの行為も「相続欠格事由」にあたり、相続権を失う原因となります。
必要な法的手続きを省略しない
遺言書と異なる合意をしたからといって、他の法的な手続きが免除されるわけではありません。
- 遺産分割協議書の作成
合意した内容は、必ず「遺産分割協議書」という正式な書面にまとめ、相続人・受遺者全員が署名し、実印を押印しましょう。これは後のトラブルを防ぎ、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きに不可欠です。 - 遺言書の検認
法務局の保管制度を利用していない「自筆証書遺言」が見つかった場合、その内容に従うか否かにかかわらず、家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける義務があります。検認は遺言書の形式や状態を確認する手続きであり、これを怠ると5万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。
全員の合意が得られない場合の対処法
相続人のうち一人でも合意が得られず、遺言書と異なる遺産分割協議ができない場合でも、遺言書の内容に納得がいかないときには、次のような法的な手段を検討することができます。
1. 遺言の無効を主張する(遺言無効確認訴訟)
遺言書そのものが法的に無効であると考えられる事情がある場合、裁判所にその無効を確認してもらう「遺言無効確認訴訟」を提起する方法があります。無効となる主な理由には、以下のようなケースが挙げられます。
- 遺言作成時に、作成者が認知症などで意思能力を欠いていた。
- 自筆証書遺言の日付や署名、押印がないなど、法律で定められた形式を満たしていない。
- 脅迫や詐欺によって無理やり書かされたものである。
2. 遺留分を請求する(遺留分侵害額請求)
「遺留分」とは、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者、子、親など)に法律上保障されている、最低限の遺産の取り分です。もし遺言書によって自分の遺留分が侵害されている場合、財産を多く受け取った他の相続人や受遺者に対し、侵害された分に相当する金銭の支払いを求める「遺産分割侵害額請求」を行うことができます。
まとめ
相続において遺言書は故人の最終意思として最優先されるのが大原則です。しかし、例外として、以下の3つの条件をすべて満たす場合に限り、遺言書とは異なる内容の遺産分割協議を行うことが可能です。
- 相続人および受遺者全員が同意し、
- 遺言書で遺産分割が禁止されておらず、
- 遺言執行者がいる場合はその同意も得られる
その際は、全員への情報開示を徹底し、遺言書を適切に扱い、必要な法的手続きを省略しないよう細心の注意が必要です。相続人間の関係が複雑であったり、手続きに不安があったりする場合は、ご自身の権利を正しく守るためにも、一度専門家に相談することをお勧めします。