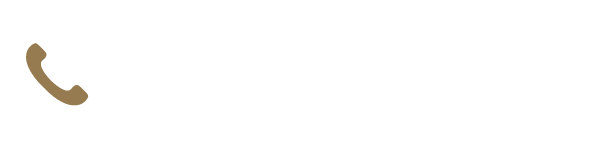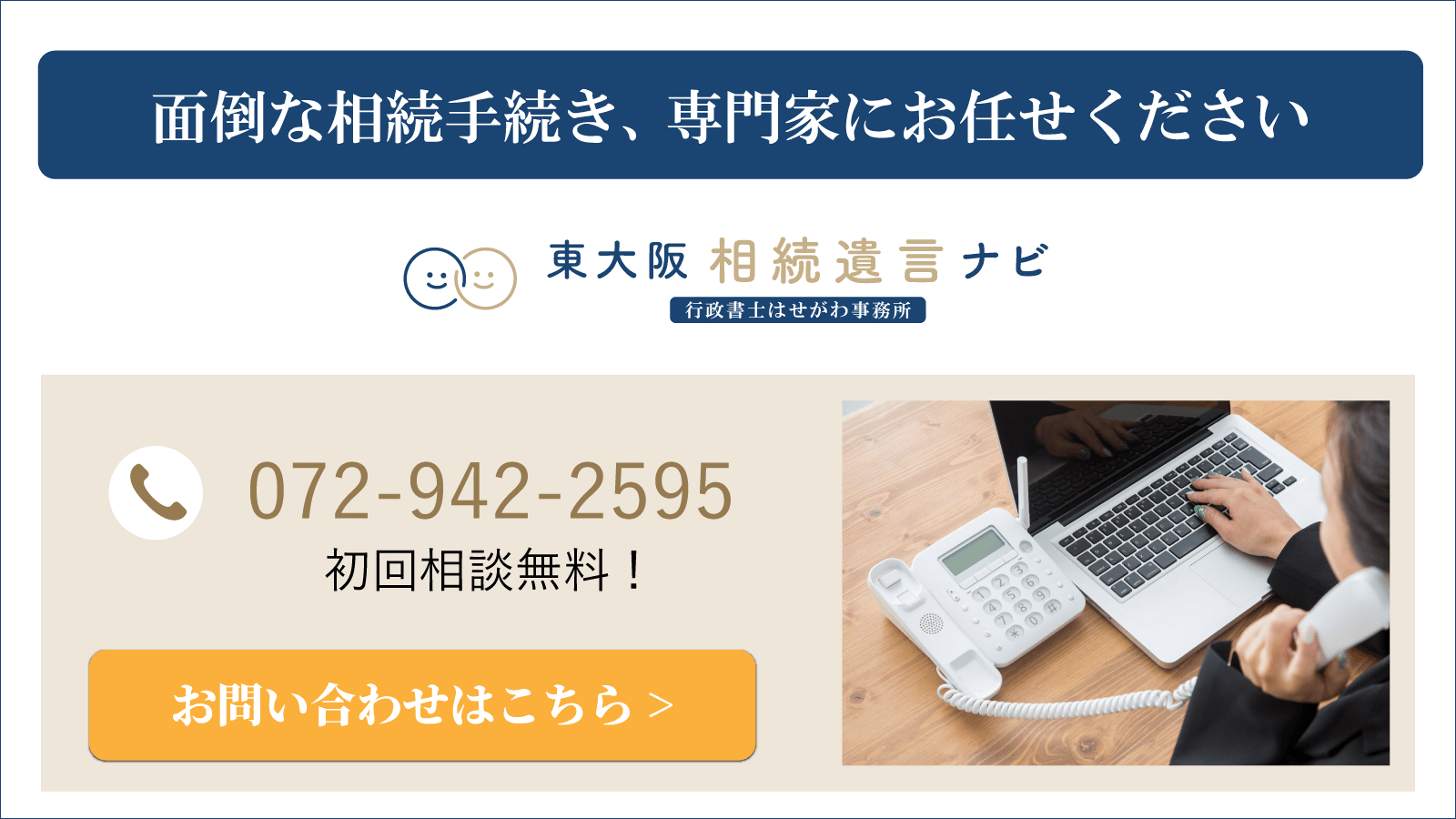初回相談無料!
相続人に認知症の方がいる場合、遺産相続はどう進める?手続き、問題点、生前対策を解説

はじめに:長寿社会で増える「相続人が認知症」という課題
長寿社会が進むにつれて、相続に関する新たな課題が浮上しています。典型的な例として、「父が亡くなり、相続人は母と子どもたちだが、その母が認知症を患っている」というケースです。このような状況では、遺産の分け方を決めるための「遺産分割協議」を進めることができず、手続きが完全に止まってしまいます。
この記事では、相続人に認知症の方がいる場合に相続手続きがなぜ停滞するのか、その具体的な問題点と法的な解決策を解説します。さらに、こうした事態を未然に防ぐための最も重要で効果的な生前対策についても詳しくご紹介します。
なぜ認知症の相続人がいると手続きが止まるのか?
相続手続きが停滞する背景には、法律上の2つの重要な原則があります。
全員の合意が必須の「遺産分割協議」
亡くなった方(被相続人)が遺言書を残していない場合、その財産を誰がどのように相続するかを決めるために、相続人全員で話し合いを行う必要があります。これを「遺産分割協議」と呼びます。
この協議は、相続人全員が参加し、全員がその内容に合意して初めて成立します。一人でも欠けたり、合意しなかったりすると、法的に有効な遺産分割は行えません。
「意思能力」がないと法律行為は無効になる
「意思能力」とは、自分が行う行為がどのような結果をもたらすかを正しく理解し、判断できる能力のことです。遺産分割協議は、財産の分け方を決める重要な「法律行為」にあたります。
ただし、ここで重要なのは、「認知症の診断=意思能力なし」と短絡的に判断すべきではないという点です。認知症は症状の進行度に幅があり、診断を受けたからといって、直ちにすべての法律行為ができなくなるわけではありません。遺産分割協議の時点で、その内容や結果を理解できるかどうかが個別に判断されます。
認知症などにより意思能力が不十分な方が参加して行われた遺産分割協議は、後から無効とされる可能性があります。また、手続きを急ぐあまり、他の相続人が本人の代わりに署名や押印をすることは、法的に無効であるだけでなく、「私文書偽造罪」という犯罪に問われるリスクがある極めて重大な違法行為です。絶対にやめましょう。
手続きを放置した場合に起こりうる問題点
遺産分割協議ができないまま放置すると、多くの深刻な問題が発生します。
預貯金口座の凍結
被相続人名義の銀行口座は凍結され、原則として預金の払い戻しができなくなります。これにより、葬儀費用や当面の生活費の支払いに困る可能性があります。(※ただし、「預貯金の仮払い制度」を利用すれば、各金融機関で上限額の範囲内であれば一部引き出しは可能です。)
不動産の塩漬け
不動産は相続人全員の共有状態となり、売却や賃貸、担保に入れて融資を受けるといった活用が一切できなくなります。管理の問題も生じ、固定資産税の負担だけが続くことになります。
相続税の申告期限
相続税の申告・納付は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。期限を過ぎると延滞税などのペナルティが課される可能性があります。また、遺産分割が確定していないと、「配偶者の税額の軽減」や「小規模宅地等の特例」といった大幅な節税特例を利用できなくなる恐れがあります。
相続放棄ができない
被相続人に借金などのマイナスの遺産があった場合でも、本人の意思で「相続放棄」をすることができません。その結果、本人が負債を背負うことになってしまいます。
法的な解決策「成年後見制度」とは?
相続手続きを法的に正しく進めるための正式な解決策が「成年後見制度」です。この制度は、認知症などで判断能力が不十分な方のために、家庭裁判所が代理人(成年後見人)を選任し、本人の財産管理や契約などを法的に支援・代行する仕組みです。
成年後見制度のメリット
成年後見制度を利用することで、停滞していた相続手続きを動かすことができます。
遺産分割協議への参加
成年後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加し、署名・押印することで、法的に有効な合意を形成できます。
相続放棄や各種手続き
後見人が本人を代理して、相続放棄の手続きや、相続税の申告、不動産の相続登記など、必要な各種手続きを行うことができます。
知っておくべき成年後見制度のデメリットと注意点
成年後見制度は有効な手段ですが、利用にあたっては慎重な検討が必要です。
時間と費用
家庭裁判所への申し立てから後見人が選任されるまでには数ヶ月かかります。また、弁護士や司法書士などの専門家が後見人に就任した場合、本人が亡くなるまで月々2万円〜6万円程度の報酬が発生し続けます。
親族が後見人になれない可能性
「子どもが親の後見人になる」と考える方が多いかもしれませんが、実際には難しいのが現状です。最高裁判所の統計(令和4年)によると、親族以外(弁護士・司法書士など)が後見人に選ばれる割合は80.9%にのぼります。なぜ親族が選ばれにくいのでしょうか。最大の理由は、相続において他の相続人との間に「利益相反」が生じるためです。子が親の後見人になると、遺産分割協議で自分の利益と親の利益が衝突するため、裁判所は中立な専門家を選ぶ傾向にあります。子が後見人になっても、結局遺産分割のためには別に「特別代理人」を選任する必要があり、裁判所から見れば「二度手間」になるのです。
柔軟な遺産分割は困難
成年後見人の最も重要な役割は「本人の財産を守る」ことです。そのため、遺産分割協議では本人の法定相続分を確保することを最優先します。「長男が家業を継ぐから多めに相続する」といった、他の相続人の希望に沿った柔軟な分割は認められにくくなります。
利益相反と特別代理人
後見人と本人の利益が対立する状況(利益相反)では、後見人は本人を代理できません。例えば、子が母の後見人である場合、父の相続において子と母は共に相続人です。この遺産分割協議では、子の取り分が増えれば母の取り分が減るため、利益相反の関係になります。この場合、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立て、その特別代理人が母を代理して協議に参加する必要があります。このように、特別代理人は他の相続人と利害関係のない中立な第三者が選任されることで、認知症であるご本人の権利が不当に侵害されるのを防ぐ重要な役割を果たします。
相続発生後にできる他の選択肢とその問題点
成年後見制度の利用を避けたい場合に検討される方法もありますが、それぞれに問題が伴います。
「法定相続分」で分ける場合
遺産分割協議を行わず、法律で定められた割合(法定相続分)で相続する方法です。例えば不動産を法定相続分で登記することは可能ですが、結局、その不動産は相続人全員の共有名義となります。将来の売却や活用には全員の同意が必要になるため、結局は認知症の方のために後見人を選任する必要が出てきます。つまり、問題の本質的な解決にはならず、単なる先送りにしかなりません。また、預貯金の払い戻しについても、結局は金融機関から相続人全員の同意を求められるため、手続きを進めることは困難です。
認知症の症状が軽度な場合
認知症と診断されていても、症状が軽度で、医師から「遺産分割協議に必要な判断能力がある」という診断書を得られる場合は、本人が協議に参加できる可能性があります。ただし、この判断能力の有無は後から親族間でトラブルの原因になりやすいため、安易に判断せず、必ず専門家に相談することをお勧めします。
最も有効な対策は「生前の準備」
ここまで見てきたように、相続が発生してからでは手続きが複雑化し、多くの困難が伴います。家族に負担をかけず、円満な相続を実現するための最も確実な方法は、判断能力がしっかりしているうちに「生前の対策」を講じておくことです。
遺言書の作成
最も有効かつシンプルな対策は「遺言書の作成」です。遺言書で財産の分け方を具体的に指定しておけば、そもそも遺産分割協議が不要になります。そのため、相続人の一人が認知症であっても、遺言書の内容に従ってスムーズに手続きを進めることができます。
特に、公証人が作成に関与する「公正証書遺言」は、法的な不備で無効になるリスクが極めて低く、証明力も高いため、最も確実な方法として推奨されます。
その他の生前対策
遺言書以外にも有効な対策があります。その一つが「家族信託」です。これは、元気なうちに信頼できる家族(例えば子)に財産の管理や処分を託す契約です。家族信託契約を結んでおけば、本人の判断能力が低下した後でも、受託者である子が契約内容に従って不動産の売却や預金の管理を行えるため、成年後見制度を利用する必要がなくなります。遺言書は本人の死後に初めて効力を生じますが、家族信託は本人の判断能力が低下した後、つまり生前から機能する点が大きな違いです。
また、「生前贈与」によって事前に財産を移転しておくことも、将来の相続に備える選択肢となり得ます。
まとめ
相続人に認知症の方がいる場合、遺産分割協議ができなくなり、預貯金の凍結や不動産の塩漬けといった問題が生じます。法的な解決策である「成年後見制度」は有効ですが、費用や時間の負担、希望通りの遺産分割が難しいといったデメリットも存在します。
結論として、将来のもしもに備え、家族の負担を減らすための最善策は、元気なうちに「遺言書」を作成しておくことです。また、状況に応じて家族信託などの対策も非常に有効です。相続に関する問題は、早期の対策が鍵となります。ご自身の状況に不安を感じたら、できるだけ早く司法書士や弁護士などの専門家にご相談ください。