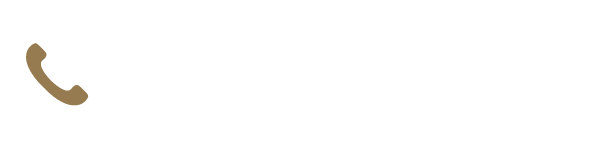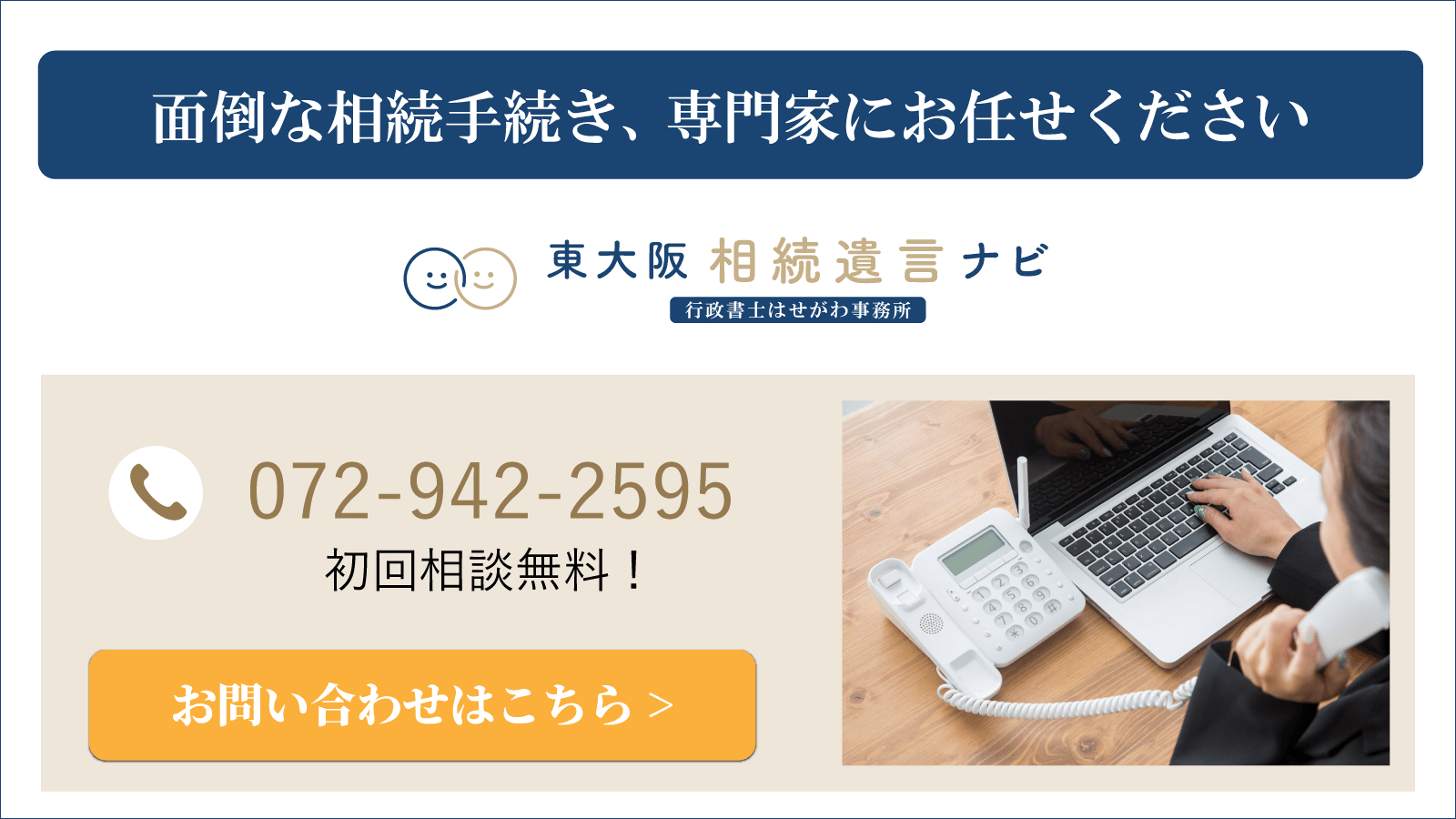初回相談無料!
不動産相続で共有名義は要注意!知っておくべきデメリットと具体的な解消法

「相続した実家は、誰も住まないけれど思い出がある。売るのも忍びないし、とりあえず公平に兄弟3人の共有名義にしておこう。」
相続が発生した際、このような安易な判断をしてしまうケースは少なくありません。一見、公平でトラブルのない選択に見えますが、この「とりあえず共有名義」が、将来的に「売りたいのに売れない」「活用したいのにできない」といった深刻なトラブルの火種になることをご存知でしょうか。
行政書士・宅建士として日々相続不動産に携わる中で、私はこの共有不動産案件でのトラブルを目の当たりにしていました。
この記事では、相続不動産の専門家として、共有名義がなぜ要注意なのか、その具体的なデメリットと、すでに共有名義になってしまった場合の解消法まで、分かりやすく解説します。
相続における不動産の「共有名義」とは?
まず、「共有名義」の基本的な概念を整理しましょう。
共有名義とは、1つの不動産を複数人で所有している状態のことです。各所有者が持つ権利の割合は「共有持分」と呼ばれます。
相続で不動産が共有名義になる代表的なケースは、以下の2パターンです。
- 遺産分割協議で合意した場合
相続人同士の話し合い(遺産分割協議)の結果、「兄弟で平等に所有しよう」と合意して共有名義で登記するケース。 - 協議がまとまらない場合
遺産分割協議がまとまらなかったり、協議自体を行わなかったりして、法律で定められた相続割合(法定相続分)のまま登記するケース。
具体例を挙げると、父親が亡くなり、兄弟3人(兄、弟、妹)が実家を相続した場合、それぞれが「3分の1」ずつの共有持分を持つことになります。これが不動産の共有状態です。
なぜ共有名義が選ばれるのか?考えられるメリット
デメリットが多い共有名義ですが、なぜ選ばれてしまうのでしょうか。考えられるメリットを以下にまとめます。ただし、これらのメリットは一時的なもので、将来発生しうるデメリットを上回ることは少ない点に注意が必要です。
- 公平な遺産分割
各相続人が法定相続分に応じた持分を得るため、不公平感が出にくく、相続人間のトラブルを一時的に避けられます。「とりあえず」の解決策として選ばれがちです。 - 税制上の優遇
共有名義の自宅を売却する際、一定の要件を満たせば、共有者それぞれが「居住用財産の3,000万円特別控除」を利用できる可能性があります。しかし、この税制優遇には大きな矛盾が潜んでいます。控除を受けるためには不動産を「売却」する必要がありますが、共有名義の最大の問題点である「全員の同意」がなければ売却自体ができないのです。結果として、この税制上のメリットは「絵に描いた餅」になる可能性があります。 - 費用の分担
固定資産税や修繕費といった不動産の維持管理費用を、持分割合に応じて分担できます。一人にかかる経済的負担を軽減できるという側面があります。
不動産を共有名義で相続する5つの深刻なデメリット
不動産を共有名義で相続することが、なぜ危険なのか。具体的な5つのデメリットを、事例を交えながら詳しく解説します。
売却や活用には「全員の同意」が必要で、身動きが取れなくなる
共有名義の不動産で最も大きな問題は、意思決定の難しさです。法律上、不動産に関する行為は内容によって必要な同意の数が異なります。
- 変更・処分行為(例:不動産全体の売却、建て替え、大規模修繕)
共有者全員の同意が必要です。これは民法第251条に定められた厳格な法的要件です。たとえ9割の持分を持つ人が売却したくても、残りの1割を持つ人が一人でも反対すれば、売却はできません。結果として、誰も活用できない「塩漬け」不動産になってしまうリスクがあります。 - 管理行為(例:賃貸に出す)
持分割合の過半数の同意が必要です。これも民法第252条で定められています。兄弟3人(持分3分の1ずつ)の場合、2人の同意が必要となり、ここでも意見が割れると活用が進みません。
世代交代で相続が重なると、権利関係がネズミ算式に複雑化する
共有名義の問題は、自分たちの代で終わりません。共有者の一人が亡くなると、その人の持分は、さらにその配偶者や子へと相続されます。世代を重ねるごとに、相続は繰り返され、共有者の数はネズミ算式に増えていきます。
(例)
1. 初代: 兄と弟の2人で実家を共有。
2. 兄が死亡: 兄の持分を、兄の妻と子2人が相続。共有者は「弟、義姉、甥、姪」の4人に増えます。
3. 次に弟が死亡: 弟の持分を、弟の子が相続。共有者は「いとこ同士」や「叔父と甥」といった関係になります。
このように、関係性は「兄弟」から「叔父と甥」、そして「いとこ同士」へと世代を重ねるごとに希薄になり、コミュニケーションは各段階でより困難になっていきます。面識すらない親戚同士での合意形成は、ほぼ不可能と言えるでしょう。
固定資産税や維持費の負担をめぐり、金銭トラブルに発展しやすい
不動産を所有している限り、固定資産税や修繕費は必ず発生します。これもトラブルの火種です。
- 固定資産税の支払い
納税通知書は、共有者の代表者1人にしか送付されません。代表者が一旦全額を立て替え、他の共有者から持分に応じた金額を徴収する必要がありますが、支払いに応じない人が出てくるとトラブルになります。 - 連帯納税義務
共有者全員に「連帯納税義務」があります。これは、万が一納税が滞った場合、役所は持分割合に関係なく、共有者のうち誰か一人に対して税金の全額を請求できるという意味です。たとえ自分の持分が10分の1でも、他の共有者が支払わなければ、全額の納税義務を負うリスクがあるのです。これは共有者にとって非常に厳しい義務です。 - 維持費の負担
「誰がいくら負担するのか」「そもそも修繕は必要なのか」といった点で意見が対立しやすく、人間関係に亀裂が入る原因となります。
共有者の一人が認知症になると、不動産が凍結されるリスクがある
高齢化社会において、これは非常に現実的なリスクです。共有者の一人が認知症などによって意思能力(判断能力)を失った場合、その人は売買契約などの法律行為ができなくなります。
この状態で不動産を売却するには、家庭裁判所に申し立てて「成年後見人」を選任してもらう必要があります。しかし、この手続きには数ヶ月の時間と費用がかかる上、成年後見人は本人の財産を守ることが最優先の役割であるため、必ずしも不動産の売却が認められるとは限りません。結果として、不動産が完全に「凍結」されてしまう恐れがあります。
自分の持分だけでも売却できるが、大きな不利益につながる
法律上、各共有者は自分の持分だけなら、他の共有者の同意なしに売却できます。しかし、これは現実的な解決策とは言えません。
不動産の一部の権利だけを買いたいという一般の買い手は、まず現れません。そのため、買い手は共有持分を専門に扱う買取業者に限られ、市場価格より大幅に安い価格で買い叩かれてしまうのが実情です。
さらに、彼らは一般的な購入者ではなく、共有持分をビジネスとして買い取る専門の不動産投資家です。その目的は、残りの共有者に対して、より高い価格での持分の買い取りを迫ったり、不動産全体の売却に同意させたりすることにある場合が多く、家族間の力関係に、金銭的な動機を持つ攻撃的な第三者が介入してくることになるのです。
トラブルを未然に防ぐ!共有名義にしないための相続方法
相続が発生した後、これから遺産分割協議を行うのであれば、共有名義を避ける方法があります。代表的な3つの方法をご紹介します。
換価分割(かんかぶんかつ)
- 内容: 不動産を売却して現金化し、その現金を相続人間で分ける方法です。
- メリット: 1円単位で公平に分けられるため、最も分かりやすくトラブルになりにくい方法です。この方法は、誰が不動産を取得するかで揉めることなく、公平な分割を実現できるため、相続人間の争いを根本的に解決します。
- 注意点: 思い出のある家を手放す必要があります。また、売却には仲介手数料などの諸経費や税金がかかります。
代償分割(だいしょうぶんかつ)
- 内容: 相続人の一人が不動産を単独で相続する代わりに、他の相続人に対して現預金(代償金)を支払う方法です。
- メリット: この方法は、特定の相続人が家を守りたい一方で他の相続人は現金化したい、という共有名義で起こりがちな意見対立を直接的に解決できます。
- 注意点: 不動産を相続する人に、代償金を支払えるだけの十分な資力が必要です。また、不動産の評価額そのものを巡る対立も起こりがちです。不動産を相続する側は代償金を抑えるために低い評価額を主張し、代償金を受け取る側は高い評価額を主張するため、ここが新たな争点になることがあります。
分筆(ぶんぴつ)
- 内容: 土地を物理的に複数に分割し、それぞれを各相続人が単独で所有する方法です。
- メリット: 各相続人が独立した所有者となるため、「全員の同意」という共有名義の最大の足かせから解放され、各自が自分の土地を自由に売却・活用できるようになります。
- 注意点: 建物には適用できず、土地のみが対象です。分割によって土地が狭くなり、かえって価値が下がってしまう可能性があるため、かなり広い土地でないと現実的ではありません。
すでに共有名義の場合の解決策は?共有状態を解消する4つの方法
すでに共有名義の不動産をお持ちの場合、迅速な行動が不可欠です。解決策はいくつか存在しますが、その有効性は一様ではありません。ここでは、最も現実的で推奨される解決策から順に解説します。
共有者全員で不動産全体を売却する
最も現実的で推奨される解決策です。共有者全員で協力して不動産全体を売却し、その代金を持分割合に応じて分配します。金銭で公平に分配できるため、根本的な問題解決につながります。
共有者の一人が他の共有者の持分を買い取る
共有者間で話し合いがまとまり、買い取る側に資金力があれば有効な方法です。特定の誰かがその不動産を取得したいという希望がある場合に検討されます。
遺言書を作成する
これは将来の相続に備えるための対策です。例えば、兄と弟で共有している場合、兄が遺言書で「自分の持分は、共有者である弟に遺贈する」と指定しておくことで、遺言者の持分は通常の相続プロセスを回避します。配偶者や子といった自身の相続人に分割される代わりに、持分は直接他の共有者へ移転され、所有権が集約されます。これにより、共有者の増加を防ぐことができるのです。
共有物分割請求訴訟
話し合いによる解決がどうしても不可能な場合の最終手段です。裁判所に申し立て、共有物の分割方法を決定してもらいます。ただし、訴訟には多くの時間と費用がかかり、裁判所が下す判断(例えば競売)が、必ずしも自分の望む結果になるとは限りません。
まとめ
これまで見てきたように、不動産を安易に共有名義で相続することは、多くのリスクをはらんでいます。
- 共有名義は、売却や活用に全員の同意が必要で身動きが取れなくなる。
- 世代交代で権利関係が複雑化し、解決が困難になる。
- 税金や維持費を巡る金銭トラブルが発生しやすい。
問題が複雑化し、関係者が増えて手遅れになる前に、できるだけ早く対策を講じることが重要です。もし少しでも不安を感じたら、まずは相続に詳しい司法書士や不動産会社などの専門家に相談することをお勧めします。
「自分たちの代は仲が良いから大丈夫」と問題を先送りにするのではなく、「子や孫の世代に負の遺産を残さない」という視点を持つことが、円満な相続の鍵となります。