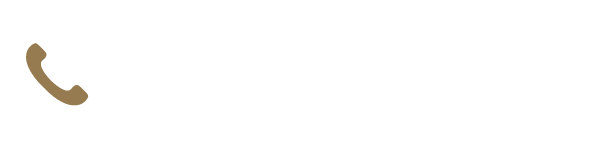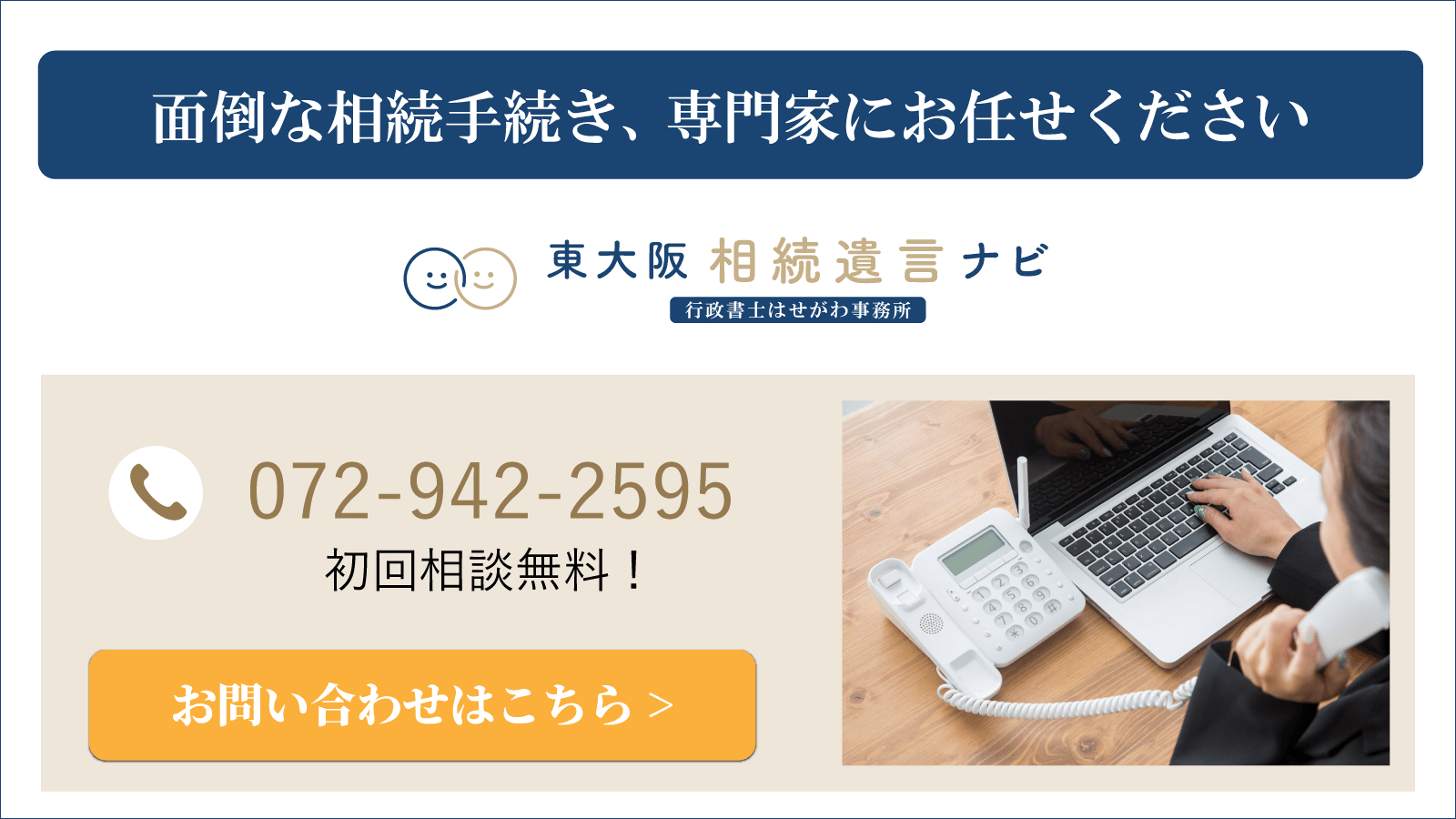初回相談無料!
相続した不動産の家賃収入は誰のもの? 時系列で見る権利の帰属と税務申告

「亡くなった父が所有していた賃貸マンションの家賃収入は、遺産分割協議が終わるまで誰のものになるのでしょうか?」このようなご相談は、相続手続きにおいて非常に多く寄せられます。賃貸不動産から生じる収益の帰属は、相続人間でのトラブルの火種になりやすい問題の一つです。
この記事では、相続の家賃収入の取り扱いについて、法的判例と明確な時系列に基づき、誰が家賃収入を受け取る権利を持つのか、そしてどのような税務手続きが必要になるのかを分かりやすく解説します。
家賃収入の帰属は3つの期間で考える
相続した不動産の家賃収入が誰のものになるかという問題は、被相続人(亡くなった方)の死亡時を基準に、以下の3つの期間に分けて考える必要があります。
- 相続開始「前」に発生した家賃収入
- 相続開始後から遺産分割完了「まで」に発生した家賃収入
- 遺産分割完了「後」に発生した家賃収入
それぞれの期間で権利の帰属と手続きが異なるため、順を追って見ていきましょう。
【時系列①】相続開始「前」の家賃収入
権利の帰属
相続開始(被相続人の死亡)より前に発生した家賃収入は、被相続人自身の財産です。
ここで重要なのは、家賃を受け取る権利がいつ確定したか、つまり「支払期日」が被相続人の死亡日より前に到来していたかどうかです。
支払期日が死亡日より前に到来している家賃は、被相続人の財産となります。すでに受け取られ、被相続人名義の預金口座に入金されている場合は、その預金が「相続財産」として遺産分割の対象となります。支払期日は到来しているものの、入居者の滞納などによりまだ支払われていない家賃(未収家賃)がある場合、その「未収家賃を受け取る権利(賃料債権)」も同様に相続財産として扱われます。
一方で、たとえ生前に受け取っていても、支払期日が死亡日より後に到来する家賃(例えば、1月末に2月分の家賃を受け取った後に1月中に亡くなった場合の2月分家賃)は、被相続人の財産とはならず、相続財産には含まれません。
税務上の手続き
相続人は、被相続人の所得について「準確定申告」を行う義務があります。これは、その年の1月1日から亡くなった日までの所得を計算し、税務署に申告・納税する手続きです。
この申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、原則として相続人全員が連名で行わなければなりません。準確定申告によって所得税の還付金が発生した場合、その還付金も相続財産に含まれます。
【時系列②】相続開始後から遺産分割完了「まで」の家賃収入
この期間の家賃収入の取り扱いは、最も誤解が多く、トラブルになりやすいポイントです。
結論:遺産ではなく、各相続人が法定相続分に応じて取得する
相続が開始してから遺産分割協議が完了するまでの間に発生した家賃収入は、遺産(相続財産)には含まれません。最高裁判所の判例(最高裁平成17年9月8日判決)により、この期間の家賃収入は「遺産とは別個の財産」であると明確に判断されています。この判例は、遺産分割協議が長引いて進まない状況でも、各相続人が自身の権利として家賃収入の分配を法的に請求できるという強力な根拠となります。
したがって、各共同相続人は、その不動産から生じる家賃収入を、自身の法定相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得します。(つまり、遺産分割協議を待たずに、それぞれの相続人が自分の取り分として法的に確定した権利を持つということです。)
遺産分割の遡及効は影響しない
民法では、遺産分割の効果は相続開始時にさかのぼる(遡及効)と定められています。これにより、「最終的に長男が不動産を相続したのだから、相続開始後からの家賃もすべて長男のものになるのでは?」と考える方がいますが、これは間違いです。
最高裁は、遺産分割の遡及効は、この期間中の家賃収入の帰属には影響しないと判断しています。つまり、遺産分割協議で特定の誰かが不動産を相続することになったとしても、それまでに他の相続人が法定相続分に応じて受け取った家賃を返す必要はありません。
税務上の手続き
この期間の家賃収入は各相続人の固有の財産となるため、収入を得た各相続人は、自身の所得として「不動産所得」の確定申告を翌年に行う必要があります。
【時系列③】遺産分割完了「後」の家賃収入
権利の帰属
遺産分割協議が成立し、不動産の所有者が確定した後は、話は単純明快です。遺産分割完了後に発生するすべての家賃収入は、その不動産を相続した個人のものとなります。
税務上の手続き
不動産を相続した新たな所有者は、その後のすべての家賃収入について、自身の所得として毎年の確定申告を行う責任を負います。
家賃収入をめぐるトラブルと対策
ここまでの法的ルールを踏まえ、よくあるトラブルとその対策を解説します。
一人の相続人が家賃を独占している場合は?
遺産分割協議が完了するまでの間、特定の相続人(例えば長男)が家賃をすべて管理し、他の相続人に分配しないケースがあります。この場合、他の相続人は自身の法定相続分に相当する金銭の支払いを法的に請求する権利があります。この請求を「不当利得返還請求」と呼びます。
トラブルを避けるための実務対応
紛争を未然に防ぐためには、以下の対応が有効です。
- 相続人全員の合意で分配方法を決める
最高裁判例では法定相続分に応じるとされていますが、相続人全員が合意すれば、これと異なる取り決めをすることも可能です。例えば、遺産分割協議書に次のような一文を加えることで、不動産を取得する人が相続開始時点からの収益もすべて取得すると定めることができます。 「相続開始後に各遺産について発生した収益及び費用は、各遺産の相続人が相続及び承継するものとする。」 - 管理用の専用口座を作る
遺産分割協議が長引く場合は、相続人の代表者名義で家賃管理用の専用口座を開設することをお勧めします。家賃の入金だけでなく、固定資産税、管理費、修繕費といった関連する支出もその口座で一元管理することで、金銭の流れが透明化され、後の分配もスムーズに行えます。
相続で必要な税務申告手続きのまとめ
この記事で解説した税務手続きを一覧表にまとめました。
| 手続きの種類 | 対象となる所得 | 申告者と期限 |
|---|---|---|
| 準確定申告 | 故人が亡くなる日までに得た所得 | 相続人全員が、相続開始を知った日から4ヶ月以内 |
| 確定申告 | 相続開始後に各相続人が得た所得 | 所得を得た各相続人が、翌年2月16日~3月15日 |
| 青色申告承認申請 | 不動産を相続した相続人の事業所得 | 被相続人の承認は引き継がれないため、新たに申請が必要。死亡日が1月1日~8月31日の場合は死亡日から4ヶ月以内、9月1日~10月31日の場合は12月31日まで、11月1日~12月31日の場合は翌年2月15日までと、被相続人の死亡時期により期限が異なるため要注意。 |
まとめ
相続不動産から生じる家賃収入の帰属は、「相続開始前」「遺産分割完了まで」「遺産分割完了後」という3つの期間で明確に区別されます。特に、遺産分割が完了するまでの期間の家賃は、遺産とはならず、各相続人が法定相続分に応じて取得するという最高裁のルールは重要なポイントです。
法的なルールは明確ですが、相続人間の無用な争いを避けるためには、これらの知識を前提として相続人全員が適切にコミュニケーションをとることが不可欠です。もし状況が複雑であったり、相続人間での話し合いが難航したりする場合には、早期に弁護士や税理士などの専門家へ相談することをお勧めします。