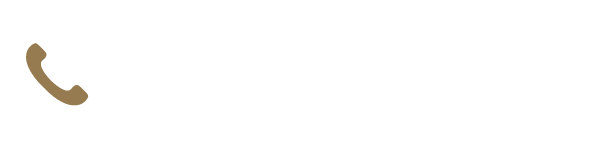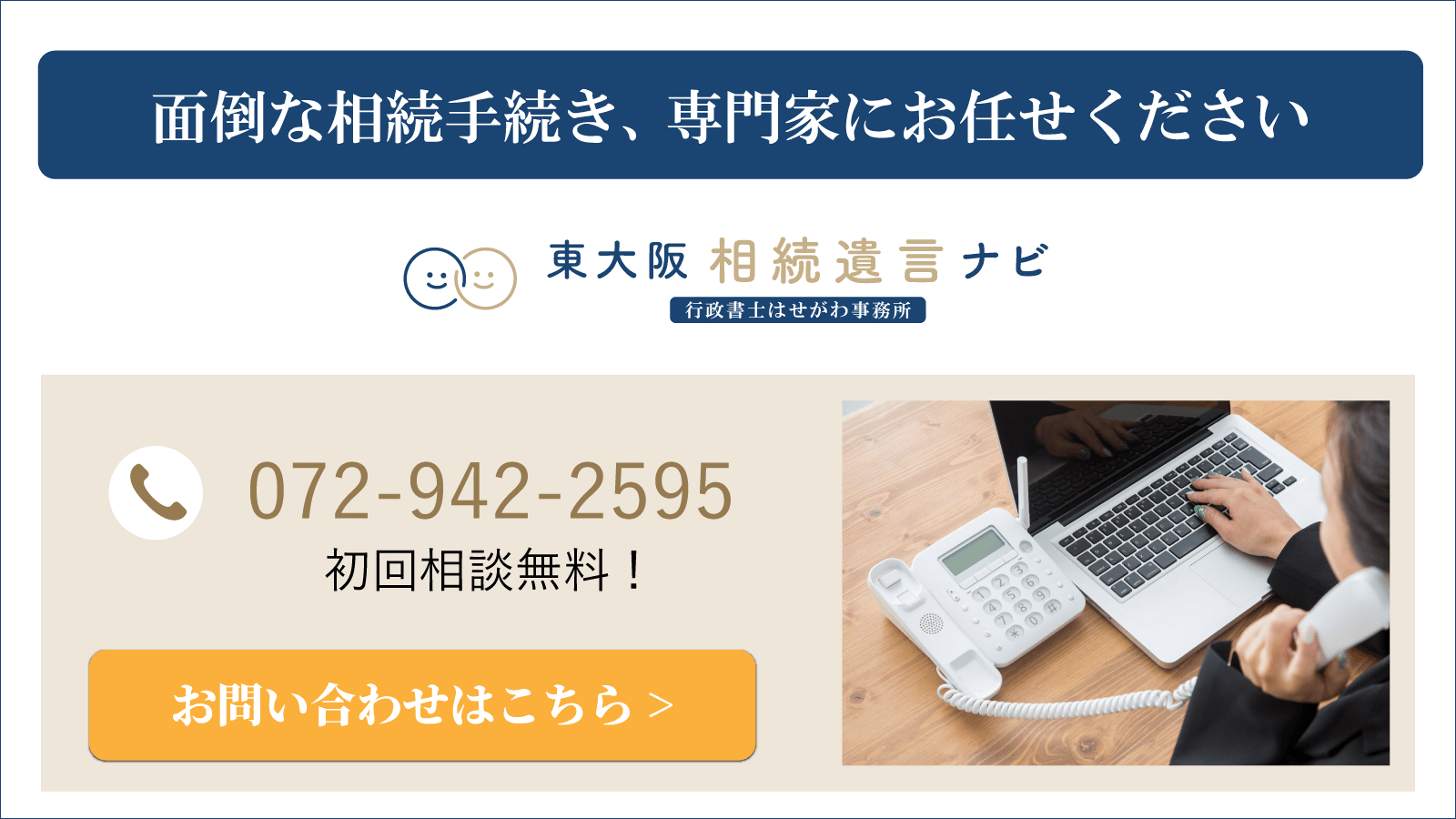初回相談無料!
遺言書に財産目録は無しでも有効?相続トラブルを招くリスクと作成のすすめ
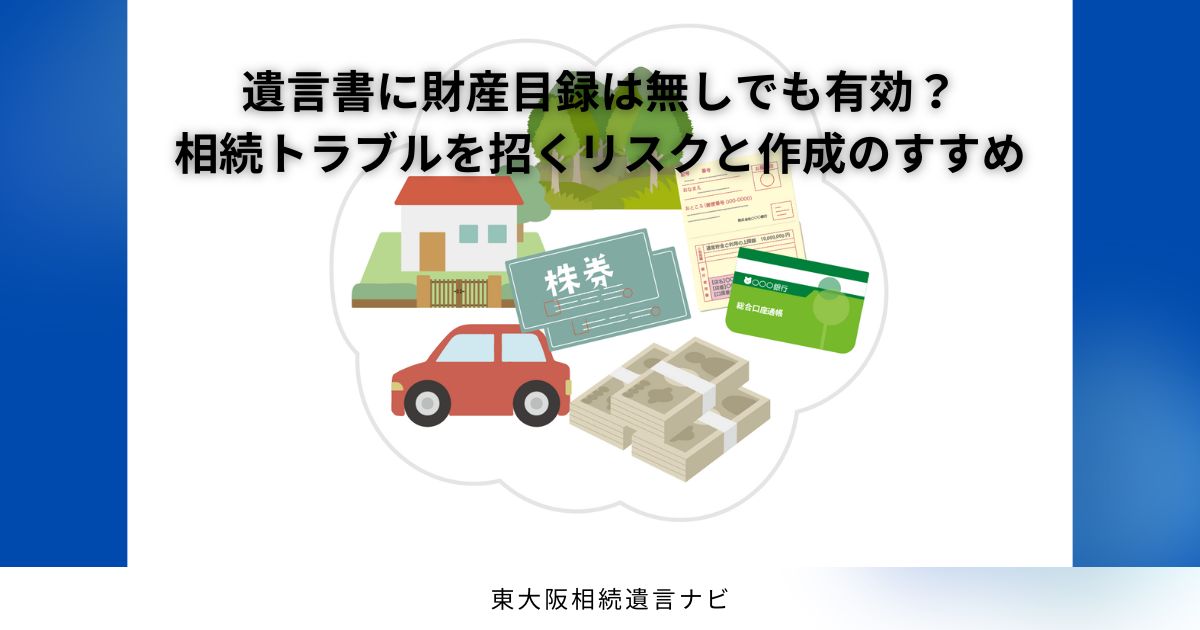
「財産目録がない遺言書は有効なのだろうか?」とお悩みの方もいらっしゃるかもしれません。結論から申し上げますと、財産目録がなくても遺言書自体は法的に有効です。
しかし、財産目録がないことで、残されたご家族が財産調査に大きな手間を強いられたり、相続人同士の「隠し財産」への疑念から相続トラブルに発展したりする重大なリスクがあります。
この記事では、相続問題を専門とする弁護士の実務的な視点から、財産目録がないことのリスク、作成するメリット、そして具体的な作成方法と注意点について、分かりやすく解説します。
結論:財産目録がなくても遺言書は法的に「有効」
まず、遺言書における財産目録の位置づけを正確に理解しましょう。
財産目録とは、遺言者が所有する預貯金や不動産といったプラスの財産から、借金などのマイナスの財産までを一覧にしたリストのことです。
法律上、遺言書に財産目録を添付することは必須要件ではありません。したがって、財産目録が添付されていない遺言書も無効にはならず、法的には有効なものとして扱われます。
しかし、法的に有効であることと、相続が円満に進むことは全く別の問題です。むしろ、財産目録がないことで、遺言書に記載されていない財産の存在が、かえってトラブルの火種となり得るのです。
財産目録がない場合に起こりうる4つの深刻なリスク
多くの相続トラブルは、この財産目録がなかったことに起因しています。具体的には、以下のような深刻な事態を招きかねません。
相続人が財産を把握できず、調査に膨大な手間がかかる
ご自身が所有する財産をすべて把握していても、それを相続人であるご家族が同じように把握しているケースは稀です。財産目録がない場合、相続人はゼロから財産調査を始めなければなりません。心当たりのある金融機関に一つひとつ照会をかけるなど、大変な手間と時間がかかってしまいます。
「隠し財産」への疑念が生まれ、相続トラブルの火種になる
財産の一覧がなければ、相続人の間で「他にも財産があるのではないか」「誰かが隠しているのではないか」といった疑心暗鬼が生じ、深刻なトラブルに発展する可能性があります。また、一度遺産分割協議が成立した後に新たな財産が見つかった場合、再度協議が必要になるだけでなく、相続税の修正申告も発生するなど、手続きが非常に煩雑になります。
借金に気づかず、相続放棄の機会を失う
財産目録はプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も記載することが重要です。特に、財産内容を特定せずに「全財産の〇割を遺贈する」といった包括遺贈の場合や、相続人が借金の存在を知らないまま相続手続きを進めてしまうと、本来であれば相続放棄(相続開始を知った時から原則3ヶ月以内)できたはずの機会を失い、予期せぬ借金を背負ってしまうリスクがあります。
遺言執行者の業務負担が増え、手続きが遅延する
遺言の内容を実現する「遺言執行者」は、その任務として遺産目録を作成する義務を負っています。遺言者自身が目録を用意していない場合、遺言執行者が財産調査から始めなければならず、その分業務負担が増大します。結果として、相続人への遺産の引き渡しが遅れる原因にもなります。
トラブル防止!遺言書に財産目録を添付すべき4つの理由
前述のリスクを回避し、円満な相続を実現するために、財産目録の作成を強く推奨します。目録を添付することには、主に4つのメリットがあります。
相続手続きが迅速かつスムーズに進む
財産目録があれば、相続人は遺産の全体像をすぐに把握できます。これにより、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しといった相続手続きを円滑に進めることができ、相続人の負担を大幅に軽減できます。
相続税の申告が容易になり、申告漏れも防げる
相続財産の総額が明確になるため、相続税の申告が必要かどうかの判断がしやすくなります。また、申告書を作成する際も、目録を参考にすることで手間が省け、財産の申告漏れといったミスを防ぐことにもつながります。
相続人間の無用な争いを未然に防ぐ
遺言者自身が作成した財産目録は、その内容に対する信頼性が非常に高いものです。相続人が作成したものと違い、「財産を隠している」といった疑念を払拭する効果があり、相続人間の無用な争いを防ぎ、円満な遺産分割協議を促します。
すべての財産に遺言者の意思を反映できる
遺言書に記載のない財産が後から見つかった場合、その財産は「遺言者の意思が示されていないもの」と見なされ、相続人全員による遺産分割協議で分け方を決めるか、法定相続分に従って分割されることになります。すべての財産を網羅した目録を作成し、それぞれの分割方法を指定しておくことで、ご自身の希望通りの遺産分割を確実に実現できます。
財産目録の作成方法と重要な注意点
【重要】2019年の法改正で自筆が不要に
まず知っておくべき重要な点として、平成31年(2019年)の民法改正により、自筆証書遺言に添付する財産目録は手書きでなくてもよくなりました。これにより、作成の手間が大幅に緩和されています。具体的には、以下の方法が認められています。
- パソコン等で作成し、印刷する方法
- 預貯金通帳のコピーや不動産の登記事項証明書など、財産を特定できる書類のコピーを添付する方法
記載すべき財産内容
財産目録には、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も漏れなく記載することが極めて重要です。記載すべき財産の具体例は以下の通りです。
- 預貯金: 金融機関名、支店名、預金種別(普通・定期など)、口座番号
- 不動産: 登記事項証明書(登記簿謄本)を参考に、所在、地番、地目、地積などを正確に記載
- 有価証券: 株式、投資信託、国債など(証券会社名、銘柄、数量など)
- その他: 自動車、生命保険、ゴルフ会員権、著作権、貴金属など
- 負債: 住宅ローン、借入金など(借入先、現在の残高など)
絶対に忘れてはいけない署名・押印
パソコンで作成したリストや書類のコピーを財産目録とする場合、絶対に守らなければならないルールがあります。それは、財産目録のすべてのページ(両面印刷の場合は両面)に、遺言者本人が署名と押印をすることです。
このルールは、パソコンで作成した目録だけでなく、預貯金通帳のコピーや登記事項証明書のコピーを財産目録として添付する場合も同様に適用されます。コピーであっても、そのすべてのページに署名・押印が必要です。
この署名・押印がないと、その財産目録は法的に無効と判断される可能性がありますので、絶対に忘れないようにしてください。
財産目録を定期的に見直す重要性
一度財産目録を作成しても、それで終わりではありません。時間の経過とともに、財産状況は変化します。不動産の売却、新たな口座の開設、相続による財産の増減など、生活の変化は財産内容に直結します。
古い情報のままの財産目録は、かえって混乱を招く原因となりかねません。ご自身の意思を正確に反映させるためにも、2~3年に一度、あるいは大きなライフイベント(結婚、不動産の購入・売却など)があった際には、遺言書と財産目録の両方を見直す習慣を持つことが極めて重要です。
まとめ
財産目録なしの遺言書も法的には有効ですが、残されたご家族の負担を減らし、深刻な相続トラブルを防ぐために、財産目録を必ず作成することを強くお勧めします。これは、法的な手続きのためだけではありません。残されるご家族への最後の思いやりであり、あなたの意思を確実に未来へつなぐための、極めて重要な一手です。
遺言書や財産目録の作成には、法的に定められた要件があり、それを満たさないと無効になってしまうリスクも伴います。ご自身の財産が多岐にわたる場合や、作成方法に少しでも不安がある場合は、弁護士や行政書士といった相続の専門家に相談することが、ご自身の意思を確実に実現するための最も確実な方法です。
※この記事のアイキャッチ画像は相続イラスト.com様の素材を使用しています。