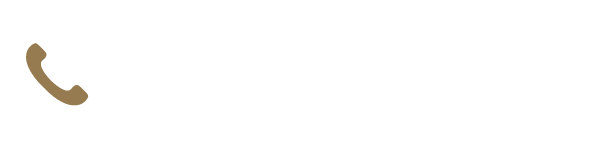ご依頼お待ちしております!!
推定相続人:法定相続人との違いを解説!相続権を失うケースや順位のルール

「『推定相続人』とは一体誰のことだろう?」「『法定相続人』や『相続人』という言葉と何が違うの?」 相続について調べ始めると、このような疑問に直面することがあります。これらの用語は似ていますが、使われるタイミングや意味合いが異なります。
この記事では、法定相続人や相続人との明確な違い、推定相続人を正確に特定する方法、そして知っておくべき注意点までをわかりやすく解説します。
結論から言うと、最も大きな違いは「推定相続人は相続発生前の呼び方、法定相続人は相続発生後の呼び方」であるという点です。この時間軸の違いを理解することが、相続の全体像を把握する第一歩となります。
推定相続人とは
推定相続人の定義
「推定相続人」とは、現時点で誰かが亡くなったと仮定した場合に、その人の法定相続人になるであろうと推定される人のことを指します。
例えば、父親・母親・長男・長女の4人家族がいるとします。もし現時点で父親が亡くなったと仮定すると、民法の規定に基づき、母親、長男、長女が財産を相続することになります。この場合、母親・長男・長女の3人が父親の「推定相続人」です。
なぜ「推定」と呼ばれるのか
「推定」という言葉が使われるのは、これが相続発生前の呼び名であり、相続権がまだ確定していないためです。将来、被相続人(財産を遺す人)が亡くなるまでの間に、家族構成が変わる可能性は十分にあります。
- 離婚すれば、元配偶者は相続権を失います。
- 推定相続人が被相続人より先に亡くなることもあります。
- 養子縁組をすれば、養子も相続権を持つことになります。
このように状況は変化しうるため、あくまで「現時点での予測」に過ぎません。したがって、推定相続人は被相続人の財産に対して具体的な権利を持つわけではなく、将来「相続人になるだろう」という期待権を有するに過ぎないのです。
この「期待権」はあくまで将来の期待に過ぎず、現時点での具体的な法的権利ではありません。そのため、例えば被相続人が生前に財産を不当に処分したとしても、推定相続人の立場ではその行為の無効を訴えることはできない、というのが判例の考え方です。
推定相続人、法定相続人、相続人の違い
相続に関する話し合いでは、これらの用語が混同されがちです。それぞれの意味を正確に理解し、使い分けることが重要です。
各用語の定義
- 法定相続人とは: 実際に相続が発生した(被相続人が亡くなった)際に、民法の定めによって遺産を相続する権利を有する人のことです。相続権が法的に確定した人を指します。
- 相続人とは: 法定相続人の中で、相続放棄などをせず、実際に財産を相続することになった人のことです。
違いのまとめ
3つの用語の違いを、時間軸(相続発生前か後か)と権利の確定状況(予測か確定か)の観点から表にまとめました。
| 用語 | タイミング | 権利の状況 |
|---|---|---|
| 推定相続人 | 相続発生前 | 将来相続人になるだろうという予測。権利は未確定。 |
| 法定相続人 | 相続発生後 | 民法に基づき相続する権利が確定した人。 |
| 相続人 | 相続発生後 | 実際に財産を相続した(または、することになった)人。 |
推定相続人が相続権を失う、または遺産を受け取れない主なケース
推定相続人であっても、必ず法定相続人になれるわけではありません。本人の意思に関わらず相続権を失うケースや、被相続人の意思、遺言の内容によって遺産を受け取れない場合があります。
相続欠格になった場合
「相続欠格」とは、相続において重大な非行を行った相続人が、法律上当然に相続権を失う制度です。被相続人の意思とは関係なく、以下の事由に該当すると自動的に相続資格が剥奪されます。
民法第891条に定められた欠格事由は以下の通りです。
- 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
- 被相続人が殺害されたことを知りながら告発・告訴しなかった者
- 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
- 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
推定相続人の廃除を受けた場合
「推定相続人の廃除」(民法第892条)とは、被相続人の意思により、家庭裁判所への申立てを通じて特定の推定相続人の相続権を剥奪できる制度です。
廃除が認められるのは、「被相続人に対する虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行」があった場合です。この制度は、遺留分(法律で保障された最低限の遺産取得分)を持つ配偶者、子、直系尊属(父母など)が対象となります。
ただし、相続権を完全に剥奪する強力な制度であるため、家庭裁判所が廃除を認めるハードルは高く、単に親子仲が悪いといった理由だけでは認められないのが実情です。
ポイント: 兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書で財産を渡さないと指定するだけで相続させないことが可能です。そのため、そもそも「廃除」の対象にはなりません。
遺言書で財産が他の人に遺贈された場合
遺言書がある場合、原則としてその内容が法定相続よりも優先されます。そのため、遺言書によって「全財産を特定の人(相続人以外でも可)に遺贈する」と指定されていた場合、推定相続人は遺産を受け取ることができません。
ただし、この場合でも、兄弟姉妹以外の法定相続人には「遺留分」を請求する権利が保障されています。遺留分とは、法律で定められた最低限の遺産の取り分のことです。遺言によって相続分がゼロになったとしても、配偶者、子、直系尊属は、遺産を受け取った人に対して自身の遺留分に相当する金銭を請求することができます。
推定相続人の範囲と順位
民法では、誰が推定相続人(および法定相続人)になるか、その範囲と優先順位が明確に定められています。
- 配偶者相続人: 被相続人の配偶者(夫または妻)は、常に推定相続人となります。
- 血族相続人: 配偶者以外の親族には順位があり、上位の順位の人がいる場合、下位の順位の人は相続人になれません。
- 第1順位:子 子が既に死亡している場合は、その子である孫などが代わりに相続します(これを代襲相続といいます)。ただし、子が「相続放棄」をした場合は、初めから相続人ではなかったとみなされるため、その子(被相続人の孫)への代襲相続は発生しません。
- 連れ子の扱い: 再婚相手の連れ子は、そのままでは相続権がありません。推定相続人となるには、被相続人と養子縁組をする必要があります。
- 非嫡出子の扱い: 婚姻関係にない男女間に生まれた子(非嫡出子)は、母との関係では自動的に相続権を持ちますが、父の財産を相続するには父による認知が必要です。
- 第2順位: 父母(子や孫がいない場合に相続人となります。父母が既に死亡している場合は、祖父母などの直系尊属が相続します)
- 第3順位: 兄弟姉妹(子、孫、父母、祖父母が誰もいない場合に相続人となります。兄弟姉妹が既に死亡している場合は、その子である甥・姪が代襲相続します)
- 第1順位:子 子が既に死亡している場合は、その子である孫などが代わりに相続します(これを代襲相続といいます)。ただし、子が「相続放棄」をした場合は、初めから相続人ではなかったとみなされるため、その子(被相続人の孫)への代襲相続は発生しません。
重要なのは、先の順位の人が一人でもいれば、後の順位の人は推定相続人にはならないという点です。例えば、子がいれば、父母や兄弟姉妹は推定相続人にはなりません。
推定相続人を確定させる方法
遺言書の作成や生前贈与など、相続対策を正確に行うためには、誰が推定相続人なのかを確定させることが不可欠です。そのための最も確実な方法は、戸籍を調査することです。
- 出生から現在までの戸籍謄本が必要
推定相続人を正確に特定するには、被相続人となる人の「出生から現在まで」の連続した全ての戸籍謄本(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)を取得する必要があります。 - なぜ現在の戸籍だけでは不十分か
現在の戸籍謄本には、結婚や転籍(本籍地の移動)をした後の情報しか記載されていません。過去の婚姻歴や、前の配偶者との間にできた子の存在などは、出生まで戸籍を遡らなければ判明しないためです。 - 戸籍の取得方法
戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場で取得できますが、2024年3月1日から始まった「広域交付制度」により、最寄りの市区町村役場の窓口でも(一部を除き)取得可能になりました。
古い戸籍は手書きで読みにくいことが多く、正確な解読には専門知識が求められる場合があります。不明な点があれば、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強く推奨します。
まとめ
この記事の要点を簡潔にまとめます。
- 推定相続人は、相続発生前の「相続人になる予定の人」を指す、予測の段階での呼び名です。
- 法定相続人は、相続発生後に、法律上の相続権が確定した人のことです。
- 両者の大きな違いは、タイミング(相続発生前か後か)と権利の確定状況(予測か確定か)にあります。
- 「相続欠格」や「推定相続人の廃除」に該当する場合や、遺言の内容によっては、推定相続人であっても相続権を失う、または遺産を受け取れないことがあります。
- 正確な推定相続人を特定するためには、被相続人となる人の出生から現在までの連続した戸籍謄本を収集することが必須です。
相続は、法律や手続きが複雑に絡み合う分野です。もしご自身の状況に不安な点や不明な点があれば、早めに専門家へ相談することをおすすめします。