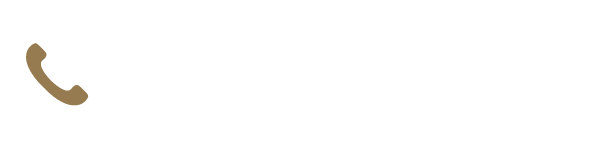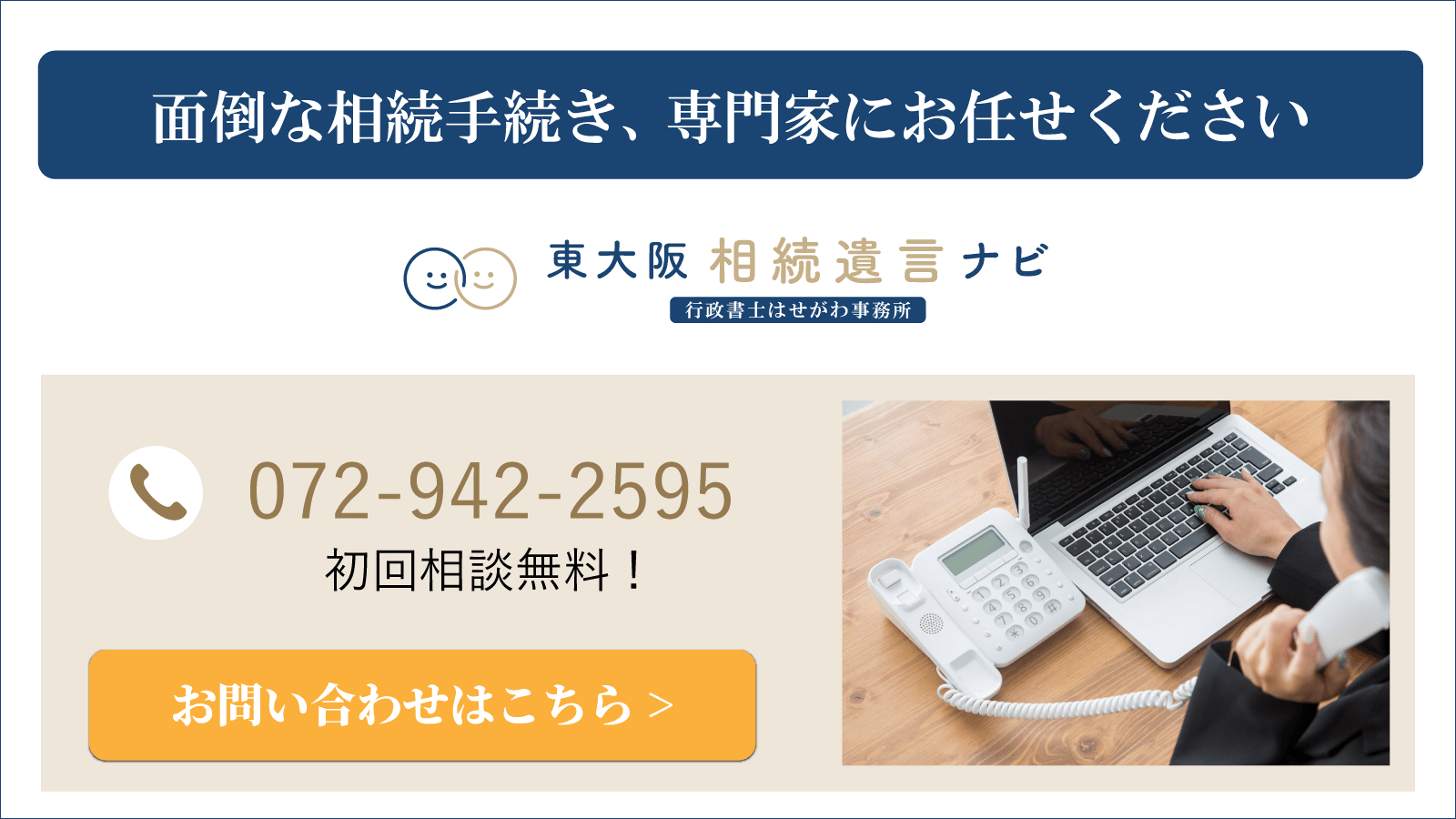初回相談無料!
相続手続きは自分でできる?判断基準と注意点を解説
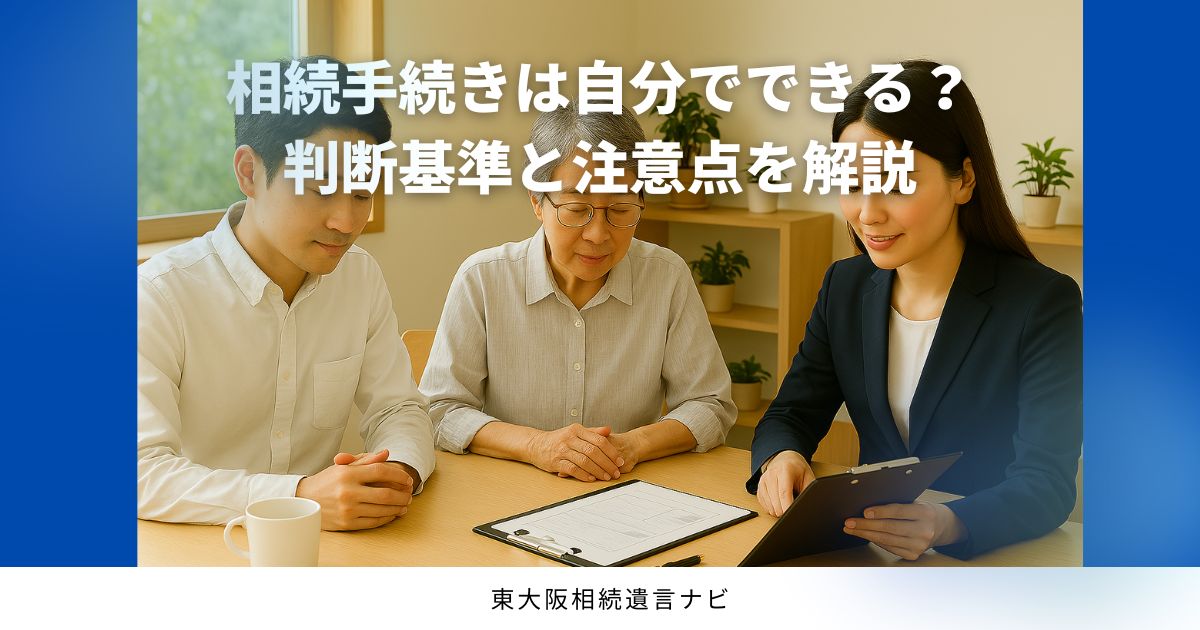
ご家族が亡くなられ、深い悲しみの中、相続という複雑で慣れない手続きに直面されていることと存じます。多くの方が「何から手をつけていいかわからない」「自分でできるのだろうか」と不安に感じていらっしゃいます。
行政書士として数多くの相続手続きをお手伝いしてきた経験から断言できるのは、「ご自身の状況を冷静に見極めること」が最も重要だということです。この記事では、そのための具体的な判断基準を、実務上の注意点と共にご紹介します。
そもそも相続手続きとは?全体の流れを5ステップで解説
ご自身で対応可能か判断する前に、まずは相続手続きの全体像を把握することが不可欠です。一般的な流れは、以下の5つのステップで進みます。
ステップ1:遺言書の確認
まず最初に行うべきは、故人が遺言書を残していないか探すことです。遺言書があれば、その内容が法定相続分や遺産分割協議よりも優先されるため、手続きの出発点が大きく変わります。
ステップ2:戸籍収集と相続人の確定
故人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を集め、法律上の相続人(法定相続人)が誰であるかを公式に確定させます。後から知らなかった相続人が現れるといったトラブルを防ぐための重要な作業です。
ステップ3:遺産分割協議と協議書の作成
相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。この協議は相続人全員の合意が原則であり、一人でも反対すると成立しません。合意内容は「遺産分割協議書」という正式な書類にまとめます。
ステップ4:預貯金や不動産の名義変更
遺産分割協議書に基づき、銀行口座の解約や不動産の所有者名義を、遺産を相続した人の名義へ変更します。各金融機関や法務局へ書類を提出して行います。
ステップ5:相続税の申告
相続した財産の総額が基礎控除額を超える場合、故人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告と納税が必要です。
【判断基準】相続手続きを自分でできるケース・専門家に任せるべきケース
それでは、この記事の核心である「自分でできるかどうかの判断基準」について、具体的なケースを見ていきましょう。
自分で手続きできる可能性が高いケース
以下の条件に当てはまる場合は、ご自身で手続きを進められる可能性があります。
- 時間に余裕がある
市区町村役場や金融機関、法務局などは平日の日中しか開いていません。平日に休みを取って、何度も足を運ぶ時間を確保できることが前提となります。 - 相続財産がシンプル(預貯金のみなど
相続財産が預貯金や解約しやすい保険のみで、不動産や非上場株式といった専門的な評価が必要なものが含まれていない場合、手続きは比較的単純です。 - 相続人の数が少なく、関係も良好
相続人が1人の場合は遺産分割協議が不要なため、手続きは最もシンプルです。人数が増えるほど、戸籍の収集や合意形成にかかる手間と時間は飛躍的に増大します。少人数で、全員が協力的で円満に話し合いができる場合、トラブルのリスクは低くなります。 - 手続きをやり遂げる意思と計画性がある
これは単にいくつかの書類を埋める作業ではありません。複数の期限を厳密に管理し、役所、法務局、複数の銀行などから集めた大量の書類を整理し、相続人全員と連絡を取り合うといった、 相当な整理能力と根気が必要です。
専門家への依頼を強く推奨するケース
一方で、以下のような状況では、無理をせず専門家に依頼することを強くお勧めします。
- 仕事などで忙しく、平日に時間が取れない
平日に役所や金融機関を訪れる時間を確保するのが難しい場合、手続きが滞り、期限を過ぎてしまうリスクがあります。 - 相続人同士の仲が悪い・意見が対立している
少しでも相続人同士の対立が予想される場合、当事者だけでの話し合いは困難を極めます。感情的な対立を避け、円滑に合意形成するためには第三者である専門家の介入が有効です。 - 相続財産が複雑(不動産、非上場株式、事業など)
不動産の評価、非上場株式の価値算定、個人事業の承継などが含まれる場合、手続きは非常に複雑になり、専門的な知識が不可欠です。 - 家族関係が複雑(前妻の子、認知した子がいるなど)
離婚・再婚歴がある、養子縁組をしている、認知した子がいるなど、家族関係が複雑な場合、相続人の確定(戸籍収集)だけでも大変な作業となり、漏れが生じるリスクも高まります。
自分で手続きするメリット・デメリット
ご自身で手続きを行う場合のメリットとデメリットを整理しておきましょう。
メリット
- 専門家に支払う費用を節約できる
- 手続きを通じて相続や家族の財産について詳しくなれる
- 第三者を介さないためプライバシーが保たれる
デメリット
- 戸籍謄本などの書類収集に多くの時間と手間がかかる
- 専門知識がないため、手続きのミスや書類の不備が起こりやすい
- 手続きの不備や相続人間の対立から、家族関係が悪化するリスクがある
【要注意】自分で進めるのが特に難しい手続き
相続手続きの中でも、特に専門性が高く、ご自身で進めるのが難しい手続きがいくつかあります。期限も厳格に定められているため、特に注意が必要です。
相続税の申告
相続財産の評価、税額を軽減する特例の適用、申告書の作成は非常に複雑です。最大の難関は、現金預金以外の不動産や非上場株式などの財産評価を正確に行うことで、ここに誤りが生じやすく、税務調査につながる可能性があります。相続税には「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」という基礎控除額があり、遺産総額がこれを超える場合に申告が必要です。
- 期限:相続があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内
不動産の名義変更(相続登記)
法務局に提出する必要書類が多く、遺産分割協議書も登記申請に使えるよう完璧に作成する必要があります。法務局のチェックは非常に厳しく、登記簿謄本と住所の表記がわずかに違う、といった些細なミスでも申請全体が却下され、やり直しを求められることも少なくありません。2024年4月1日から義務化され、正当な理由なく怠った場合は過料が科される可能性があります。
- 期限:不動産の取得を知った日から3年以内
相続放棄・限定承認
借金などマイナスの財産が多い場合に選択する手続きですが、家庭裁判所への申立てが必要です。書類に不備があると受理されない可能性があり、一度受理されると原則として撤回できません。
- 期限:相続があったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申立て
相続人間で争いがある場合の遺産分割協議
相続人同士で意見が対立している場合、当事者だけで話し合いをまとめることはほぼ不可能です。感情的になると客観的な対話はできなくなります。法律の専門家は、個人的な感情ではなく法的な権利と現実的な解決策に焦点を当てる「緩衝材」として機能するため、家族だけでは不可能な冷静な議論を可能にします。
困ったときは誰に相談する?専門家とその役割
相続に関する専門家は複数あり、それぞれ得意分野が異なります。状況に応じて適切な相談先を選びましょう。
| 専門家 | 主な役割 |
|---|---|
| 弁護士 | 遺産分割で揉めているなど、相続人同士のトラブル・紛争解決の専門家。交渉や調停・審判の代理人になれます。 |
| 司法書士 | 不動産の名義変更(相続登記)など、法務局に提出する書類作成の専門家。 |
| 税理士 | 相続税の申告が必要な場合の、税金計算と申告手続きの専門家。 |
| 行政書士 | 遺産分割協議書の作成や、戸籍収集、金融機関の手続きなど、役所や関係各所に提出する書類作成の専門家。 |
まとめ
相続手続きをご自身で行うことは、相続財産がシンプルで、相続人間の関係が良好、かつ時間に余裕がある場合には可能です。しかし、そのためにはご自身の状況を冷静に分析することが何よりも重要です。
少しでも不安があれば、一人で抱え込まずに専門家の窓口を叩いてみてください。初回の相談だけで、やるべきことの全体像が見え、心の負担が大きく軽くなるはずです。専門家の力を借りることで、手続きを円滑に進め、将来のトラブルを防ぐことにつながります。