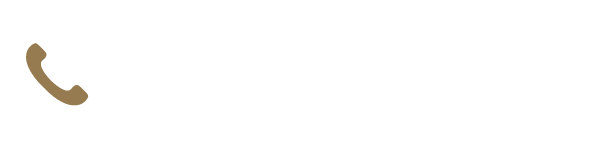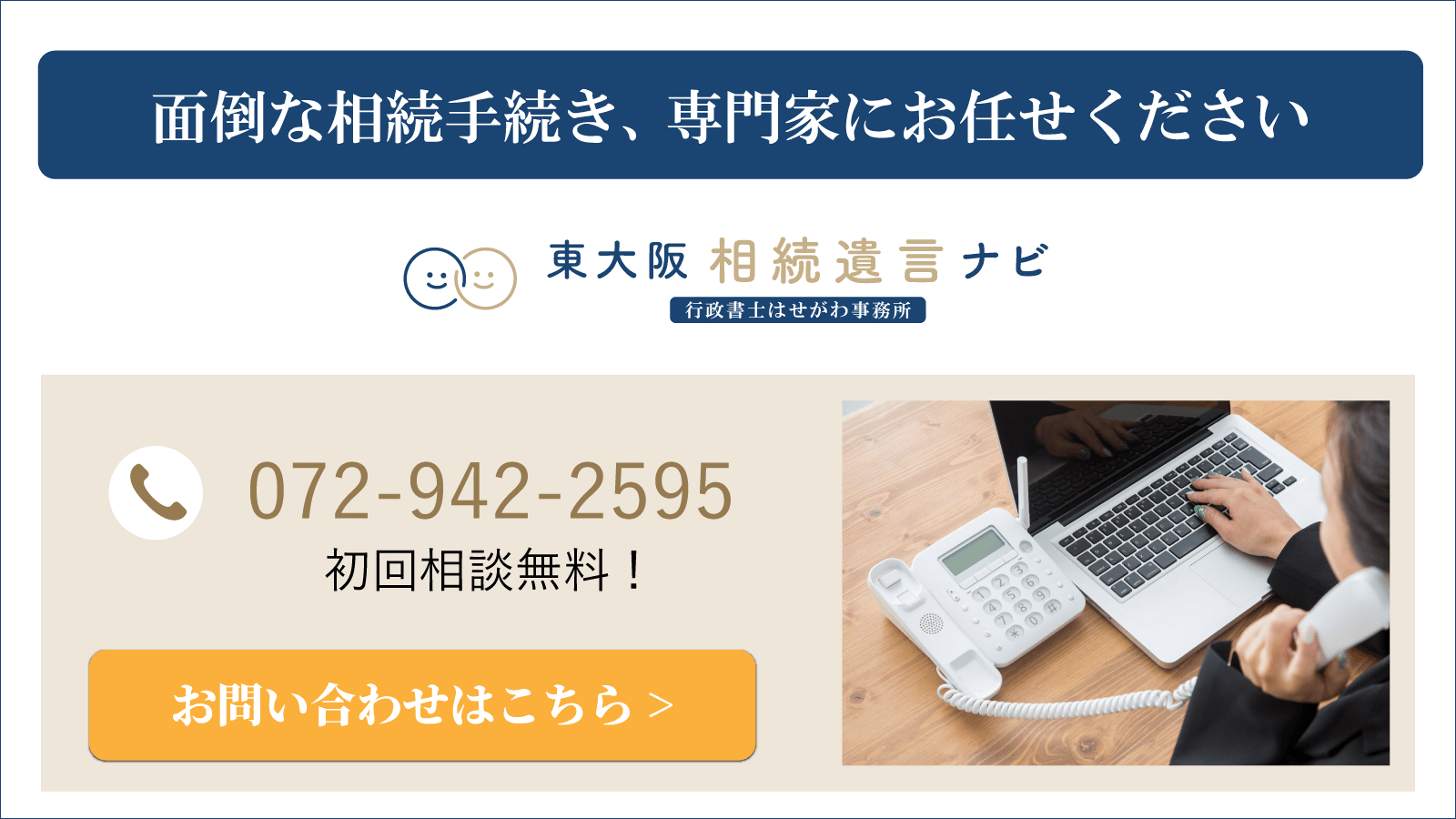初回相談無料!
相続農地は放置NG!売却・転用・相続放棄の選び方とは

農地を相続したけれど、自分では耕作する予定がない——そんなお悩みを抱えていませんか?
実は、農地の相続には固定資産税や管理コストなど、想像以上の負担がついて回ります。
本記事では、耕作しない農地を相続した場合の対処法について、売却・転用・相続放棄といった選択肢を具体的に解説します。
法律の制限や手続きの注意点にも触れながら、後悔しない判断をするためのポイントをわかりやすくお伝えします。
農地の相続で困ったときに、まず読むべき内容をまとめました。ぜひ参考にしてください。
相続した農地を耕作しない場合の対応方法
農地を相続したものの、自分では耕作しないというケースは少なくありません。その場合、いくつかの選択肢があります。
対応策としては、大きく分けて「農地のまま売却」「農地転用して売却」「相続放棄」の三つが挙げられます。
いずれの方法にもメリット・デメリットがありますので、農地の状況や相続人の事情に応じて最適な選択をすることが大切です。
相続した農地にかかる維持費の負担とは
農地を持ち続ける場合、維持管理には一定の費用がかかります。具体的には次のようなものが挙げられます。
固定資産税や草刈りなどの具体的なコスト
結論から言えば、農地を所有しているだけでも毎年費用が発生します。
主な費用は「固定資産税」と「管理費用」です。固定資産税は地目が農地であっても課税されます。さらに、雑草の繁茂を防ぐために年数回の草刈りが必要で、これにも人件費や機材費がかかります。
| 項目 | 内容 | おおよその費用感 |
| 固定資産税 | 地目が農地でも課税対象 | 数千円~数万円/年 |
| 草刈り費用 | 自分で行うか、業者へ依頼 | 数千円~数万円/回程度 |
| 境界管理や整地 | 隣地とのトラブル防止など | 数万円~必要に応じて |
これらの費用が毎年発生することを考えると、耕作しない農地を所有し続けるのは非効率と言えます。
耕作しない農地を放置するリスク
農地を放置すると、近隣への迷惑や行政指導を受けるリスクがあります。
例えば、草が伸び放題になれば害虫の発生源となり、近隣の住環境に悪影響を与えます。また、不法投棄や不審火の温床となることもあります。
自治体によっては雑草等の繁茂や生活環境の保全に関する条例などにより、所有者へ指導や勧告がなされる場合もあります。最悪の場合、行政代執行で強制的に草刈りが行われ、費用が請求されることもあるため注意が必要です。
相続農地を農地のまま売却する方法
農地をそのまま売却する方法は、シンプルな対処法ですが、いくつかの制限があります。
農地法による売却の制限と条件
農地を売却するには、「農地法」に基づいた手続きが必要です。
農地法第3条により、農地の権利移転は農業委員会の許可を受けなければ無効とされます。つまり、農地を農地として売る場合、買主が農業を営む意思と能力を持っていることが条件になります。
また、売却には現地調査や必要書類の提出など、多くの手続きが求められます。
農地を買えるのはどんな人か
農地を農地のまま購入できるのは、基本的に農業従事者に限られます。
具体的には、以下のような要件を満たす人です。
- 農業に従事している、またはこれから従事する意思がある
- 買受人自身が耕作に従事する
- 経営面積が地域の基準を満たしている
このように、買主に求められる条件が厳しいため、農地を農地のまま売却するのは簡単ではありません。
農業従事者減少による買い手不足の実情
現在、農業従事者の数は全国的に減少しています。
高齢化や後継者不足により、新たに農地を取得して耕作する人が少なくなっているのが現状です。
そのため、農地を売却しようとしても買い手が見つからず、数年単位で売れないケースも珍しくありません。売却活動には時間がかかることを見越して行動する必要があります。
農地転用して売却する選択肢
農地を他の用途に転用して売却する方法は、有効な選択肢の一つです。
農地転用の基礎知識と手続きの流れ
農地転用とは、農地を住宅用地や商業用地などに変更することを指します。
農地法第4条・第5条により、農地を農地以外に利用する場合、都道府県知事や農業委員会の許可が必要です。
手続きには、土地の現況調査や転用先の計画書の提出などが求められ、申請から許可まで数ヶ月かかることもあります。
都市計画区域内か外かによって手続きが異なるため、事前の確認が不可欠です。
宅地や駐車場などの活用例
農地を転用することで、さまざまな活用が可能になります。
たとえば、以下のような用途が考えられます。
- 宅地として住宅を建てる
- 月極駐車場やコインパーキング
- 資材置き場や倉庫用地
このように、転用すれば買い手の幅が広がり、売却しやすくなります。ただし、土地の立地やインフラ状況によっては、希望通りに転用できない場合もあります。
農地転用に必要な許可と注意点
農地転用には多くの注意点があります。
まず、申請者が所有者である必要があります。また、地域によっては市街化調整区域に指定されており、転用が難しいケースもあります。
さらに、農地の面積や用途によって追加の審査や開発許可が必要になることもあります。手続きが煩雑なため、専門家への相談が不可欠です。
相続放棄という選択肢もある
農地の管理や売却が難しい場合、「相続放棄」も検討すべき選択肢です。
相続放棄の基本と手続き期限
相続放棄とは、家庭裁判所に申述して財産の一切を受け取らないとする手続きです。
この手続きには期限があり、相続開始を知ってから3ヶ月以内に申述しなければなりません。相続放棄が認められれば、農地の管理義務も負わなくて済みます。
農地の維持費を完全に免れるメリット
相続放棄をすれば、農地の維持費は一切かからなくなります。
耕作しない農地に費用をかけ続けるよりも、全体の相続を放棄することで経済的な負担を回避できるのは大きな利点です。
他の財産も放棄するリスクとは
ただし、相続放棄をすると他の財産も一切受け取ることができません。
たとえば、預貯金や不動産、家財などのプラスの財産も全て対象外になります。農地のためだけに相続放棄を選ぶのは、慎重に検討すべきです。

相続農地の処分に迷ったらどうするか
農地の処分に悩む場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
専門家への早期相談の重要性
農地の相続や売却、転用に関する知識は一般の人にとって分かりにくいものです。
司法書士、行政書士、不動産業者などの専門家に早めに相談することで、後悔のない判断ができます。とくに、売却や転用には手続きが複雑なため、専門的なサポートが重要です。
地域の状況に応じた最適な判断とは
農地の価値や売却のしやすさは、地域によって大きく異なります。
都市部に近い農地であれば、転用によって高値での売却が可能な場合もあります。一方、過疎地や山間部では買い手が見つからないケースも少なくありません。
そのため、相続する前から地域の不動産事情を把握し、対策を練っておくことが重要です。
農地の相続でお悩みの方は行政書士へご相談ください
農地の相続は、法律や制度が複雑で、判断に迷うことも多くあります。
耕作しない農地の処分方法に困ったときや、相続放棄を検討している場合は、まずは専門家にご相談ください。
当事務所では、相続手続きに精通した行政書士が丁寧に対応いたします。さらに、不動産会社を併設しており、農地や空き地の査定・活用提案も無料で行っております。
相続に関するご不安を一つずつ解消していけるよう、全力でサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。