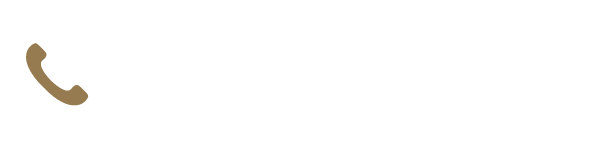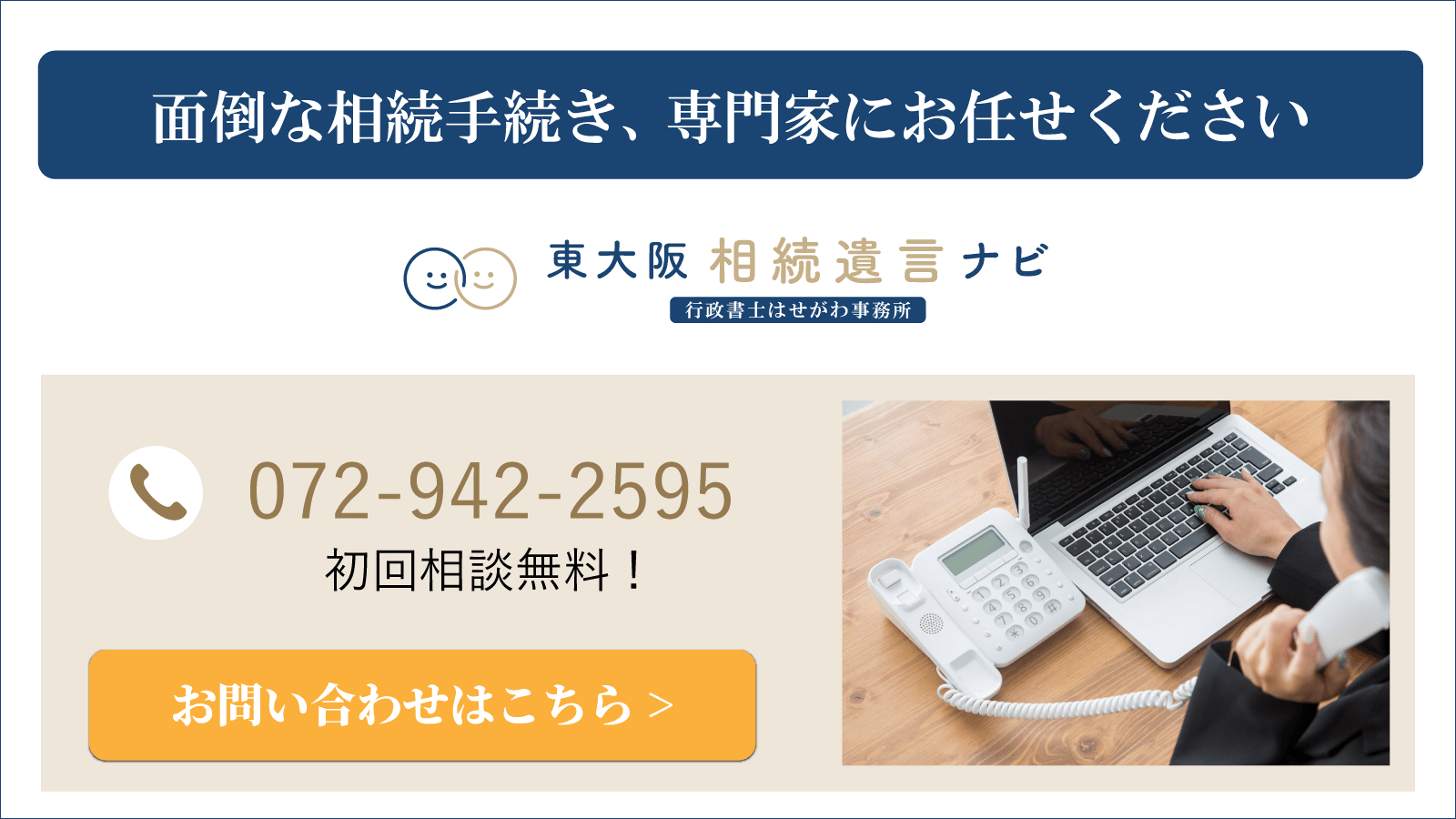初回相談無料!
遺贈(いぞう)
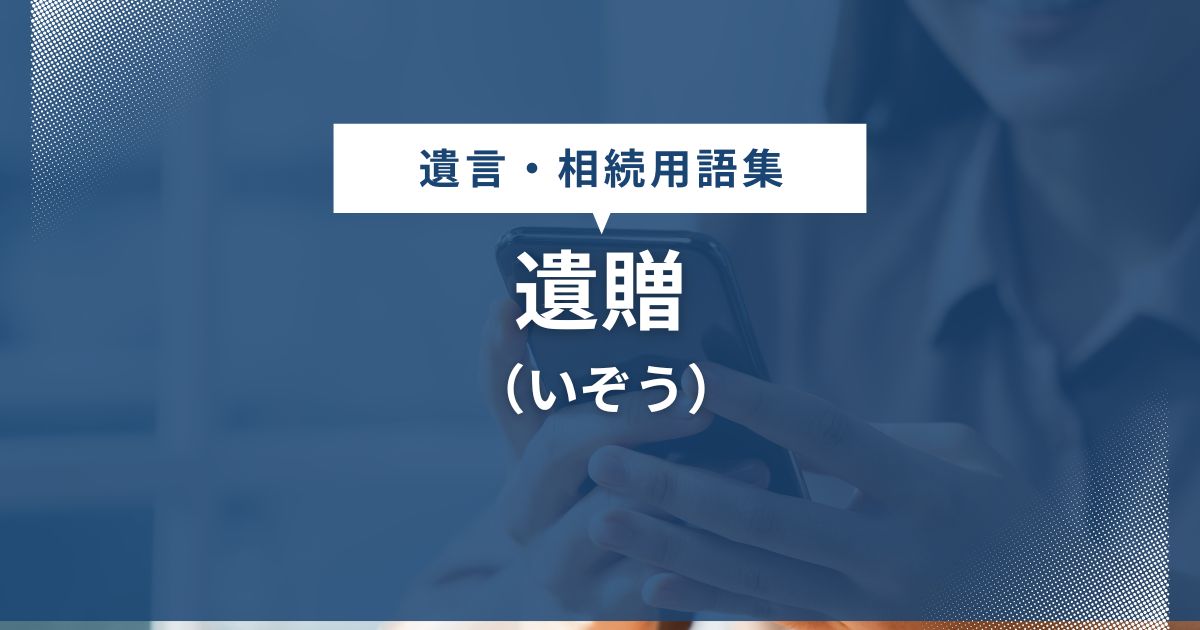
遺贈とは
「遺贈(いぞう)」とは、故人が生前に作成した「遺言」によって、その財産の一部または全部を無償で特定の個人や団体に譲る行為を指します。これは、自身の財産を誰にどのように残したいかという故人の意思を実現するための有効な手段です。
遺贈において財産を贈る人を「遺贈者」、財産を受け取る人を「受遺者」と呼びます。受遺者は、法定相続人(民法で定められた相続権を持つ親族)である必要はなく、個人だけでなく、法人や団体、さらにはまだ生まれていない胎児でも指定することができます。特に、社会貢献活動を目的として公益法人やNPO法人などに寄付する形式は、「遺贈寄付」と呼ばれ、近年注目されています。

遺贈の種類:特定遺贈と包括遺贈
遺贈には大きく分けて「特定遺贈」と「包括遺贈」の2種類があります。
特定の財産(例:特定の不動産、預貯金100万円など)を具体的に指定して遺贈する方法です。受遺者は指定されたプラスの財産だけを承継し、原則として、それ以外の負債などのマイナス財産を引き継ぐことはありません。
財産全体に対する割合(例:全財産の2分の1、遺産の30%など)を指定して遺贈する方法です。包括遺贈を受けた受遺者は、相続人と同一の権利義務を持つため、財産だけでなく、借金などの負債も割合に応じて引き継ぐことになります。
受遺者が特定遺贈された財産を放棄する場合、期限は定められておらず、遺言執行者や他の相続人に対して意思表示を行うことで可能です。一方、包括遺贈の放棄は、自己に包括遺贈があったことを知った日から3ヶ月以内に、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。
遺贈・相続・死因贈与の違い
財産を死後に引き継ぐ方法としては、「遺贈」のほかに「相続」や「死因贈与」があります。それぞれに違いがあるため、理解しておくことが重要です。
民法で定められた法定相続人が、被相続人(亡くなった人)の財産(プラスの財産とマイナスの財産を含む)を承継するものです。遺言書がなくても行われますが、遺言書で相続人の間で財産の配分を指定することも可能です。
遺言書が必須であり、法定相続人以外の人や団体にも財産を譲ることができます。受遺者は遺贈を放棄する選択権があります。
贈与者が亡くなった際に財産を贈与するという契約です。遺贈が贈る側の一方的な意思表示で成立するのに対し、死因贈与は贈る側と贈られる側の合意が必要です。
手続きや税金においても違いがあります。例えば、不動産取得税は、相続では非課税ですが、特定遺贈や死因贈与では課税されます。また、不動産の登記にかかる登録免許税も、法定相続人の場合は評価額の0.4%ですが、受遺者が法定相続人以外の場合は2%と高くなります。
遺贈のメリットとデメリット
メリット
- 遺言者の意思を最大限に反映できる:法定相続人ではない孫や兄弟姉妹、生前お世話になった人、または特定の団体など、本当に財産を残したい相手を自由に指定できます。
- 社会貢献につながる:NPO法人などの公益団体への遺贈(遺贈寄付)を通じて、自身の理想や社会への貢献を実現できます。
- 条件を付けることができる:例えば、受遺者に母親の生活費を渡すことを条件に自宅を譲る「負担付遺贈」も可能です。
- 生前の財産に影響しない:自身の老後資金などを心配することなく、死後の財産の使い道を決められます。
デメリットと注意点
遺贈は有効な手段ですが、計画なしに行うとトラブルの原因となることもあります。
遺留分(いりゅうぶん)侵害のリスク
- 遺留分とは:法定相続人(配偶者、子ども、直系尊属など)には、遺言の内容にかかわらず、法律で最低限保障された財産を相続する権利があります。
- トラブル回避:遺留分を侵害する遺言書も法的には有効ですが、侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」を行うことができます。これにより相続人間でトラブルが生じ、関係性が悪化する原因となるため、遺言書作成時には遺留分に配慮し、必要であれば遺言に遺贈の理由や気持ちを付言事項として記すことが推奨されます。
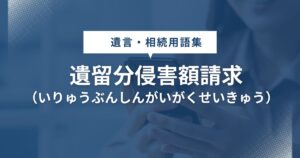
税金の問題
- 相続税:遺贈された財産には相続税が課税されます。
- 2割加算:受遺者が故人の一親等の血族(子や父母、代襲相続による孫)および配偶者以外の場合、相続税額が2割加算されます。
- 不動産取得税・登録免許税:不動産を特定遺贈で取得した場合、相続ではかからない不動産取得税が課税され、登録免許税も高額になります。
- 受遺者の負担:高額な税金が受遺者の負担となり、せっかくの遺贈を放棄せざるを得なくなるケースもあります。遺言者は受遺者に課せられる税金も考慮し、特定遺贈とするなど配慮することが重要です。
遺言書の有効性
遺贈は遺言書が必須であり、その書き方には民法で定められた厳格な方式があります。方式に不備があると遺言書が無効となり、故人の意思が実現できない可能性があります。
遺贈の手続きの流れ
遺贈を実現するためには、以下のステップを踏むことが一般的です。
- 遺言書の作成と保管:遺言者が自身の意思に基づき、法的に有効な遺言書(公正証書遺言、自筆証書遺言など)を作成します。遺言書の内容を実現する「遺言執行者」を指定することも重要です。
- 遺言書の検認(必要な場合):遺言者が亡くなった後、自筆証書遺言などの場合は家庭裁判所での「検認」が必要となります。公正証書遺言は検認が不要です。
- 遺言の執行:遺言執行者が、遺言書の内容に基づいて財産目録の作成、受遺者への財産引き渡しなど、遺贈の手続きを進めます。
- 相続税の申告と納付:遺贈を受けた受遺者は、原則として、遺言者が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告と納付を行う義務があります。
専門家への相談の重要性
遺贈は、故人の大切な想いを未来へ確実に繋ぐための強力な手段ですが、その手続きや税務、法的な側面は非常に複雑です。特に、遺留分への配慮や適切な遺言書の作成は、相続トラブルを避ける上で不可欠です。
そのため、遺贈を検討する際には、税理士や司法書士、弁護士などの専門家に相談し、適切な助言を受けることが強く推奨されます。専門家は、遺言者の意図を正確に法的な文書に落とし込み、税金の影響を考慮した最適な遺贈方法を提案し、受遺者がスムーズに財産を受け取れるようサポートしてくれます。
まとめ
遺贈は、遺言者の意思で特定の相手に財産を譲り渡すことができる、非常に自由度の高い制度です。しかし、その一方で、法定相続人の遺留分や相続税の2割加算、不動産取得税といった様々な注意点が存在します。これらの複雑な要素を適切に管理し、故人の大切な思いを確実に実現するためには、専門家の助けを借りることが、道しるべとなってくれるでしょう。遺贈はまさに、人生の最後に財産という「種」を蒔き、未来の誰かに「実り」を届けるようなものです。その種が確実に芽吹き、実を結ぶように、事前の準備と専門知識が不可欠です。