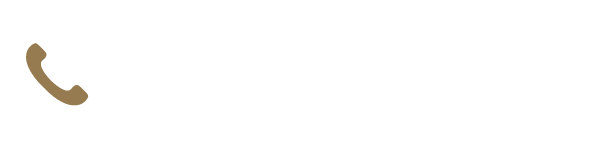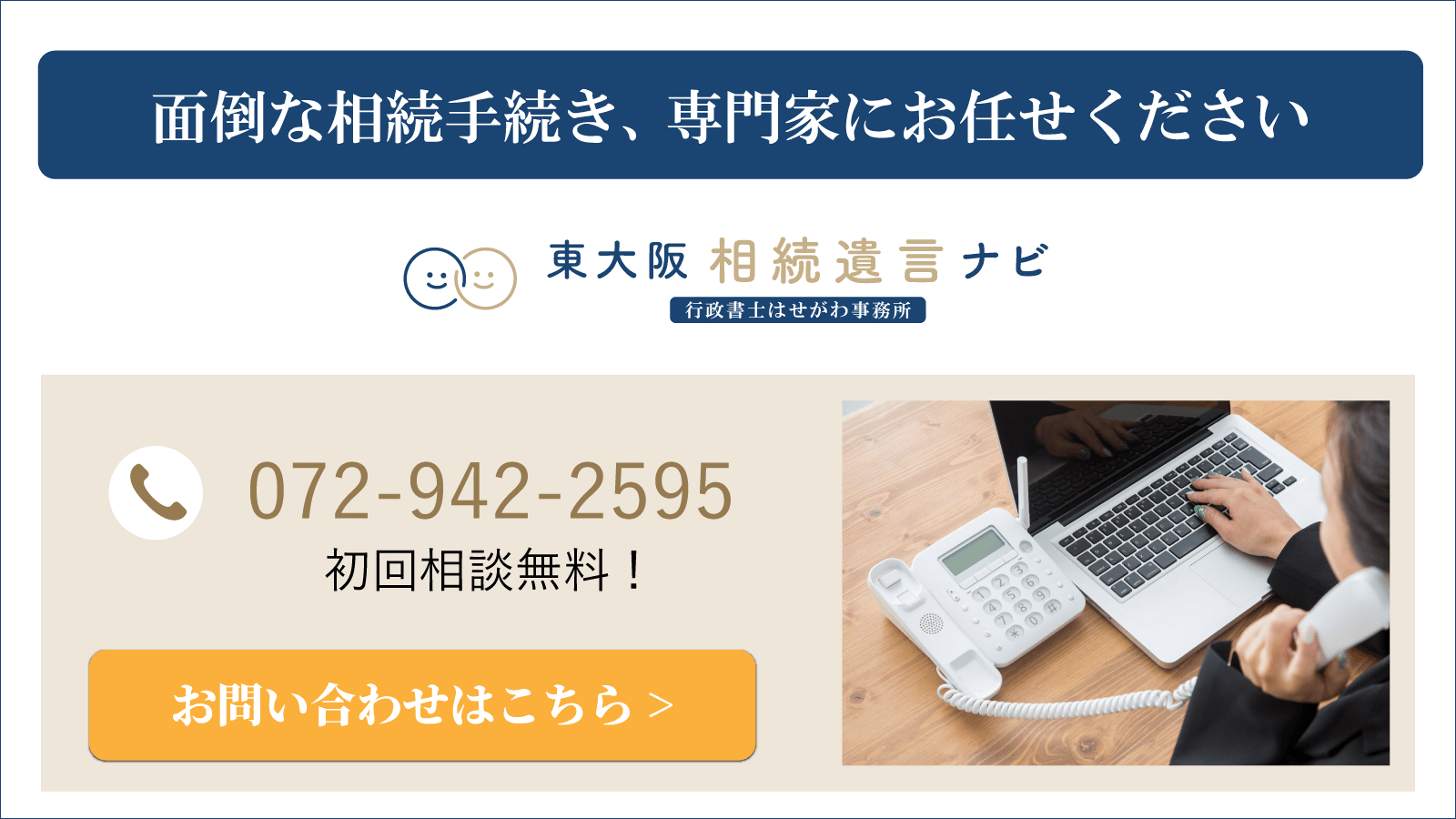初回相談無料!
遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)
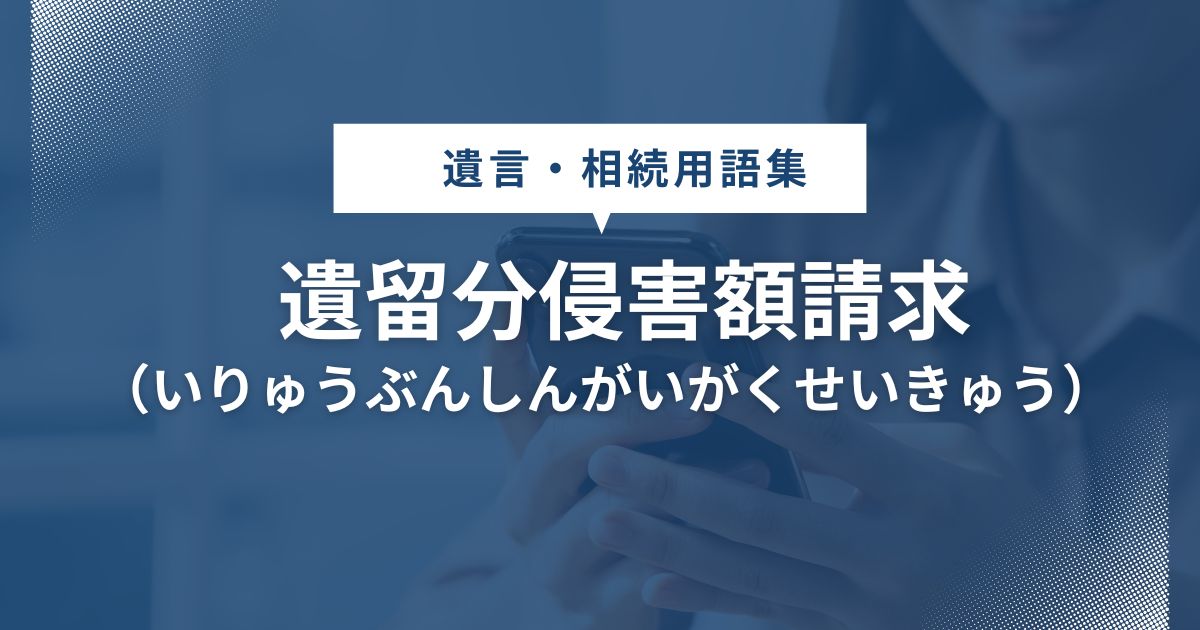
遺留分侵害額請求は、相続にまつわるトラブルを解決する上で非常に重要な制度です。ここでは、その内容を法律の専門家監修にも耐えうる正確さを保ちながら、一般読者にも分かりやすく解説します。
遺留分侵害額請求とは
遺産分割や遺言書に関するご相談では、この「遺留分」が問題となるケースが少なくありません。例えば、遺言書の内容によって、ご自身の相続分が全くなくなってしまったり、大幅に減ってしまったりする場合があります。このような不公平な状況を防ぐため、特定の相続人に保障された「最低限の財産分」を請求できるのが、遺留分侵害額請求です。
この制度は、2019年の民法改正によって大きく変化しました。以前は「遺留分減殺請求」という名称でしたが、現在は「遺留分侵害額請求」に変わっています。名称だけでなく、その内容もより分かりやすく、実用的になっています。
最も大きな変更点は、以前は現物で財産を取り戻す「現物返還」が、すべて「金銭請求」、つまり侵害された遺留分の金額に相当する金銭を請求するお金での解決に変わったことです。これにより、不動産などが共有関係になり、その後の処分や管理が複雑になることを避けられるようになりました。相続財産をめぐる権利関係の清算が、よりシンプルに行えるようになった点が特徴です。
遺留分とは
遺留分とは、法定相続人が最低限受け取ることが法律で保障されている相続財産の一部です。法定相続人とは、民法で定められた、亡くなった方(被相続人)の財産を相続する権利を持つ親族を指します。
この制度は、被相続人が遺言書によって財産を自由に処分できたとしても、残された法定相続人の生活が困窮しないよう、その権利を保護する目的で設けられています。つまり、遺言書による偏った財産の分配から、相続人を守るためのセーフティネットと言えるでしょう。
だれが遺留分を請求できるの?
遺留分侵害額請求ができる人、すなわち遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の法定相続人です。具体的には、被相続人の配偶者、子ども(代襲相続人である孫やひ孫も含む)、父母(直系尊属である祖父母も含む)が該当します。一方で、兄弟姉妹(およびその代襲者となる甥姪)には、遺留分は認められていませんので注意が必要です。
遺留分の割合はどのくらい
遺留分の割合は、法定相続人の組み合わせによって異なります。遺留分全体の割合は、大きく分けて二つのパターンがあります。
- 相続人が、配偶者や子ども(直系卑属)のどちらか一方でもいる場合は、相続財産の2分の1です。
- 相続人が、父母や祖父母(直系尊属)だけの場合は、相続財産の3分の1です。
これらの遺留分全体の割合を、法定相続人それぞれの法定相続分でさらに按分することで、個別の遺留分額が算出されます。例えば、法定相続人が配偶者と子2人の場合、遺留分全体の割合は1/2です。この1/2を、配偶者の法定相続分1/2と子らの法定相続分1/2(子1人あたり1/4)で按分します。結果として、配偶者の遺留分は1/4、子1人あたりの遺留分は1/8となります。
留分侵害額請求が発生する具体的なケース
遺留分侵害額請求は、相続人の最低限の取り分である「遺留分」が不当に減らされたときに認められる権利です。具体的には、大きく分けて遺言書、死因贈与、生前贈与の三つの場面で発生する可能性があります。
遺言書による指定
最も典型的なのは、被相続人が遺言書で財産の配分を一方的に決めてしまう場合です。例えば、複数の相続人がいるにもかかわらず、一部の相続人や親族以外の人物に大半の財産を遺贈する内容が書かれていることがあります。遺言が形式的に有効であればそのまま効力を持ちますが、遺留分を侵害された相続人は、財産を多く得た相手に対して遺留分侵害額請求を行い、侵害分を金銭で取り戻すことができます。
死因贈与が行われた場合
次に、死因贈与も遺留分を侵害する典型例です。これは「亡くなったら財産を渡す」という条件付きの契約で、遺言と似ていますが、生前に受贈者との合意を必要とする点で異なります。仮にこの契約が相続人の取り分を減らす結果になれば、やはり遺留分侵害額請求の対象となります。
生前贈与が行われた場合
さらに、生前に財産を大きく贈与してしまうと、残された財産が少なくなり遺留分を侵害することがあります。そのため、相続開始前10年以内に法定相続人に与えられた持参金や住宅資金などは「特別受益」とされ、遺留分計算の基礎に算入されます。また、相続開始前1年以内に相続人以外に贈与された財産も同様に算入されます。さらに、当事者が遺留分を害することを知りながら行った贈与や、時価とかけ離れた不当な価格での取引も、実質的に贈与とみなされ、侵害額請求の対象となり得ます。
このように、遺言や贈与は被相続人の意思を尊重する制度ですが、行き過ぎた偏りが生じた場合には、遺留分侵害額請求によって公平性を回復する仕組みが整えられています。
遺留分侵害額の計算方法
遺留分侵害額請求を行うためには、自分の遺留分がどの程度侵害されているのかを具体的に把握しなければなりません。計算は大きく3つのステップで行います。
基準となる財産価額を算定
まず、遺留分を計算するための基準となる「遺留分を算定するための財産の価額」を求めます。これは、被相続人が残した財産の総額に、生前贈与や遺贈の価額を加算し、そこから債務を差し引いて計算します。式で表すと「相続財産+贈与財産-債務」となります。ここでの贈与財産には、特別受益とされる住宅資金や事業資金の援助なども含まれます。
相続人ごとの遺留分額を計算
次に、算出した価額に遺留分全体の割合を掛け合わせます。その上で法定相続分に従って按分することで、各相続人の遺留分額が決まります。たとえば遺産総額6,000万円、相続人が配偶者と子ども2人の場合、遺留分割合は1/2です。配偶者の法定相続分は1/2なので遺留分は1,500万円、子どもはそれぞれ750万円となります。
遺留分侵害額の確定
次に、算出した遺留分額から、相続開始前に受けた特別受益や実際に取得した財産を差し引きます。その差額が遺留分侵害額です。ゼロまたはマイナスであれば、請求はできません。
シミュレーション例
具体例で確認しましょう。遺産総額6,000万円、相続人は配偶者Aと子B・Cの3人。遺言によりBが4,500万円、Aが1,000万円、Cが500万円を取得した場合、本来の遺留分はAが1,500万円、Cが750万円です。実際の取得額との差から、Aは500万円、Cは250万円をBに請求できることになります。
このように、遺留分侵害額は「基準価額の算定 → 各人の遺留分額の計算 → 実際取得分との差引き」という流れで求められます。請求の可否を判断するためにも、正確な計算が不可欠です。
遺留分侵害額請求の手続きと流れ
遺留分侵害額請求は、自ら権利を行使しなければ始まりません。手続きは交渉から始まり、まとまらなければ調停や訴訟へと進みます。
話し合い(交渉)
まずは遺留分を侵害した相手と話し合います。相手は親や兄弟など親族であることが多く、感情的な対立も起こりやすいため、弁護士に交渉を依頼することも検討されます。合意に至れば「合意書(和解書)」を作成し、可能であれば公正証書にしておくと安心です。
内容証明郵便での意思表示
交渉が進まない場合は、内容証明郵便で請求の意思を伝えます。これは、時効の進行を止め、後の証拠を残す効果があります。遺留分の侵害を知ってから1年で時効となる場合があるため、早めの対応が大切です。遺言執行者がいる場合はその人にも通知します。
家庭裁判所への調停
解決できなければ家庭裁判所に調停を申し立てます。調停委員が中立的に関与し、解決を促します。成立すれば「調停調書」が作成され、判決と同じ効力を持つため、相手が支払いに応じない場合は強制執行も可能です。ただし、調停申立て自体は意思表示に当たらないため、内容証明などは別途必要です。
訴訟の提起
調停が不成立となれば訴訟に進みます。裁判所が最終的に遺留分侵害額の有無や金額を判断します。訴訟は専門性が高く、証拠収集も重要となるため、弁護士の関与が強く推奨されます。請求額が140万円超は地方裁判所、それ以下は簡易裁判所が管轄です。
必要書類と費用
調停申立てには申立書のほか、被相続人や相続人の戸籍謄本、遺言書の写し、不動産や預貯金など財産の証明書類が必要です。費用は収入印紙1,200円分と、裁判所ごとに定められた郵便切手代がかかります。
このように遺留分侵害額請求は段階を踏んで進める手続きであり、期限や証拠を意識して準備を整えることが重要です。
遺留分侵害額請求権の時効と除斥期間
遺留分侵害額請求には厳格な期限があり、これを過ぎると権利を失ってしまいます。主な制限は「1年」と「10年」の二つです。
事実を知ってから1年
相続が開始したことと、遺留分を侵害する贈与や遺贈の事実を知った時から1年以内に請求しなければなりません。例えば、遺言書を提示された時点が典型的な起算点です。1年という期間は短いため、早めの対応が欠かせません。
相続開始から10年
事実を知らなかったとしても、相続開始から10年が経過すると権利は消滅します。これは「除斥期間」と呼ばれ、時効のように中断や延長ができないのが特徴です。
時効を止める方法
時効を中断するには、請求の意思を相手に伝える必要があります。口頭でも可能ですが、証拠を残すためには内容証明郵便を利用するのが確実です。これにより時効完成を一時的に猶予し、その間に交渉や調停の準備を進められます。
期限を過ぎれば権利行使ができなくなるため、遺留分請求では早めの行動と記録に残る意思表示が重要です。
遺留分侵害額請求をされた場合の対応
これまでは請求する側の視点を中心に解説してきましたが、逆に自分が遺留分侵害額請求を受けた場合の対応も知っておくことが大切です。請求を受けたときに冷静さを失い、感情的に反応してしまうと不利な結果を招くこともあるため、事前に流れを理解しておくと安心です。
無視は禁物。必ず対応を
遺留分侵害額請求の通知や内容証明郵便を受け取ったら、決して放置してはいけません。対応しないままでいると、相手が家庭裁判所へ調停を申し立てたり、訴訟を起こす可能性が高まります。もっとも、請求を受けたからといって必ずしもその全額を支払う必要はありません。まずは請求の内容を確認し、妥当性を判断したうえで、応じるか交渉するかを検討しましょう。
請求を受けた際のチェックポイント
- 請求額は正しいか
相手の主張する金額が本当に正当かどうかを確認します。遺留分が侵害されているのか、自分で計算してみることが重要です。ただし、特別受益などの判断は複雑なため、専門家に相談して金額の妥当性を確認するのが安心です。 - 時効にかかっていないか
遺留分侵害額請求権には時効があります。権利者が「相続開始」と「侵害の事実」を知ってから1年、または相続開始から10年が経過すると権利は消滅します。相手の請求がこの期間を過ぎていないかを必ず確認しましょう。 - 特別受益の有無
請求者が生前に多額の贈与を受けていた場合、それが特別受益にあたれば遺留分額から差し引かれ、請求額は減ります。贈与の有無や内容を調査し、必要であれば弁護士に依頼して正確に確認することが重要です。
遺留分侵害額請求を受けたときは、感情的に判断せず、事実関係を一つずつ検証する姿勢が求められます。相続トラブルは家族関係に影響することも多いため、法律的な視点だけでなく円満な解決を意識することも大切です。専門家の助言を得ながら、冷静に最適な対応を選択していきましょう。
遺留分侵害額請求に備える生前対策
遺留分侵害額請求が発生すると、家族間に深刻な対立が生じ、関係が壊れてしまう恐れがあります。そうした事態を避けるためには、被相続人が元気なうちに適切な準備をしておくことが大切です。ここでは代表的な生前対策を紹介します。
遺留分に配慮した遺言書の作成
最も基本的な対策は、遺留分に配慮した遺言書を作成することです。土地の代わりに金銭を相続させるなど、分け方を工夫すれば紛争を防げます。さらに「付言事項」で配分の理由や家族への感謝を伝えておくと、相続人の理解を得やすくなります。付言事項は法的効力はありませんが、トラブル防止に大きな効果を発揮します。
生命保険を活用した代償分割
不動産のように分割が難しい財産が多い場合は、生命保険を利用して代償分割を指定するのも有効です。不動産を受け取る子を保険金の受取人にし、その保険金を他の相続人の代償金に充てる方法です。これにより、不動産を相続しない相続人も現金で遺留分を確保でき、公平な分配が可能となります。
計画的な生前贈与
特定の相続人に多くの財産を渡したい場合は、早めに生前贈与を行うのも一案です。遺言がある場合、相続開始前10年以内の贈与が遺留分の対象になりますが、10年以上前の贈与は原則として対象外です。ただし遺言がない場合は、贈与が「特別受益」として遺産分割に考慮される可能性があるため注意が必要です。
遺留分の放棄
どうしても侵害が避けられないときは、遺留分権利者に放棄してもらう方法もあります。相続開始前に放棄する場合は家庭裁判所の許可が必要で、本人の自由意思や合理的理由、代償の有無などが審査されます。開始後であれば相続人同士の合意でも可能です。
事前に適切な備えをすることで、遺留分侵害額請求をめぐる争いを未然に防ぎ、家族の絆を守ることができます。
まとめ
遺留分侵害額請求は、遺言や生前贈与によって法定相続人の最低限の取り分が侵害された際に、その不足分を金銭で取り戻すための重要な権利です。2019年の民法改正により、現物返還ではなく金銭請求が原則となり、手続きが明確になりました。請求は話し合いから始まり、合意に至らなければ内容証明郵便での意思表示や家庭裁判所での調停、さらに訴訟へと発展する可能性があります。特に注意すべきは時効で、「侵害を知ってから1年」と「相続開始から10年」を過ぎると権利は消滅します。請求する側も、受ける側も冷静に状況を確認し、正確な計算と適切な対応を取ることが欠かせません。相続は感情的な対立を招きやすいため、専門家の助言を得ることでスムーズな解決につながります。遺言書の工夫や生命保険の活用、生前贈与の計画、遺留分放棄といった生前対策も重要です。将来のトラブルを避けるためにも、疑問や不安があれば早めに信頼できる専門家へ相談することをおすすめします。