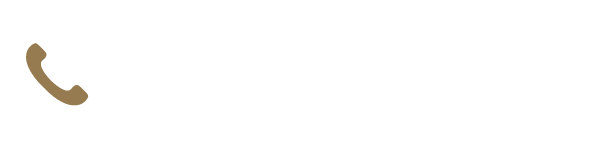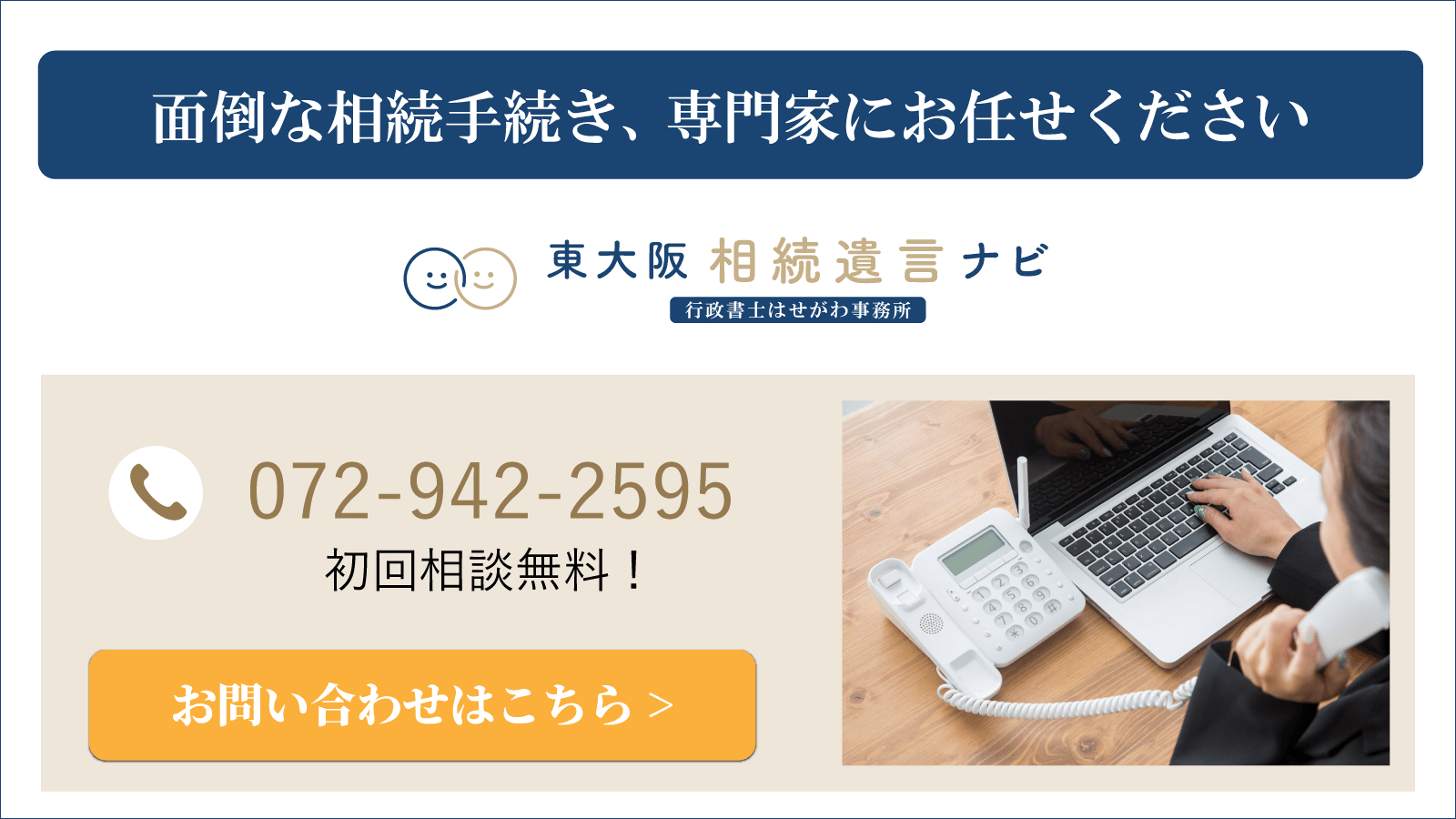初回相談無料!
遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)
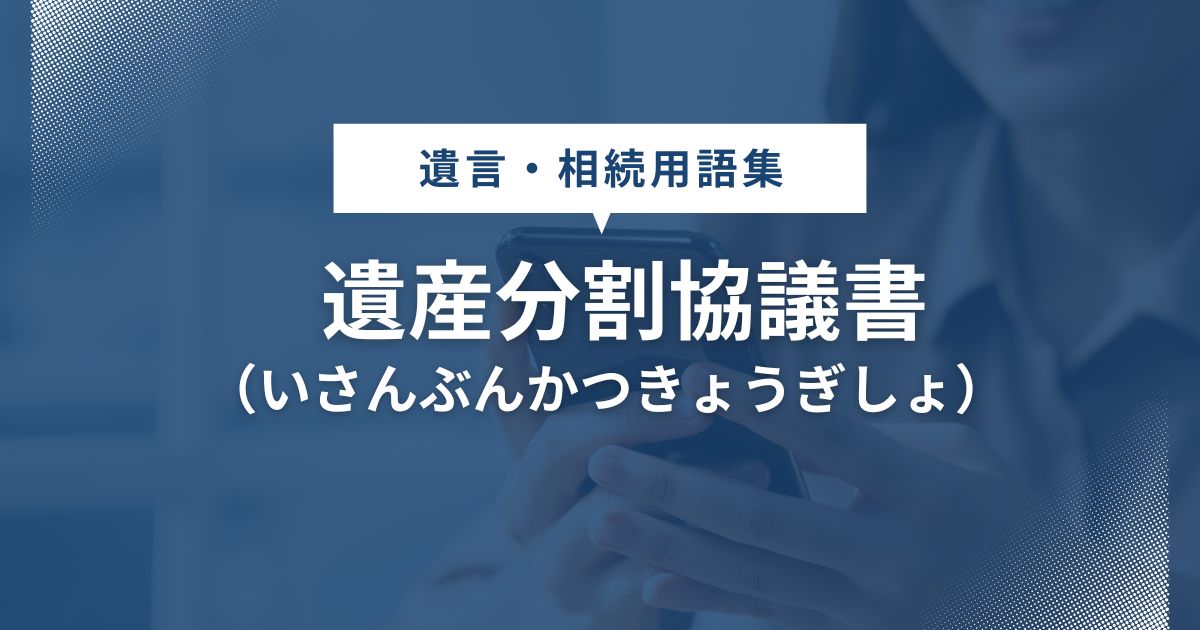
遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分け方について話し合い(遺産分割協議)を行い、その結果をまとめた正式な書類のことをいいます。相続人が複数いる場合、誰がどの財産を相続するのかを明確にするために作成される重要な書類です。
遺産分割協議書の目的と必要性
法律上、遺産分割協議は口頭でも成立するため、遺産分割協議書の作成は法的に義務付けられているわけではありません。しかし、相続が開始されたら、できるだけ早い段階で遺産分割協議を始め、遺産分割協議書を作成することが強く推奨されます。その主な目的と必要性は以下の通りです。
- 将来的なトラブルの防止
口約束だけでは、後になって「合意していない」「言った、言わない」といった認識の不一致や誤解による揉め事が生じる可能性があります。書面として残すことで、合意内容が明確になり、こうしたトラブルを未然に防ぐ証拠となります。 - 各種相続手続きの実施
遺言書がない場合、不動産の相続登記(名義変更)、預貯金の名義変更や解約・払戻し、株式の名義変更、自動車の名義変更などの手続きを進める際に、遺産分割協議書の提出が必須となります。これらの手続きが滞ると、将来的にさらなるトラブルにつながる恐れがあります。 - 相続税申告における特例の適用
相続税がかかる場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった有利な特例を適用するためには、遺産分割協議書を添付して相続税の申告書を提出する必要があります。申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)までに遺産分割協議ができていないと、これらの特例を受けられず、相続税が増えてしまう可能性があります。
遺産分割協議書が不要なケース
遺産分割協議書が不要なケースもあります。
- 相続人が一人だけの場合
- 被相続人が遺言書ですべての財産の分け方を指定しており、相続人全員がその遺言書の内容通りに遺産を分ける場合
ただし、遺言書がある場合でも、遺言書に記載のない財産が後から見つかった場合や、相続人全員の合意があれば遺言書と異なる分割を行うことも可能であり、その際には遺産分割協議書が必要となります。記録として残しトラブルを避けるために、遺産分割協議書を作成しておくことが一般的で賢明とされています。
遺産分割協議書作成までの流れとポイント
遺産分割協議書を作成するまでの一般的な流れは以下のステップで行われます。
相続人の調査と確定(法定相続人調査)
遺産分割協議は、被相続人の法定相続人全員で行わなければ無効となります。そのため、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を取り寄せ、誰が正式な法定相続人となるのかを正確に確定することが最初のステップです。
- 過去に認知した子 や、前妻との間に子がいた場合 も相続人に含まれます。
- 相続人の中に行方不明者がいる場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を請求し、その財産管理人が協議に参加します(家庭裁判所の許可が必要)。
- 認知症などで意思表示ができない相続人がいる場合は、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立て、成年後見人が本人に代わって協議に参加します。
- 未成年者が相続人の場合、親権者が代理しますが、親も相続人である場合は親子の利害が対立するため、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求する必要があります。
相続財産の調査と評価(財産調査)
プラスの財産(不動産、預貯金、株式、動産など)だけでなく、借入金やローン、未払金、保証債務などのマイナスの財産も含め、全ての財産を正確に把握し、財産目録を作成します。
遺産分割協議の実施
相続人および相続財産が確定したら、相続人全員で遺産の分割方法について話し合います。相続人全員の合意が得られれば、法定相続分とは異なる割合での分割も可能です。
話し合いの方法
全員が一堂に会する方法のほか、合意内容を持ち回りで確認・同意する方法 や、段階的に遺産分割協議を行う方法 も可能です。
合意が得られない場合
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を申し立て、それでも合意できない場合は遺産分割審判により裁判所が分割方法を決定します。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議で合意が得られたら、その内容を遺産分割協議書として書面にまとめます。書式に法的な決まりはなく、手書きでもパソコンで作成しプリントアウトしても構いません。
記載すべき内容
| 表題 | 「遺産分割協議書」と記載します。 |
| 被相続人の情報 | 亡くなった方(被相続人)の最後の本籍地、最後の住所、氏名、死亡日を記載します。 |
| 協議成立の文言 | 法定相続人全員が協議に参加し、合意に至った旨を明記します。 |
| 財産の具体的な分割内容 | 誰がどの財産を取得するかを明確に、かつ特定できるよう具体的に記載します。 不動産 登記簿謄本(全部事項証明書)に記載されている通り、所在地、地番、地目、地積(土地の場合)、家屋番号、構造、床面積(建物の場合)などを正確に記載します。登記簿謄本上の表記と異なる記載は、名義変更手続きで受理されない可能性があります。 預貯金 銀行名、支店名、預貯金の種類(普通・定期など)、口座番号、口座名義人を記載します。残高は利息などで変動するため、記載しないのが一般的です。 株式・有価証券 券会社名、発行会社名、保有株数を記載します。 債務・負債 債権者、契約内容、債務残高など、具体的な内容を記載します。 動産 家財道具、書画骨董品、貴金属など、具体的な品目を記載し、誰が取得するのかを明記します。 生命保険金・死亡退職金 これらは受取人固有の財産であり、遺産分割の対象とならないため、遺産分割協議書に記載する必要はありません。 |
| 後日判明した財産の取り扱い | 後から新たな遺産が発見される場合に備え、その取り扱い(例:「後日判明した財産は〇〇が相続する」など)を明記しておくと、再度の協議が不要となり、トラブルを防げます。 |
| 日付 | 遺産分割協議書を作成した日付を記入します。 |
| 相続人全員の署名と実印の押印 | 相続人全員が自筆で署名し、実印を押印する必要があります。一人でも欠けると遺産分割協議書は無効となります。 |
| 契印(割印)または製本 | 遺産分割協議書が複数ページにわたる場合は、改ざんを防ぐために契印(割印)が必要です。相続人全員が実印で、ページの見開き部分に押印します。枚数が多い場合は、製本テープで一冊にまとめ、表紙と製本テープにまたがる形で全員が押印する方法もあります。 |
| 作成部数 | 原則として相続人全員が1通ずつ保管できるよう、人数分の部数を作成します。法務局や金融機関に提出する際は、「原本還付」手続きをすることで、提出した原本を返却してもらい、他の手続きに使い回すことが可能です。 |
遺産分割協議書作成時に必要な書類
遺産分割協議書を作成し、その後の手続きを進めるためには、以下の書類が必要となります。
必ず必要な書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本:相続人を確定するため。
- 相続人全員の戸籍謄本:法定相続人の生存を確認するため。
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票:被相続人の最後の住所を確認するため。
- 相続人全員の印鑑登録証明書と実印:遺産分割協議書への署名・押印を証明するため。
- 財産目録:財産内容を一覧で把握するため(作成義務はないが、あると便利)。
相続する財産によって必要な書類
- 預貯金:残高証明書、預貯金通帳など。
- 不動産:登記簿謄本(全部事項証明書)、固定資産税納税通知書または評価証明書。
- 自動車:車検証のコピーなど。
- その他、ゴルフ会員権、貴金属などの鑑定書。
特別な場合に必要な書類
- 相続放棄申述受理証明書または相続放棄申述受理通知書:相続放棄者がいる場合に、相続放棄が認められていることを証明するため。
- 不在者財産管理人、成年後見人、特別代理人などが関与する場合は、それらの資格を証明する家庭裁判所の審判書。
書類収集には時間がかかる場合があるため、できるだけ早めに準備に取り掛かることが重要です。
遺産分割協議書のトラブルと専門家への相談
- 紛失した場合 遺産分割協議書を紛失した場合は、他の相続人から原本を借りて手続きを行うか、相続人全員の再度の署名・押印を得て再作成することが可能です。紛失を防ぐため、金庫などの安全な場所に保管しましょう。
- 内容に不備があった場合 記載内容に誤りや不足があると、遺産分割協議書自体が無効となり、手続きが進まなくなる恐れがあります。特に不動産の表記ミスなどは、再度相続人全員の署名・押印を伴う作り直しが必要となり、時間や手間がかかります。
- 合意内容が守られない場合 作成された遺産分割協議書に合意した内容を相続人が守らない場合、遺産分割協議自体を白紙に戻すことは原則としてできません。調停、訴訟、または強制執行といった法的手続きによって履行を求める必要があります。
まとめ
遺産分割協議書の作成は自分でも可能ですが、相続人の確定、財産調査、正確な書面作成など、専門的な知識や多くの手間を要する作業です。特に相続財産が複雑な場合や、相続人間で意見の対立が予想される場合は、弁護士、司法書士、税理士、行政書士といった専門家、または信託銀行の遺産整理業務 などのサポートを検討することをお勧めします。専門家は、書類作成だけでなく、協議の進め方やトラブル解決のアドバイスも提供してくれます。