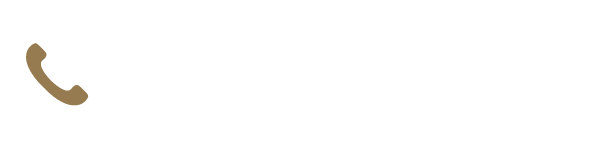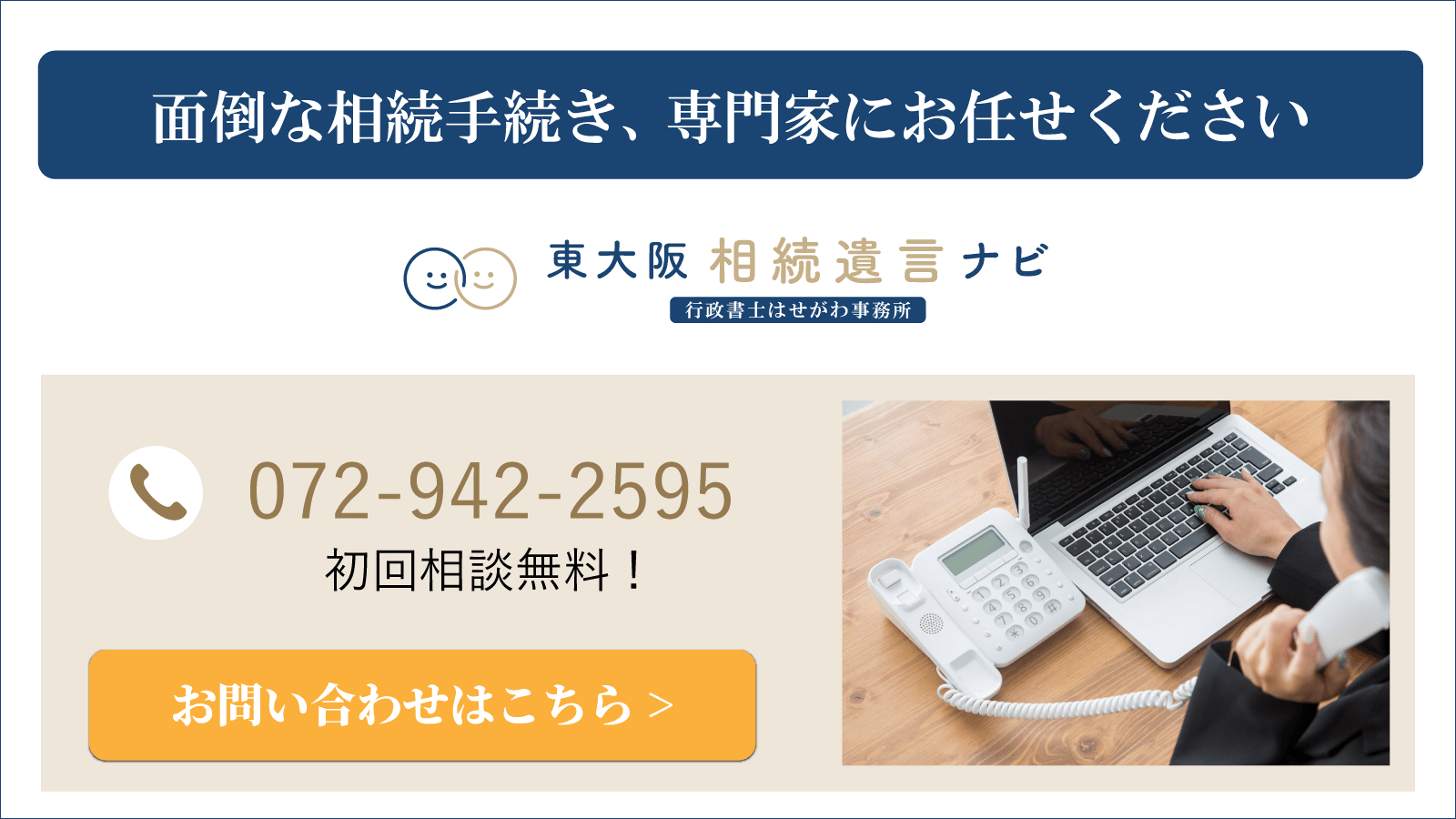初回相談無料!
遺留分(いりゅうぶん)
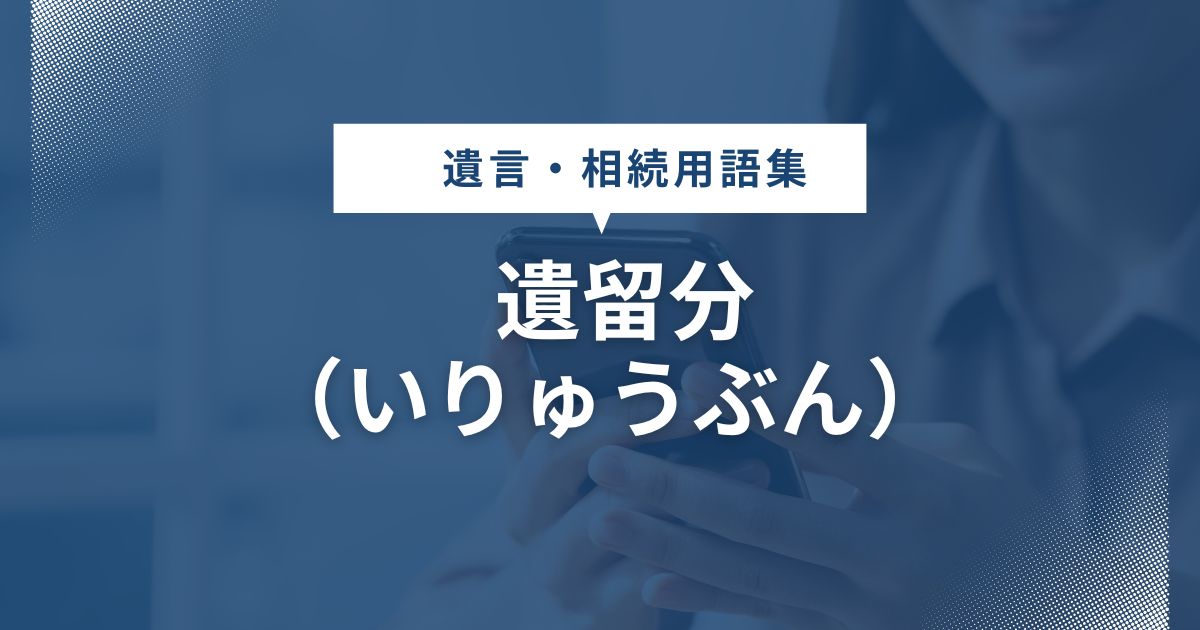
遺産相続において、遺言書が残されている場合、通常はその内容が優先されます。しかし、遺言書の内容によっては、特定の相続人が一切財産を受け取れないという不公平な状況が生じることもあります。このような事態から相続人を守るため、民法で定められているのが「遺留分(いりゅうぶん)」という制度です。
遺留分とは
遺留分とは、兄弟姉妹を除く「法定相続人(ほうていそうぞくにん)」に、法律上最低限保障されている遺産の取り分のことです。遺言の自由を尊重しつつも、残された家族の生活を守る目的があります。遺留分は、法律で定められた相続人が主張できる最低限度の権利と言えるでしょう。
遺留分が認められる相続人
遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。具体的には、亡くなった方の配偶者、子どもや孫などの「直系卑属(ちょっけいひぞく)」、そして親や祖父母などの「直系尊属(ちょっけいそんぞく)」が該当します。
代襲相続の場合
子どもがすでに亡くなっている場合、その子どもである孫が「代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)」として相続します。このような代襲相続の場合にも、孫には遺留分が認められます。また、親が亡くなっている場合には、祖父母にも遺留分が認められます。
遺留分が認められない人
一方で、兄弟姉妹(甥・姪も含む)には遺留分が認められていません。また、被相続人(亡くなった人)を殺害するなどの犯罪行為があった「相続欠格者(そうぞくけっかく)」や、虐待などにより相続権を剥奪された「相続廃除(そうぞくはいじょ)」された人も、遺留分を失います。さらに、自らの意思で相続権を放棄した「相続放棄(そうぞくほうき)」をした人や、遺留分を放棄した人も権利は認められません。
遺留分の割合
遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。
- 直系尊属のみが相続人である場合は、遺産全体の3分の1が遺留分となります。
- それ以外の相続人(配偶者、子どもなど)がいる場合は、遺産全体の2分の1が遺留分となります。
この遺産全体に対する遺留分(総体的遺留分)を、各相続人の「法定相続分(ほうていそうぞくぶん)」に応じて分け合います。例えば、配偶者と子ども2人が相続人の場合、遺産総額8,000万円で計算すると以下のようになります。
- 配偶者: 総体的遺留分(1/2)× 法定相続分(1/2)= 1/4 (2,000万円)。
- 子ども1人あたり: 総体的遺留分(1/2)× 法定相続分(1/4)= 1/8 (1,000万円)。
遺留分侵害額請求とは?(2019年法改正)
遺言書によって遺留分が侵害された場合、遺留分権利者(遺留分が認められる相続人)は「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」を行うことができます。これは、遺留分を侵害している相手に対し、侵害された分の金銭を請求する権利です。
法改正について
2019年7月1日以降に発生した相続からは、民法の改正により遺留分制度が変わりました。改正前は「遺留分減殺請求」と呼ばれ、不動産などの「物的権利(ぶってきけんり)」を請求できましたが、その結果、財産の共有状態が生じるなど複雑な問題がありました。 法改正後は、原則として侵害された遺留分に相当する「金銭」を請求できるようになりました。これにより、不動産などの共有状態を避けることが可能になり、トラブルの回避に繋がっています。
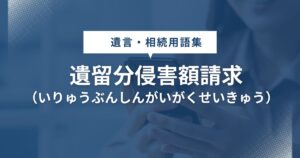
遺留分侵害額請求の対象となる財産
遺留分侵害額を算定するための財産には、主に以下のものが含まれます。
- 遺贈(いぞう)による財産: 遺言書で特定の人に贈与された財産です。
- 死因贈与(しいんぞうよ)による財産: 贈与する人が亡くなったときに効力が発生する契約による贈与です。
- 生前贈与(せいぜんぞうよ)による財産: 被相続人が生前に贈与した財産です。
生前贈与の対象期間
生前贈与は、原則として相続開始前1年間のものが対象です。しかし、贈与者と受贈者の双方が「遺留分を侵害すること」を知っていた場合は、1年以上前の贈与も対象となります。 また、相続人への生前贈与が「特別受益(とくべつじゅえき)」に該当する場合は、原則として相続開始前10年以内の贈与が対象となります。
例外規定
中小企業の株式や事業用財産を後継者に承継させる場合など、一定の要件を満たすことで遺留分侵害額請求の例外となる場合があります。これは、中小企業の事業承継を円滑に進めるための特例です。
請求の順序
複数の贈与がある場合、請求には順序が定められています。まず「遺贈」を受けた人に請求し、不足があれば「死因贈与」を受けた人に請求します。さらに不足がある場合は「生前贈与」を受けた人に請求し、生前贈与は日付が新しいものから対象となります。
遺留分侵害額請求の請求期限(時効)
遺留分侵害額請求権には期限があります。
- 1年間の時効: 相続が開始したことと、遺留分が侵害されたことの両方を知った日から1年以内に請求する必要があります。この期間を過ぎると「消滅時効(しょうめつじこう)」により請求できなくなる可能性があります。
- 10年間の期間制限: 相続開始や遺留分侵害の事実を知らなくても、相続開始から10年が経過すると、遺留分を根拠とする請求はできなくなります。
遺留分侵害額請求の流れ
遺留分侵害額請求は、以下の流れで進めるのが一般的です。
- 話し合い: まずは、遺留分を侵害している相手と直接話し合いを行います。この際、請求した事実を残すため、「内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん)」で請求書を送付することが重要です。
- 調停: 話し合いで合意に至らない場合、家庭裁判所に「遺留分侵害額の請求調停(いりゅうぶんしんがいがくのせいきゅうちょうてい)」を申し立てます。ここでは、裁判官や「調停委員(ちょうていいん)」を交えて話し合いを進めます。
- 訴訟: 調停でも合意が得られない場合は、「訴訟(そしょう)」を提起し、地方裁判所で遺留分の支払額などが決定されます。
請求時の注意点
遺留分侵害額請求は、請求する側が遺留分を侵害されていることを証明する必要があります。根拠となる資料を事前に揃えておくことが大切です。また、手続きは複雑であり、相続トラブルに発展しやすい性質があります。不安な場合は、相続分野に詳しい弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
遺留分侵害を避けるための対策
遺留分に関するトラブルは、被相続人が遺留分に配慮しない遺言書を作成することで発生することが多いです。円滑な相続を目指すためには、以下の対策を検討しましょう。
- 遺留分の知識を身につける: 遺言書や生前贈与を検討する際は、遺留分を意識した内容にすることが大切です。
- 生前から家族で話し合う: 遺産総額や承継の内訳について、生前から家族全員で話し合い、相互理解を深めることがトラブル防止に繋がります。
- 専門家に相談する: 遺留分や相続は専門的な知識が必要となるため、弁護士、税理士、金融機関などの専門家のアドバイスを受けるのが賢明です。特に二次相続(相続人が複数回発生すること)も考慮に入れると、より複雑になるため、早めの相談が推奨されます。
遺留分は、残された家族の生活を守るための重要な権利です。適切な知識と準備で、スムーズな相続を目指しましょう。