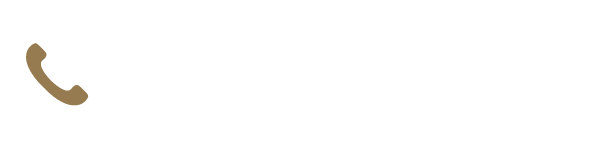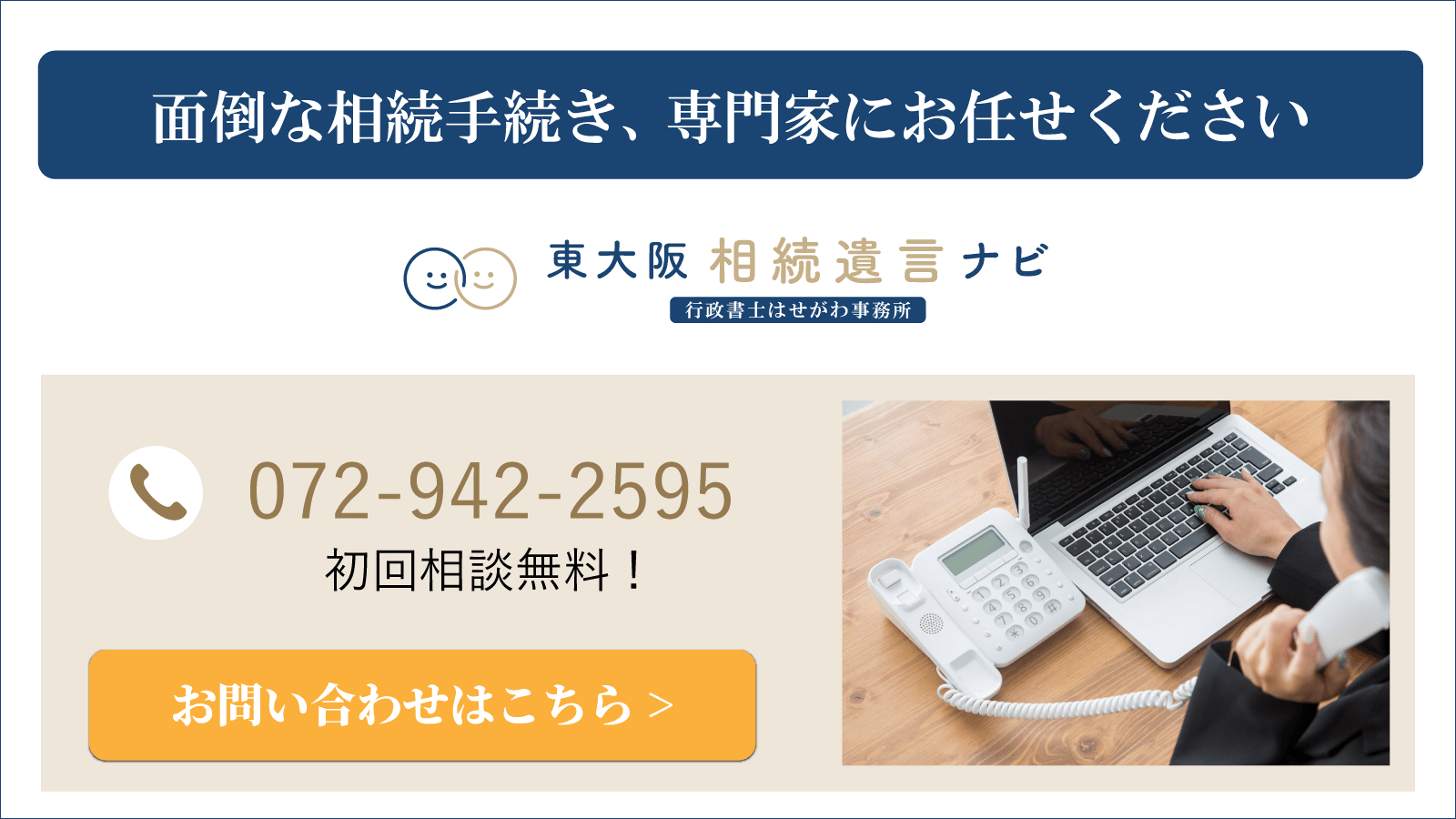初回相談無料!
改製原戸籍(かいせいげんこせき)
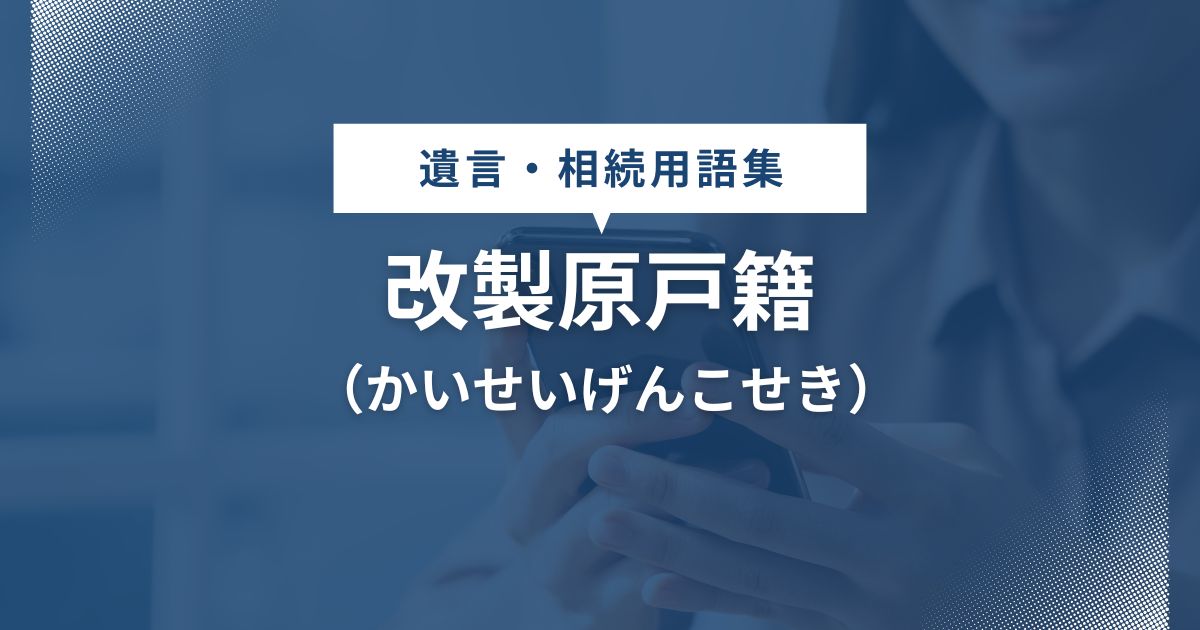
改製原戸籍(かいせいげんこせき)とは、法務省令による制度改正以前の古い様式の戸籍を指します。一般的には「はらこせき」と読まれることが多いです。戸籍法はこれまでに何度か改正されており、その際に戸籍の様式が変更されたため、改製前の戸籍が「改製原戸籍」となります。
現在、代表的な改製原戸籍として「平成改製原戸籍」と「昭和改製原戸籍」があります。
改製原戸籍の主な特徴
様式・縦書き
現在の戸籍がA4横書きでコンピューター記録されているのに対し、改製原戸籍はB4サイズの縦書きで文章形式で記載されています。特に平成改製原戸籍は、平成6年の法改正に伴うコンピューター化以前の様式です。
• 記載内容の違い: 改製原戸籍と現在の戸籍謄本では記載内容に違いがあります。法改正により戸籍の様式が変更される際、その時点で効力のない情報(例:改製前に除籍された人の情報、改製前になされた認知・養子縁組・離婚など)は現在の戸籍謄本には転載されず、記載されません。
種類
- 平成改製原戸籍: 平成6年(1994年)の法改正に伴うもので、戸籍のコンピューター化以前の書式です。
- 昭和改製原戸籍: 昭和22年(1947年)の法改正に伴うもので、戸籍の基本単位が「家」から「夫婦」に変更され、「戸主」の欄が「筆頭者」に変わる前の様式です。昭和改製原戸籍には「戸主」が記載されており、筆頭者の欄が「前戸主」と書かれているのが特徴です。
- その他、大正4年式戸籍や明治31年式戸籍も存在します。
保存期間
改製原戸籍簿の保存期間は、平成22年6月1日の法改正によって150年に延長されました(起算日は改製の翌年)。ただし、この法改正以前に保存期間が経過した改製原戸籍は、すでに廃棄されている可能性があります。
改製原戸籍が必要となる場面
改製原戸籍は、主に現在の戸籍謄本では確認できない過去の身分関係を証明する必要がある場合に用いられます。
相続手続き
- 相続人の調査・確定
被相続人(亡くなった人)の生まれてから死亡するまでの全ての戸籍情報を集めて、法定相続人を調査・確定するために必要です。現在の戸籍謄本には記載されていない情報があるため、改製原戸籍が不可欠です。 - 金融機関での手続き
被相続人の銀行口座の解約や、有価証券、不動産の名義変更手続きなど、金融機関や関係機関に提出を求められることがあります。
過去の身分事項の証明
改製前に除籍された人、改製前になされた認知・養子縁組・離婚など、現在の戸籍には記載されない過去の重要な身分事項を証明する場合に必要となります。
家系の確認
昭和の法改正で戸籍の単位が変更されたため、家系のつながりを遡って確認する際に複数の改製原戸籍が必要となることがあります。
相続登記(不動産の名義変更)
登記簿上の住所と住民票の除票上の住所が異なる場合、原則として「改製原戸籍の附票」が必要となります。
改製原戸籍の入手方法
取得できる人
- 原則として、本人、同一戸籍に記載されている人(配偶者)、直系尊属(祖父母・父母)、直系卑属(子・孫)です。
- 上記以外の人でも、正当な事由がある場合や、委任状がある場合は取得が可能です。例えば、相続人が兄弟姉妹で法定相続人の確定に必要な場合や、司法書士・税理士などの士業が代理で取得する場合などが該当します。
- 第三者(債権者、生命保険会社、成年後見人など)が請求する場合は、その理由や提出先などを請求書に詳しく記載し、利害関係を証明する書類の提示が必要です。
取得場所
- 本籍地の市区町村役場
改製原戸籍は、原則として被相続人の本籍地の市区町村の役所・役場の窓口で取得できます。 - 広域交付
令和6年3月1日からは、近くの市区町村役場でも改製原戸籍謄本の取得が可能になりました。ただし、この広域交付で取得できるのは、本人、配偶者、直系尊属(祖父母・父母)、直系卑属(子・孫)のものに限られます。代理人や兄弟姉妹などの改製原戸籍謄本は、これまで通り本籍地の役所で手続きが必要です。 - 郵送での取り寄せ
本籍地が遠方の場合、本籍地の役所に郵送で請求することも可能です。 - コンビニでは不可
マイナンバーカードを持っていても、改製原戸籍謄本はコンビニエンスストアでは取得できません。コンビニで取得できるのは、現在の戸籍謄本などです。
必要書類
- 交付申請書(申請窓口や役場のホームページから入手)。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)。
- 発行手数料:1通につき750円。
- 代理人が請求する場合は委任状。
- 親族関係が確認できない場合は、親族関係が確認できる資料(請求する方の戸籍謄本など)。
- 郵送で請求する場合は、交付手数料分の定額小為替と、住所・氏名を記載し切手を貼った返信用封筒。
注意するべきこと
- 相続手続きでは、複数の改製原戸籍や除籍謄本が必要になることが多いため、手続きをスムーズに進めるために2〜3セット余分に取得しておくと良いでしょう。
- 被相続人の本籍地が不明な場合は、本籍地の記載のある住民票を取得することで判明します。
- 戸籍の届け出がされてから記載が完了するまでに時間がかかる場合があるため、請求前に本籍地に確認することをおすすめします。
- 改製原戸籍簿が廃棄されている場合や、戦争・災害などで消失している場合は、「廃棄証明」や「消失証明」を交付してもらうことになります。
まとめ
改製原戸籍は、現在の戸籍だけでは把握できない過去の身分関係を確認するうえで欠かせない資料です。特に、遺産分割協議書の作成や遺言書の作成においては、法定相続人を正確に確定するために必要となるケースが多く見られます。しかし、改製原戸籍の取得や内容の読み取りは専門知識が求められ、一般の方にとっては複雑で時間のかかる作業となりがちです。相続や遺言の手続きを円滑に進めるためにも、改製原戸籍の扱いに精通した行政書士に相談・依頼することをおすすめします。専門家のサポートを受けることで、手続きの不備やトラブルを未然に防ぎ、安心して将来に備えることができます。